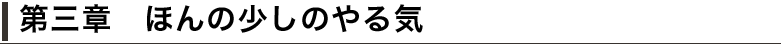次の日、授業の予鈴前。
隣で熱心に授業の予習を行うルミアを尻目に、システィーナは窓の外、フェジテの空に浮かぶ『メルガリウスの天空城』を頬杖つきながら、ぼんやりと眺めていた。
フェジテを象徴する空の城。どうしてそこにあるのか。いつからそこにあったのか。誰も知り得ない謎と不思議に満ちた幻の城。授業開始前に余裕があれば、それを遠望し、その神秘に思いを馳せるのがシスティーナの密かな日課だった。
……。
…………。
『ごらん、わしの可愛いシスティーナ。あれがメルガリウスの天空城だよ』
昨日、無神経な講師に偉大なる祖父を間接的に侮辱されたからだろうか。
ふと、システィーナの脳裏に懐かしい祖父の言葉が思い浮かんだ。
『どうじゃ? 綺麗じゃろう? あの城は気が遠くなるほど昔から、フェジテの空にあのように浮かんでいたのだよ。そう、何百年も……何千年も……ずっと、ずっと長い間……』
天空の城を語る祖父の目はいつだって、きらきらと輝いていたのを覚えている。
『ははは、皆がわしのことを、偉大な功績を残した魔術師だのなんだのと煽てるが……実はなんてことはない。わしが魔術を極めんとした理由はな……そう、たった一歩だけ、あの城に足を踏み入れたかった。あの荘厳なる全容を間近で一目だけ見てみたかった。何千年もの間、誰にも解けなかった空の城の謎を解き明かしたかった。それだけなのだよ』
その顔は幾ら歳を経て貫禄を得ても、まるで夢見る少年のようで――
『なにしろ、あの城は遥か太古に滅んでしまった魔法文明の残滓とも、母なる神がお創りたもうた神の御座とも、言われておる。伝説によれば、この世界の全ての叡智が眠っているとも。もし、それが真実ならば、一体誰が作ったのか、なぜあそこに存在しているのか……わしの頭上にはいつだってこの世で極上の不思議があったのだよ。思うだけで胸躍るこの浪漫……一魔術師として、この謎、挑んでみたくないわけなかろうて』
システィーナは天空城に関する祖父の考察や仮説、研究成果を聞くのが大好きだった。
だが……晩年、足腰が弱り、身体の調子の良くなかった祖父は、この話をする時、少しだけ寂しそうだった。
足を踏み入れてみたかった、一目だけ見てみたかった。語られる夢はみんな過去形で。
実体の無い、ただそこに見えるだけのまやかしの城。
魔術で空を飛んでそこへ至ろうにも、寄れば夢幻と消えてしまう蜃気楼の城。
それは、なまじ目の前にある分だけ、とても残酷な夢だ。
恐らく、晩年の祖父は悟っていたのだろう――もう、自分があの城に至ることはないのだ――と。
――お爺様は夢を諦めてしまったの?
いつだったか、システィーナはたまらなくなって、祖父にそう聞いたことがある。今思えばそれはとても残酷な質問だったかもしれない。
『……残念ながら、この世にはままならんことが多々あるものなのだよ……わしの父も、祖父も、曾祖父もな、皆、そうだった……あの城に至る糸口すらつかめずに……な』
だが、祖父はただ、優しくシスティーナの頭をなでた。
『本当に……残念なことじゃ……』
そう言って。
遠く懐かしく、眩い物を見るかのように、祖父は再び空の城に目を向ける。
天気は明朗、抜けるような青空に煌々と降り注ぐ陽光、半透明の城はとてもよく映えた。
その時。その燦爛たる城と、それを望む祖父の姿が、システィーナの魂を捕えた。
その祖父の背中が、眼差しが、あまりにも切なかったから――その空に浮かぶ幻影の城の姿があまりにも眩く、綺麗だったから――だから、その日、その時から、祖父の夢はシスティーナの夢になったのだ。
――だったら、私がやる――
――私が、お爺様以上に立派な魔術師になって――
――私が、お爺様の代わりに『メルガリウスの天空城』の謎を解いてみせるわ――
…………。
……。
「おい、白猫」
頭上から突然、ぶっきらぼうな言葉が降って来る。
システィーナの背中がびくりと震え、その意識が現実に立ち返る。目を向けずともわかる。いつのまにか自分のかたわらに立っているその男は、あの憎き非常勤講師だ。
「おい、聞いてんのか、白猫。返事しろ」
「し、白猫? 白猫って私のこと……? な、何よ、それ!?」
がたん、とシスティーナは肩を怒らせて席を立ち、グレンをにらみつけた。
「人を動物扱いしないで下さい!? 私にはシスティーナっていう名前が――」
「うるさい、話を聞け。昨日のことでお前に一言、言いたいことがある」
「な、何よ!? 昨日の続き!?」
システィーナは身構え、敵意に満ちた視線をグレンに送った。
「そこまでして私を論破したいの!? 魔術が下らないものだって決めつけたいの!? だったら私は――」
弁舌はグレンの方が上手だ。口論になれば勝てないだろう。だが、それでも、退くわけにはいかない。自分は祖父の夢を背負っているのだ。システィーナは無様をさらすことになろうとも徹底抗戦の決意を固めて――
「……昨日は、すまんかった」
「え?」
そして、最も予想だにしてなかった言葉に、システィーナは硬直した。
「まぁ、その、なんだ……大事な物は人それぞれ……だよな? 俺は魔術が大嫌いだが……その、お前のことをどうこう言うのは、筋が違うっつーか、やり過ぎっつーか、大人げねえっつーか、その……まぁ、ええと、結局、なんだ、あれだ、……悪かった」
グレンは気まずそうなしかめっ面で、目をそらしながら、しどろもどろと謝罪のような言葉をつぶやき、ほんのわずかな角度だけ頭を下げた。
ひょっとして、それは謝っているつもりなのだろうか?
「…………はぁ?」
その真意を量りかねて戸惑うシスティーナの前で、話はこれで終わりだと言わんばかりにグレンは踵を返し、教壇の方へと向かっていく。
そもそも、グレンは何しにここにやってきたのだろうか。まだ授業開始時間前だ。グレンが遅刻せずに教室にやってくるなんて……何かおかしい。
「なんだよ……? 何が起きてるんだよ……?」
「なぁ、カイ? ありゃ一体、どういう風の吹き回しなんだ?」
「お、俺が知るかよ……」
それはクラスの生徒達も同様で、あのグレンが授業開始前に教室に姿を現したことに困惑を隠せないようだった。
システィーナはどういうつもり? と言わんばかりの露骨な敵意に満ちた視線をグレンに送った。だが、当のグレンは腕組みをして黒板に背を預けて眼を閉じ、自身に集まるクラス中の猜疑の視線に完全無視を決め込んでいた。
やがて予鈴が鳴る。どうせ遅刻せずには来たけど立ったまま寝ているんだろ、との大方の予想を見事に裏切ってグレンは目を開き、教壇に立った。
そして信じられないことを言った。
「じゃ、授業を始める」
どよめきがうねりとなって教室中を支配した。誰もが顔を見合わせる。
「さて……と。これが呪文学の教科書……だったっけ?」
グレンが教科書を開いてぱらぱらとページをめくっていく。めくるごとにその顔が苦い物になっていく。やがて、グレンは露骨にため息をついて教科書を閉じた。
何事かと構える生徒達の前で、グレンは窓際へとずかずか歩み寄り、窓を開き……
「そぉい!」
窓の外へとその教科書を投げ捨てていた。
ああ、やっぱりいつものグレンだ。もうすっかり見慣れたグレンの奇行に、生徒達は失望のため息と共に各々自分の好きな教科書を開いた。今日も自習の時間が始まるのだ。
だが。
「さて、授業を始める前にお前らに一言言っておくことがある」
再び教壇に立ったグレンは一呼吸置いて――
「お前らって本当に馬鹿だよな」
なんかとんでもない暴言を吐いた。
「昨日までの十日間、お前らの授業態度見ててわかったよ。お前らって魔術のこと、なぁ~んにもわかっちゃねーんだな。わかってたら呪文の共通語訳を教えろなんて間抜けな質問出てくるわけないし、魔術の勉強と称して魔術式の書き取りやるなんていうアホな真似するわけないもんな」
今、まさに羽ペンを手に教科書を開き、魔術式の書き取りを行おうとしていた生徒達が硬直する。
「【ショック・ボルト】程度の一節詠唱もできない三流魔術師に言われたくないね」
誰が言ったか。しん、と教室が静まり返る。
そして、あちらこちらからクスクスと押し殺すような侮蔑の笑いが上がった。
「ま、正直、それを言われると耳が痛い」
ふて腐れたようにグレンはそっぽを向きながら小指で耳をほじる。
「残念ながら、俺は男に生まれたわりには魔力操作の感覚と、後、略式詠唱のセンスが致命的なまでになくてね。学生時代は大分苦労したぜ。だがな……誰か知らんが今、【ショック・ボルト】『程度』とか言った奴。残念ながらお前やっぱ馬鹿だわ。ははっ、自分で証明してやんの」
教室中に、あっと言う間に苛立ちが蔓延していく。
「まぁ、いい。じゃ、今日はその件の【ショック・ボルト】の呪文について話そうか。お前らのレベルならこれでちょうど良いだろ」
あまりにもひどい侮辱にクラスが騒然となった。
「今さら、【ショック・ボルト】なんて初等魔術を説明されても……」
「やれやれ、僕達は【ショック・ボルト】なんてとっくの昔に極めているんですが?」
「はいはーい、これが、黒魔【ショック・ボルト】の呪文書でーす。ご覧下さい、なんか思春期の恥ずかしい詩みたいな文章や、数式や幾何学図形がルーン語でみっしり書いてありますねー、これ魔術式って言います」
生徒達の不平不満を完全無視してグレンは本を掲げて話し始めた。
「お前ら、コイツの一節詠唱ができるくらいだから、基礎的な魔力操作や発声術、呼吸法、マナ・バイオリズム調節に精神制御、記憶術……魔術の基本技能は一通りできると前提するぞ? 魔力容量(キャパシティ)も意識容量(メモリ)も魔術師として問題ない水準にあると仮定する。てなわけで、この術式を完璧に暗記して、そして設定された呪文を唱えれば、あら不思議。魔術が発動しちゃいまーす。これが、あれです。俗に言う『呪文を覚えた』っていう奴でーす」
そして、グレンは壁を向いて左指を指し、呪文を唱えた。
「《雷精よ・紫電の衝撃以て・撃ち倒せ》」
グレンの指先から紫電が迸り、壁を叩いた。
相変わらずの三節詠唱に軽蔑の視線が集まるが、グレンは気にする素振りを見せない。たった今、自分が唱えた呪文をルーン語で黒板に書き表していく。
「さて、これが【ショック・ボルト】の基本的な詠唱呪文だ。魔力を操るセンスに長けた奴なら《雷精の紫電よ》の一節でも詠唱可能なのは……まぁ、ご存知の通り。じゃ、問題な」
グレンはチョークで黒板に書いた呪文の節を切った。
《雷精よ・紫電の・衝撃以て・撃ち倒せ》
すると三節の呪文が四節になった。
「さて、これを唱えると何が起こる? 当ててみな」
クラス中が沈黙する。
何が起こるかわからないというより、なぜそんなことを聞くのかという困惑の沈黙だ。
「詠唱条件は……そうだな。速度二十四、音程三階半、テンション五十、マナ・バイオリズムはニュートラル状態……まぁ、最も基本的な唱え方で勘弁してやるか。さ、誰かわかる奴は?」
沈黙が教室を続いて支配していた。答えられる者は誰一人いなかった。
優等生で知られるシスティーナすら、額に脂汗を浮かべて悔しそうに押し黙っている。
「これはひどい。まさか全滅か?」
「そんなこと言ったって、そんな所で節を区切った呪文なんてあるはずありませんわ!」
クラスの生徒の一人、ツインテールの少女――ウェンディがたまらず声を張り上げ、机を叩いて立ち上がる。
「ぎゃ――はははははッ!? ちょ、お前、マジで言ってんのかははははははっ!」
返ってきたのは下品極まりない嘲笑だった。
「その呪文はマトモに起動しませんよ。必ずなんらかの形で失敗しますね」
クラスではシスティーナに次ぐ成績を持つ男子生徒――ギイブルが立ち上がり、眼鏡を押し上げながら負けじと応戦する。
「必ずなんらかの形で失敗します、だってよ!? ぷぎゃ――ははははははははっ!」
「な――」
「あのなぁ、あえて完成された呪文を違えてんだから失敗するのは当たり前だろ!? 俺が聞いてんのは、その失敗がどういう形で現れるのかって話だよ?」
打ちひしがれたようにうつむくギイブルを尻目に、
「何が起きるかなんてわかるわけありませんわ! 結果はランダムです!」
ウェンディはさらに負けじと吠え立てるが――
「ラ ン ダ ム!? お、お前、このクソ簡単な術式捕まえて、ここまで詳細な条件を与えられておいて、ランダム!? お前らこの術、極めたんじゃないの!? 俺の腹の皮をよじり殺す気かぎゃははははははははははっ! やめて苦しい助けてママ!」
ひたすらグレンは人を小馬鹿にするように大笑いし続ける。
この時点でクラスの苛立ちは最高潮に達していた。
「もういい。答えは右に曲がる、だ」
ひとしきり笑い倒したグレンは四節になった呪文を唱えた。グレンの宣言通り、狙った場所へ直進するはずの力線は大きく弧を描くように右に曲がって壁へと着弾した。
「さらにだな……」
《雷・精よ・紫電の・衝撃以て・撃ち倒せ》
さらにチョークで節を切る。
「加えて射程が三分の一くらいになるかな」
これも宣言通りになった。
「で、こんなことをすると……」
《雷精よ・紫電 以て・撃ち倒せ》
今度は節を元に戻し、呪文の一部を消す。
「出力が物凄く落ちる」
グレンはいきなり生徒の一人に向けて呪文を撃った。
だが、撃たれた生徒は何も感じなかったようで目を白黒させる。
「ま、極めたっつーなら、これくらいはできねーとな?」
指先でチョークをくるくる回転させ、見事なまでのどや顔のグレン。
腹立たしいことこの上ないが、誰も何も言い返せない。このグレンという三流魔術師には術式や呪文について、自分達には見えていない何かが確かに見えているからだ。
「そもそもさ。お前ら、なんでこんな意味不明な本を覚えて、変な言葉を口にしただけで不思議現象が起こるかわかってんの? だって常識で考えておかしいだろ?」
「そ、それは術式が世界の法則に干渉をして――」
とっさにこぼれたギイブルのそんな発言を、グレンは即座に拾う。
「とか言うんだろ? わかってる。じゃ、魔術式ってなんだ? 式ってのは人が理解できる、人が作った言葉や数式や記号の羅列なんだぜ? 魔術式が仮に世界の法則に干渉するとして、なんでそんなものが世界の法則に干渉できるんだ? おまけになんでそれを覚えないといけないんだ? で、魔術式とは一見なんの関係もない呪文を唱えただけで魔術が起動するのはなんでだ? おかしいと思ったことはねーのか? ま、ねーんだろうな。それがこの世界の当たり前だからな」
これはまさにグレンの指摘どおりで、生徒達の誰もが――システィーナすらも、そういうものだと勝手に流してしまっていたことだった。なにしろ、そんなことを考えなくても術式と呪文を一生懸命覚えれば使える魔術はどんどん増えていく。魔術の勉強で浮かぶ疑問と言えば習得や実践法に関することばかりで、根本的な理屈に関しては二の次だった。
そして、習得することそれ自体が楽しくて誇らしくて、皆、覚えた呪文の数ばかりを競ってきた。習得した呪文の数が優秀さの証だった。そういう根本的なことを突き詰めて考える余裕は生徒達にはなかったのだ。
「つーわけで、今日、俺はお前らに、【ショック・ボルト】の呪文を教材にした術式構造と呪文のド基礎を教えてやるよ。ま、興味ない奴は寝てな」
しかし、今この教室内において欠片でも眠気を抱いている生徒は誰一人いなかった。
グレンはまず魔術の二大法則の一つ『等価対応の法則』の復習から始めた。
大宇宙すなわち世界は、小宇宙すなわち人と等価に対応しているという古典魔術理論である。世界の変化は人に、人の変化は世界に影響を与えるというものだ。
「占星術なんてまさに等価対応の賜物だよな。星の動きを観察して、人の運命を読む。つまり、世界の影響が人に及ぼす影響を計算する術だ。魔術ってのはその逆なわけだ」
では、魔術式とは何か?
それは世界に影響を与えるものではない。人に影響を与えるものだ。人の深層意識を変革させ、それに対応する世界法則に結果として介入する、それが魔術式の正体だ。
「要するに魔術式ってのは超高度な自己暗示っつーコトだ。だから、お前らが魔術は世界の真理を求めて~なんてカッコイイことよく言うけど、そりゃ間違いだ。魔術は人の心を突き詰めるもんなんだよ」
つまりルーン語とは最も効率良く、効果的かつ普遍的に、自己暗示による深層意識変革を起こせるよう、人間が長い歴史の中で編み出した暗示特化専用言語に過ぎない。
「何? たかが言葉ごときに人の深層意識を変えるほどの力があるのが信じられないだって? ……ったく、あー言えばこう言う奴らだな……おい、そこの白猫」
「だから私は猫じゃありません! 私にはシスティーナって名前が――」
「……愛している。実は一目見たときから俺はお前に惚れていた」
「は? ……な、……な、なななな、貴方、何を言って――ッ!?」
「はい、注目ー。白猫の顔が真っ赤になりましたねー? 見事に言葉ごときが意識になんらかの影響を与えましたねー? 比較的理性による制御のたやすい表層意識ですらこの有様なわけだから理性のきかない深層意識なんて――ぐわぁっ!? ちょ、この馬鹿! 教科書投げんなッ!?」
「馬鹿はアンタよッ! この馬鹿馬鹿馬鹿――ッ!」
一騒動の後、顔を真っ赤に腫らしたグレンは術式と呪文の関係について話し始める。
「核心を先に言っちまえば、やっぱ文法と公式みたいなのがあるんだよ。深層意識を自分が望む形に変革させるためのな」
そして、グレンは呪文とは深層意識に覚え込ませた術式を有効にするキーワードと説明する。このキーワードを唱えることで、術式が深層意識を変革させる。
「ま、要は連想ゲームだわな。例えば、そこの白猫娘と聞けば白髪、と誰もが連想するように呪文と術式の関係も同じだ。ルーンで呪文を括ることで相互――痛ぇッ!? ちょ、頼むから教科書投げないでぉおぶはぁッ!?」
グレンの顔に、さらに本の痕がつく。
「要するに、呪文と術式に関する魔術則……文法の理解と公式の算出方法こそが魔術師にとっては最重要なわけだ。なのにお前らと来たら、この部分を平気ですっとばして書き取りだの翻訳だの、覚えることばっか優先しやがって。教科書も『細かいことはいいんだよ、とにかく覚えろ』と言わんばかりの論調だしな」
生徒達も今度こそ、ぐうの音も出ない。
「要するに、だ。呪文や術式を分かりやすく翻訳して覚えやすくすること、これがお前らの受けてきた『分かりやすい授業』であり、ガリガリ書き取りして覚えること、これがお前らの『お勉強』だったんだろ? もうね、アホかと」
グレンは肩をすくめて、呆れ返ったように鼻を鳴らした。
「で、その問題の魔術文法と魔術公式なんだが……実は全部理解しようとしたら、寿命が足らん……いや、怒るな。こればっかりはマジだ。いや、本当に」
ここまで持ち上げておいてなんだと、非難めいた視線がグレンに集まる。
「だーかーら、ド基礎を教えるっつったろ? これを知らなきゃより上位の文法公式は理解不可能、なんていう骨子みたいなもんがやっぱあるんだよ。ま、これから俺が説明することが理解できれば……んーと」
少しの間、グレンはこめかみを小突きながら考え込んで。
「《まぁ・とにかく・痺れろ》」
三節のルーンで変な呪文をゆっくり唱えた。
すると、驚くことに【ショック・ボルト】の魔術が起動した。生徒達は目を丸くした。
「あら? 威力が思ったより弱いな……まぁいい、こんな風に即興でこの程度の呪文なら改変することくらいはできるようになるか? 大抵精度落ちるからお勧めしないが」
ここに来て、ようやく生徒達のグレンを見る目が変わってくる。
「じゃ、これからいよいよ基礎的な文法と公式を解説すんぞ。ま、興味ない奴は寝てな。正直マジで退屈な話だから」
しかし、今この教室内において欠片でも眠気を抱いている生徒はやはり、誰一人としていなかった。
――――。
――同時刻。フェジテの某所にて。
『計画は順調か?』
「ええ、順調ですよ?」
一筋の光も差さぬ真っ暗闇の中、その男は柔和な笑みを浮かべながら、耳元に当てた半割りの宝石から響いてきた声の質問に答えた。
『で? その講師……ヒューイ=ルイセンは今、どこに?』
「はは、『彼』ですか? もちろん『消えました』」
『ふっ、はははっ、そうか『消えた』か』
「……はい。問題は『彼』の後釜に入ってきた方なのですが」
『グレン=レーダス、か。講師の補充は想定内だが、まさかここまで早いとはな。どうもあの魔女の差し金らしい』
「はは、万事が上手くいくというわけはありませんから」
男は肩をすくめて、おどけてみせる。
「しかし、あのアルフォネア教授が直々に連れて来た魔術師……大丈夫なのでしょうか?」
『グレンが我々の計画の障害となるか否かについてだが、私は問題ないと判断した』
「そうなのですか?」
『ああ。このグレンという男。あの魔女が連れて来た魔術師ということで警戒して調べてみれば……なんてことはない。第三階梯(トレデ)止まりの三流魔術師。我々の敵ではない』
「となるとやはり……」
『ああ、計画実行予定日はやはり、件の魔術学会開催の日だ。その日、学院の主要な教授、講師格の魔術師達は全員魔術学院を出払う。そして、その日は『あの』クラスの生徒達だけが、魔術学院に来ることになる。まさに絶好の日だ』
「……目標がなんらかの事情で学院の授業を欠席した場合はどうしますか?」
『計画を破棄すればいいだけの話。元よりあの組織にとって今回の作戦、そして我々の価値などその程度だ』
「はは、難儀な組織に忠誠を誓ったものですね、我々も」
『構わん。あの組織は私に全てを与えてくれる』
「お互い様、というわけですか?」
『ああ』
「ふふ、では計画の成功を祈りましょう。天なる智慧に栄光あれ――」