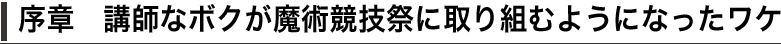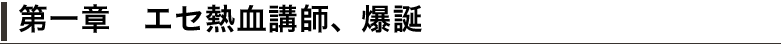アルザーノ帝国魔術学院、放課後の学院長室にて。
「——と、いうわけで。給料の前借り、もしくはお小遣いをプリーズ」
「《ふざけんな・この・馬鹿野郎》——ッ!」
突如、紅蓮の炎と衝撃が渦巻き、爆音が響き渡った。
セリカが唱えた爆裂呪文が、戯言をほざいたグレンに容赦なく炸裂したのだ。
その爆発の余波によって部屋の窓ガラスは吹き飛び、レースカーテンは灰化、壁は焼け焦げ、絨毯は炭化。煌びやかな絵画や古めかしい本棚、磨き抜かれた飾り鎧、ソファーにシェードランプなどと言った品の良い調度品の数々は無残に半壊——学院長室の内装は、もはや見る影もなかった。
「ごほっ!? がはごほげほっ!? な、何すんだ、殺す気かテメェ!?」
真っ黒焦げになったグレンが床に這いつくばりながら、非難がましい声を上げる。
「やっかましい! 生物の種の保存に関わる重大な相談があるとか言って、何かと思って身構えてたら、そんなことか!?」
「そんなこととはなんだ!? もし、俺が餓死したら、俺が絶滅しちゃうだろ!? 俺は世界に一匹しかいないんだぞ!? 絶滅危惧種なんだぞ!? 大事にしろよ!?」
「うっさい、絶滅しろ! むしろ、そんな劣等種、手ずから根絶してやるわ!」
不毛な取っ組み合いを始めるグレンとセリカの間に、この騒ぎにも動じず執務机に腰かけ、二人の動向を見守っていたこの部屋の主——リック学院長が割って入った。
「まぁまぁ、二人とも落ち着きなさい。何か物凄く回りくい言い回しじゃったが……つまり、グレン君は生活費……主に食費としてのお金が必要なのかな?」
「その通り。さっすが学院長、話がわかる! いやー、セリカの奴がさぁ? 最近になって突然、自分の食費くらい自分で出せとか言いだすからさー?」
「当然だろう! 無職の時ならいざ知らず、今は学院の魔術講師として立派な収入があるんだからな!」
セリカがイライラとしかめっ面で腕組みして、グレンを睨みつける。
「とにかく、俺、今月ヤバイんっすよ、学院長! このままじゃ明日から半強制的な減量(ダイエツト)に突入する羽目に……」
「しかし、先週、給料日だったばかりじゃぞ? 君は一体、何にそんなにお金を使ったのかね?」
その問いに、グレンは憂いを湛えた表情で窓際に歩み寄り、外の風景に目を向けた。
窓の外には、植樹と色とりどりの花が踊る花壇で飾られた学院敷地内の庭園光景と、鉄柵を挟んでその外側に広がるフェジテの古風な町並み——そして、その遙かなる上空に浮かぶ雄大な幻の城——フェジテの象徴、メルガリウスの天空城の偉容があった。
「何に使ったかとおっしゃいましたか……それはもちろん、未来へと投資したんですよ」
「未来に投資?」
「ええ、明日という無限の可能性のため、そして、より多くの希望を掴むために——」
遠い目で語るグレンに、セリカがボソリと口を挟む。
「要するにギャンブルでスッたのか。本当に救えないな。もう死ねよ、お前」
「やめてよね、せっかく人が格好良く決めてるのに水を差すの」
身もフタもないセリカの言い草に、グレンは口を尖らせて抗議した。
「大体、俺が悪いんじゃないぞ!? あそこでハートの3が来るのが悪いんだッ! 4以上のカードだったら、俺はぁーッ!?」
なんかもう、ダメ人間の見本だった。
「——というわけで、助けて下さい、お二方」
「しかしなぁ……規則は規則なわけで、給料の先払いはできんのだよ」
「ぐっ、そうなんすか……困った。高利貸しの連中も、定職について間もないお前には貸せないとかケチ臭いこと言うし、セリカも屋敷の食料庫に魔術の鍵かけてやがるし……」
望みを絶たれたグレンは掌で顔を覆って、ため息をついた。
「なぁ、セリカ君。次の給料日まで食費だけでも融通してやったらどうかね? グレン君は君の屋敷に部屋を間借りして、一緒に暮らしているのだろう?」
そんなグレンを少し気の毒に思ったのか、リックがセリカにそんな提案をする。
「お断りだ、学院長。こいつを甘やかしたらロクなことにならんからな。そもそもが全部自業自得、たまには良い薬だ。ま、頑張って次の給料日まで生き延びな」
だが、対するセリカの反応はけんのほろろだ。
「食費さえ入れれば、昔からのよしみで食事の世話くらいはしてやるさ。食費さえ入れればな。それが最低条件だ。ただでさえ、家賃は見逃してやってるんだからな」
「ほら、聞きました? 学院長。まったく、セリカの奴、これなんですもの……昔から本当にワガママな奴でして……やれやれ、困ったもんです」
グレンは呆れ顔で嘆息し、口の端を釣り上げ、肩をすくめて鼻で笑い——
「な ん で、私が悪いような話になってるんだよ!? 悪いのはお前だろうが!?」
「ちょ、ギブ!? こめかみ痛い!? 頭つぶれる!? 助けてママぁああ——ッ!?」
セリカは掌でグレンの頭蓋を、ぎりぎりと万力のように締め上げた。
上がるグレンの情けない悲鳴に、リックは苦笑いをしながら一つの提案をする。
「給料の先払いはできんが、特別賞与は出せる可能性があるぞ、グレン君」
「特別賞与ですと!?」
その言葉に、グレンはセリカの手を振り払い、リックの下へ素早く馳せ参じた。
「それは一体、なんなんですか!?」
「来週、学院で開催される『魔術競技祭』じゃよ」
「な!? ま、魔術競技祭……? それは一体……?」
「うむ、我らがアルザーノ帝国魔術学院で年に三度に分けて開催される、学院生徒同士による魔術の技の競い合いじゃ。それぞれの学年次ごとに、各クラスの選手達が様々な魔術競技で技比べを行い、総合的に最も優秀な成績を収めたクラスの担当講師には、恒例として特別賞与が出ることになっておる」
「なんと、マジっすか!? そんな素晴らしいイベントがあったんですか!?」
「来週に開催される魔術競技祭は、ちょうどグレン君の担当するクラスが参加する二年次生の部じゃ。ここは一つ、特別賞与狙いに頑張ってみてはどうかね?」
「はい、頑張らせていただきます! それにしても、魔術競技祭……そんなものがあったとは!? くっ! もっと早く教えていただけていればッ!?」
グレンの現金な発言に、セリカはこめかみを押さえ、冷ややかな呆れ顔で呟いた。
「いや、お前、この学院の卒業生だろ、なんで知らないんだよ? 大体、二年次生の連中はどのクラスも盛り上がってただろ。なにしろ今回は特別に女王陛下が——」
「ええい、こうしちゃいられん! 俺にはやらねばならないことがある! ちっ、あいつら、まだ残っていればいいが——さらば!」
だが、セリカの突っ込みなどグレンは露ほどにも聞いていなかった。何を思ったか、握り拳を固めて踵を返し、慌ただしく学院長室を飛び出していく。
そんなグレンの後ろ姿を、セリカはため息混じりに見送った。
「……で? 学院長。現実的な話、グレンのクラスは優勝できるのか?」
「……正直、厳しいじゃろうな」
リックは微妙な表情で、セリカの問いに応じた。
「確かにグレン君のクラスには、学年トップクラスの成績優秀者であるシスティーナ君がいるが……総合力でハーレイ君の一組の優勝が固いと、もっぱらの評判だ」
「ああ、ハーレイ担当のクラスか。あそこはやたら粒が揃ってるからな……」
「うむ、彼のクラスはとにかく成績優秀者が多く、層が厚い。いくらシスティーナ君がいるとは言え、彼女を全競技種目で使い回してもおよばんじゃろうて」
「全種目で使い回す……ね」
その時、セリカはなぜか辟易したように息をつく。
「いいのかね? セリカ君。このままだと君の愛弟子殿は本当に餓死してしまうかもしれんぞ? 助けてやらんのかね?」
「ま、それは心配ないさ、学院長」
セリカはあっけらかんと応じた。
「あいつなら草を食うなり、枝をかじるなりなんなりで生き延びるさ。昔、そういうことも教えたしな。それよりも、あのまま捨て置いた方がどうやら面白くなりそうだ」
「……ほう?」
そんなセリカの物言いに、学院長も興味を引かれたように口の端を釣り上げる。
「動機はアレだがグレンの奴、ようやく『その気』になったようだ。ここ最近、競技祭に蔓延する例の風潮にはうんざりしていたとこだが……さて、あいつはどうするかな?」
どこか楽しそうにセリカは笑った。
放課後のアルザーノ帝国魔術学院、東館二階。
その時、魔術学士二年次生二組の教室は、びっくりするほど盛り下がっていた。
「はーい、『飛行競争』の種目に出たい人、いませんかー?」
壇上に立ったシスティーナがクラス中に呼びかけるが、誰も応じない。
クラスメイト達は皆、一様にうつむいたまま、教室は葬式のように静まり返っている。
「……じゃあ、『変身』の種目に出たい人ー?」
やはり、無反応。教室は静まり返ったままだった。
「はぁ、困ったなぁ……来週には競技祭だっていうのに全然、決まらないなぁ……」
システィーナは頭を掻きながら、黒板の前で書記を務めるルミアに目配せする。
ルミアは一つ頷き、穏やかながら意外によく通る声でクラスの生徒達に呼びかけた。
「ねぇ、皆。せっかくグレン先生が今回の競技祭は『お前達の好きにしろ』って言ってくれたんだし、思い切って皆で頑張ってみない? ほら、去年、競技祭に参加できなかった人には絶好の機会だよ?」
それでも、誰も何も言わない。皆、気まずそうに視線を合わせようとしない。
「……無駄だよ、二人とも」
その時、この膠着状態にうんざりした眼鏡の少年が席を立った。
少年の名はギイブル。このクラスではシスティーナに次ぐ優等生だ。
「皆、気後れしてるんだよ。そりゃそうさ。他のクラスは例年通り、クラスの成績上位陣が出場してくるに決まってるんだ。最初から負けるとわかっている戦いは誰だってしたくない……そうだろ?」
「……でも、せっかくの機会なんだし」
むっとしながら反論しようとするシスティーナを無視し、ギイブルが続ける。
「おまけに今回、僕達二年次生の魔術競技祭には、あの女王陛下が賓客として御尊来になるんだ。皆、陛下の前で無様をさらしたくないのさ」
嫌味な物言いだが、ギイブルの言はクラスに蔓延する心情を的確に突いていた。
「それより、システィーナ。そろそろ、真面目に決めないかい?」
「……私は今でも真面目に決めようとしてるんだけど?」
「ははっ、冗談上手いね。足手まとい達にお情けで出番を与えようとしてるのに?」
ギイブルは皮肉げな薄笑い口の端に浮かべ、クラスの生徒達を一瞥する。
「見なよ。君の突拍子もない提案のおかげで、元々、競技祭に出場する資格があった優秀な連中も気まずくなっちゃって萎縮している……もういいだろう?」
「わ、私はそんなつもりじゃ!? それに皆のことを足手まといだなんて……ッ!」
眉を釣り上げ、声を荒げるシスティーナ。
ギイブルはそれをさらりと受け流し、さらに歯に衣着せぬ言葉でたたみかける。
「綺麗事はいいよ。そんなことより、さっさと全競技を僕や君のようなクラスの成績上位陣で固めるべきだ。そうしなければ他のクラスに……特にハーレイ先生が率いる一組に勝てるわけがない」
「勝つことだけが競技祭の目的じゃないでしょう? それに、それ去年もやったけど……なんか凄くつまらなかったし……」
「勝つことだけが目的じゃない? つまらない? 何を言ってるんだ、君は。魔術競技祭はつまるつまらないの問題じゃないだろう?」
ギイブルはシスティーナの言い分を鼻で笑った。
「めったなことじゃ魔術の技比べができないこの学院において、誰が本当に一番優れた魔術の技を持っているのか——それを明白にできる数少ない機会が魔術競技祭じゃないか」
「それはそうかもしれないけど……ッ!」
「しかも、この競技祭には学院の卒業者……魔導省に勤める官僚や、帝国宮廷魔導士団の団員の方々も数多く来賓としていらっしゃるんだ。魔術競技祭は将来それらを目指す生徒達にとって、絶好のアピールの場でもある。僕ら成績優秀者にその機会がより多く与えられるのは当然と思わないかい?」
「ねぇ、貴方、それ本気で言ってる……?」
怒りも露わにシスティーナがギイブルを睨みつける。
だが、ギイブルはどこ吹く風で、さらに持論を展開していく。
「それにさ、今回の優勝クラスには、女王陛下から直々に勲章を賜る栄誉が与えられるんだ。これにどれほどの価値があるのか、君にもわかるだろう? システィーナ。だから、だだこねてないで大人しく出場メンバーを成績上位陣で固めるんだ。これはこのクラスのためでもあるのさ」
「ギイブル……貴方、いい加減に——」
恐らく場の雰囲気は最悪になるだろう——それを理解していながらも、とうとう我慢できなくなったシスティーナが怒声を上げようとした、その時だった。
ドタタタタ——と、外の廊下から駆け足の音が迫ってきたかと思えば……次の瞬間、ばぁんっ! と、派手に音を立てて教室前方の扉が開かれた。
「話は聞いたッ! ここは俺に任せろ、このグレン=レーダス大先生様にな——ッ!」
両袖に腕を通さず羽織ったローブが、無意味にバサリと翻る。
開け放たれた扉の向こうには、人差し指を前に突き出し、不自然なほど胸を反らして、全身をねじり、流し目で見栄を切る、という謎のポーズを決めたグレンがいた。
「……ややこしいのが来た」
システィーナが頭を抱えてため息をついた。
あまりにも意味不明の登場の仕方に思わず呆然とするクラス一同を前に、グレンはシスティーナを押しのけるように教壇に立った。
「喧嘩はやめるんだ、お前達。争いは何も生まない……何よりも——」
グレンはきらきらと輝くような、爽やかな笑みを満面に浮かべて——
「俺達は、優勝という一つの目標を目指して共に戦う仲間じゃないか」
(——キモい)
その瞬間、クラス一同の心情は見事に一致した。なんとも悲しい統率力だった。
「まぁ、なんだ。なかなか種目決めに難航しているようだな、お前達」
そんなクラスに流れる微妙な空気を微塵も読まず、グレンはどこまでもマイペースに話を続ける。実にいつも通りである。
「ったく何やってんだ、やる気あんのか? 他のクラスの連中はとっくに種目を決めて、来週の競技祭に向けて特訓してんだぞ? やれやれ、意識の差が知れるぜ」
「やる気なかったのは先生でしょ!?」
あまりにもあんまりな言い草に、流石にシスティーナが突っ込みを入れる。
「大体、先生ったら先日、私が競技祭について聞いた時、『お前らの好きにしろ』って言ってたじゃないですか! なんで今頃になってそんなこと言うんですか!?」
「……え?」
いかにも心外だとばかりに、きょとんとするグレン。
「……俺、そんなこと言ったっけ? いや、マジで覚えがないんですけど」
「あぁ……やっぱり面倒臭がって、人の話、全っ然、聞いてなかったんですね……」
グレンの相変わらずの平常運転ぶりに、システィーナは激しく脱力して突っ伏した。
「まぁ、んなことはどうでもいいとして、だ。お前らに任せて決まらない以上、ここはこのクラスを率いる総監督たるこの俺が、超カリスマ魔術講師的英断力を駆使し、お前らが出場する競技種目を決めてやろう。言っておくが——」
野心と熱情に煌々と燃えた瞳で、グレンが偉そうに宣言する。
「俺が総指揮を執るからには勝ちに行くぞ? 全力でな。俺がお前らを優勝させてやる。だから、そういう編成をさせてもらう。遊びはナシだ。心しろ」
ざわざわ。普段の低温動物ぶりからは想像もつかないこの熱血ぶりに、クラス中の生徒達がどよめきながら顔を見合わせる。
「おい、白猫。競技種目のリストをよこせ。ルミア、悪いが今から俺が言う名前と競技名を順に黒板へ書いていってくれ」
「人を猫扱いするなって言ってるのに……もう!」
「はい、わかりました、先生」
システィーナが不満そうにリストを手渡し、ルミアがチョークを構えた。
「ふむ……」
グレンが真剣な眼差しで、競技種目とそのルールが書かれたリストに目を通し始める。
「なぁ、おい、白猫。これって毎年同じ競技なのか?」
「違うわ。『決闘戦』とか、いくつかの例外を除いて、去年とまったく同じ競技をやるということはほとんどないわ。今までになかった新しい競技も突然作られたりするし、一見同じ競技でもルールが変わっていたり……」
「なるほど、生徒達の応用力を試す意味合いもあるか。つーことは……ふむ……」
システィーナはグレンのそんな様子を横目で流し見ながら、小さく嘆息した。
(まったく、なんで突然、やる気になったのかしら?)
グレンは紆余曲折を経て、このクラスを担当することになった魔術講師である。質の高い授業こそ行うものの、自身の魔術研究には関してはさっぱりやる気がなく怠惰、あまつさえ崇高なる魔術を小馬鹿にする問題発言を繰り返す魔術師失格のダメ人間……というのがこの学院内における、グレンに対する共通認識である。
だが、システィーナは知っている。普段のグレンはダメ人間だが、いざという時には己が命を張って自分以外の誰かのために戦える——そんな熱い人間であることを。
グレンのそんな一面を知っているからこそ、システィーナはグレンに対して普段は説教ばかりだが、決定的に愛想を尽かす気にはなれない。
今回もそうだ。むしろ、やる気になってくれたことを好ましく思うくらいである。
(でも……なんて言うか、間が悪いなぁ……)
システィーナは心の中で、ほんの少しだけ苦々しく思った。
グレンはこう言ったのだ。全力で勝ちに行く、と。
この魔術競技祭において全力で勝ちに行くということは、凡庸な成績の生徒達は出場させず、クラスの成績上位者数名を全ての種目で使い回すという、例年お決まりの編成をするということだ。
(はぁ……何もこんな時にやる気出さなくたって……)
システィーナは事実、学年で五本の指に入る成績優秀者だ。当然、去年もそんなお決まりに従って、一年次生の部の魔術競技祭に出場したのだが……面白くなかった。父親から聞かされていた話とずいぶん違った。昔はクラス全員が参加して、全員一緒に盛り上がったお祭りだったらしいのだが、そんな競技祭はいつの間にか廃れてしまったらしい。
だから、グレンが好きにしろと言ってくれたのは、それはそれでよかったのだ。
皆で参加すれば、きっと楽しくなる。
父親から聞いていたような楽しい魔術競技祭になる——そう思ったのだ。
だが、食い入るようにリストを見つめるグレンの真剣な表情を見る限り、今年も父親から聞かされていたような、楽しい魔術競技祭になることはなさそうだった。
はぁ、と諦めたかのように、システィーナが寂しい嘆息をこぼしていると。
「……よし、大体わかった」
グレンが顔を上げる。とうとう参加メンバーを発表するらしい。
「心して聞けよ、お前ら。まず一番配点が高い『決闘戦』——これは白猫、ギイブル、そして……カッシュ、お前ら三人が出ろ」
えっ? と。その時、クラス中の誰もが首をかしげた。
競技祭の『決闘戦』は、三対三の団体戦で実際の魔術戦を行う、最も注目を集める目玉競技であり、各クラス最強の三人を選出するのが常だ。
だが、成績順で選ぶならば、システィーナ、ギイブルの次に来るのはウェンディのはずなのだ。なぜ、ここで成績的にはウェンディに劣るカッシュが出てくるのか。
指名されたカッシュ自身も、この謎の選抜に戸惑いを隠せないようだった。
だが、グレンはクラス中に渦巻く困惑を完全に無視し、さらに続ける。
「えーと、次……『暗号早解き』。これはウェンディ一択だな。『飛行競争』……ロッドとカイが適任だろ。『精神防御』……ああ、こりゃルミア以外にありえんわ。えーと、それから『探知&開錠競争』は——『グランツィア』は——」
次々と発表される参加メンバーに生徒達は気付いた。複数の競技種目に何度も使い回されている生徒が一人もいない。成績上位者で固めたい、配点の高い競技にも平気で上位の生徒を差し置いて下位の生徒を割り当てたりしている。察するに、グレンはクラス四十人全員を、なんらかの競技種目に出場させるつもりらしかった。
全力で勝ちに行くのではなかったのか? 遊びは無しじゃなかったのか?
グレンの意図が読めず、クラス一同等しく当惑していると。
「——で、最後、『変身』はリンに頼むか。よし、これで出場枠が全部埋まったな」
グレンのメンバー発表が終わった。結局、選を漏れた生徒は一人としていない。四十人全員、最低一回は何かしらの競技に出場することになっていた。
「何か質問は?」
「私は納得いたしませんわっ!」
生徒達がざわめく中、いかにもお嬢様然としたツインテールの少女、ウェンディが早速、言葉荒々しく立ち上がる。
「どうして私(わたくし)が『決闘戦』の選抜から漏れているんですの!? 私の方がカッシュさんより成績がよろしくってよ!?」
「あー、それなんだがな……」
少し言い辛そうにグレンがこめかみを掻いた。
「お前、確かに呪文の数も魔術知識も魔力容量(キャパシティ)もスゲェけど、ちょっと、どん臭ぇトコあるからなー。突発的な事故に弱ぇし、たまに呪文噛むし」
「な——ッ!?」
「だから、使える呪文は少ねーが、運動能力と状況判断のいいカッシュの方が『決闘戦』やるなら強ぇって判断した。気を悪くしたんなら謝る。その代わり『暗号早解き』、これはお前の独壇場だろ? お前の【リード・ランゲージ】の腕前は、このクラスの中じゃ文句なしのピカ一だしな。ここは任せた。ぜひ点数稼いでくれ」
「ま、まぁ……そういうことでしたら……言い方が癪に障りますけど……」
怒るに怒れず、反論もできず、ウェンディはすごすごと引き下がる。
他にも、どうして自分がこの種目に選ばれたのか、疑問に思った生徒達が次々と手を上げ、グレンに問いかける。
「そりゃ【レビテート・フライ】も【グラビティ・コントロール】も結局は同じ重力操作系の黒魔術だし、黒魔術は運動とエネルギーを操る術ということでどれも根底は同じだ。カイ、お前ならいけるはずだ」
「テレサ、お前、この間、錬金術実験で誰かが落としかけたフラスコを、とっさに【サイ・テレキネシス】で拾ってたろ? お前、自分で気付いてないだけで念動系の白魔術、特に遠隔操作系の術式に相性がいい」
「グランツィアは、個々の能力うんぬんよりチームワークだ。いつも仲良し三人組のお前らがやるのが多分、一番いいんじゃねーか? お前ら同調詠唱(シンクロ)も上手いしな」
だが、それら生徒達の疑問にグレンは一応、筋の通った答えを返し続ける。
要するに、グレンは生徒達の、普段は目立たなくとも実は尖っている長所を最大限生かした編成をしたらしかった。
なぜグレンが突然、やる気になったのかは不明だし、全力で勝ちに行くと言うわりには非効率なことをやっている感は否めないが、グレンはグレンなりに最強の編成を考えたようだった。
(しかも、これって……)
システィーナは黒板に並んだ名前を見る。基本的には各生徒達の得意分野を生かし、得意分野から外れていたとしても、得意分野からの応用で対応できるよう、よく考えられている。これは常日頃から生徒達のことをよく見て、得手不得手を細かく熟知していなければできない編成だ。普段、自分が教える生徒達のことなどまったく興味がないような素振りのグレンだが、一応、きちんと見ていたらしい。
(先生って、本っ当にダメ人間だけど……たまに、こういうとこあるからなぁ……)
生徒達の疑問に応対するグレンの姿を、システィーナは少し微笑ましく見つめていた。
「——さて、他に質問は?」
グレンが辺りを見渡す。
もはや、グレンの編成に対する反論は何一つない。
「じゃ、これで決まりってことでいいか?」
内心ほくそ笑みながら、グレンは生徒達に問いかけた。
(ふぅー、やれやれ、上手くいった……)
グレンの目標はとにかく、勝つことだ。なんとしても勝たねばならない。勝って、特別賞与をもらわなければならない、生きるために。ていうか、餓死は嫌だ。セリカは助けないと言ったら本当に助けない非情で冷たい奴なのだ。
ゆえに、勝つためには多少強引でも、ここで勝率を最大限高める編成を押し通さねばならなかった。いくらお祭りだからと言って、遊び感覚で各人やりたい競技を適当に決められてしまっては困るのだ。勝つために、あざとい編成をしなければならなかった。
なんやかんやで第一目標はうまくいきつつある。このクラスの生徒四十人で優勝を目指すならば、グレンが提案した編成が間違いなくベストのはずだ。
(ふっ……あざといとか言うなかれ、勝利以外に価値はあらず、勝てば官軍なのさ……まぁ、できるならシスティーナとか全種目で使い回したいんだけどな……)
確かに生徒達の尖っている部分を最大限生かすように編成はしたが、それが成績上位者との根本的な実力差を覆せる物ではないことを、グレンは理解している。あくまで、いい勝負ができるようになるだろう程度の気休めに過ぎない。さらに本気で勝ちに行くならば成績上位者のみで全種目を固める、などということをするべきだろう。
(……けど、そりゃ流石に反則だろうしな……まぁ、しゃーない、この四十人を上手く使って、勝率を最大限高めて挑むっきゃねぇ……)
グレンがそんなことを考えていると。
「やれやれ……先生、いい加減にしてくださいませんかね?」
ゆらりと、生徒の一人が立ち上がった。ギイブルだ。
「何が全力で勝ちに行く、ですか。そんな編成で勝てるわけないじゃないですか」
「む……?」
まさか、自分が考えた編成以上に勝率が高まる編成があるのか。
もし、あるのならば、そっちを採用するに決まっていた。グレンにとっては、もはや講師としてのプライドや威厳の問題じゃないのだ。餓死の瀬戸際なのだから。
「ほう? ギイブル。ということはお前、俺が考えた以上に勝てる編成ができるのか? よし、言ってみてくれ」
「……あの、先生、本気でそれ言ってるんですか?」
苛立ちを隠そうともせず、吐き捨てるようにギイブルは言い放った。
「そんなの決まってるじゃないですか! 成績上位者だけで全種目を固めるんですよ! それが毎年の恒例で、他の全クラスがやってることじゃないですか!」
「…………え?」
グレンの動きが止まる。
え? 何それ? そんなんいいの? 硬直しながらとめどない思考が流れていく。どうも、自分はひどい勘違いをしていたらしい。
(あ、なぁーんだ。一人の生徒を複数の種目に使い回していいんだ、毎年の恒例なんだ、どこもやってることなんだ、へぇー、そうなんだー、ほぉー、ふぅーん……)
それを聞いたグレンは内心、ガッツポーズを決めていた。
(よっしゃ……ぐへへ、この編成でも充分あざとくて、どん引きされるかと思ったが、そういうことなら、もう容赦しねえ。さらにあざとい編成を考えてやるぜ……ッ!)
特にシスティーナは容赦なくコキ使ってやる。あの白猫娘は生意気だが、なんかもう、とにかく優秀であることだけは間違いないのだ。生意気で生意気だが。システィーナが多くの競技種目に参加してくれれば、それだけで優勝確率が跳ね上がるのだ。
「うむ……そうだな、そういうことなら……」
グレンがギイブルの意見に首肯しようとした、その時だ。
「何を言ってるの、ギイブル! せっかく先生が考えてくれた編成にケチつける気!?」
ギイブルに真っ向から反論する少女がいた。システィーナだ。
(ちょ——おま、何、ギイブル君に反論しちゃってるの——ッ!?)
焦燥に満ちたグレンの胸中も露知らず、システィーナはクラス一同に向き直ると、真摯な表情で訴えかける。
「皆、見て! 先生の考えてくれたこの編成を! 皆の得手不得手をきちんと考えて、皆が活躍できるようにしてくれているのよ!?」
システィーナの必死の訴えに、クラス中がざわめく。
そう言えば……とか。確かに……とか。あちこちから、ひそひそと声が漏れる。
(ちょ……お前ら……説得されんな……頼むから……)
「先生がここまで考えてくれたのに、皆、まだ尻込みするの!? 女王陛下の前で無様な姿を見せたくないとか、そんな情けない理由で参加しないの!? それこそ無様じゃない! 陛下に顔向けできないじゃない!」
(無様でも顔向けできなくてもいいから、余計なこと言わんといて頼むから……)
「大体、成績上位者だけに競わせての勝利なんて、なんの意味があるの? 先生は全力で勝ちに行く、俺がこのクラスを優勝に導いてやるって言ってくれたわ! それは、皆でやるからこそ意味があるのよ!」
そして、システィーナはグレンに振り返って言った。
「ですよね、先生!?」
その表情は、グレンに向けるものとしては珍しく険の取れた、朗らかな笑顔だった。
「お、おう……」
としか言えなかった。ここで違うとか言ったら単なる極悪人である。
「た、確かにシスティーナの言うとおりだよな……」
「あぁ、そうだ……俺達だって……」
そして、クラス全体の雰囲気は明らかにシスティーナに追従ムードだった。
(あ、後に引けねぇ——ッ!? こらぁ、ちょっと待て、お前ら! 俺にとっては死活問題なんだぞ!? 餓死がかかってんだぞ!? わかってんのか、コンチクショウ!?)
こうなると頼みの綱はギイブルしかいない。
(頑張れ! 負けるな、ギイブル君! 白猫の言い草なんざ派手に論破したれ!)
グレンは縋るような視線でギイブルを見つめるが……
「ふん、やれやれ。君は相変わらずだね、システィーナ。……まぁ、いい。それがクラスの総意だというなら、好きにすればいいさ」
ギイブルは皮肉げに冷笑して着席してしまった。
(てめ、この、押し弱過ぎだろ、この草食系男子がぁ——ッ!?)
「ま、せいぜいお手並み拝見させていただきますよ、先生?」
(やかましいわ! 見せられるお手並みなんかねーよ!?)
挑発的なギイブルの物言いに、グレンはもう声無き叫びをあげるしかなかった。
と、そんなグレンに。
「あはは、よかったですね。先生の目論見どおりに行きそうですよ?」
システィーナがそんなことを言って、くすりと笑った。
(こ、こいつ……あざ笑いやがった!? この俺を! 思いっきり、蔑むかのように笑いやがった!? しかも痛烈な皮肉の追い打ちまで……ッ!?)
グレンにはその笑顔がもう、悪魔の微笑みにしか見えなかった。
(ま、まさか、こいつ……俺の企みを察してわざと!? だとしたら、なんて嫌な奴なんだ、白猫め……ッ!)
「ま、せっかく先生がたまにやる気出して、一生懸命考えてくれたみたいですから、私達も精一杯、頑張ってあげるわ。期待しててね、先生」
「お、おぅ……任せたぞ……」
珍しくご機嫌なシスティーナと、どこか引きつった笑みを浮かべるグレン。
「なんか……かみ合ってないような気がするなぁ……なんでだろう?」
そんな二人の様子を、ルミアは苦笑いで眺めていた。