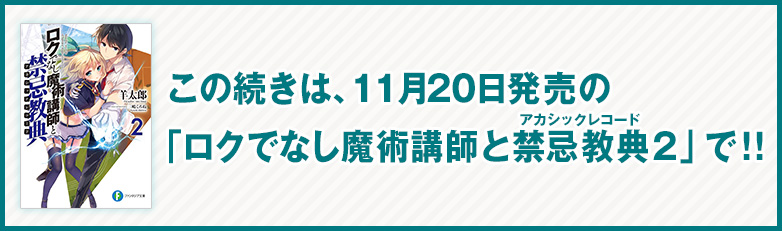呪文のダメージから回復したグレンは早速、昼食を調達しに行くことにした。
とは言ってもお金のないグレンにまともな食事は許されない。ここ数日間、グレンに許された食事は、シロッテと呼ばれる木の枝だ。
シロッテは星形の葉が特徴的な落葉広葉樹で、その若枝に限って樹液に糖分が含まれている。その枝をかじると、枝に含まれる糖分をある程度摂取することが可能だ。
一週間前、学院敷地内の北部に広がる通称『迷いの森』の入り口付近で、シロッテの木を発見したグレンは以来、昼食時になるとその場所に足繁く通い、シロッテの若枝を回収、飢えを凌いでいた。
「とは言ってもなぁ……」
シロッテの枝を取ってきたグレンは学院中庭のベンチにぐったり腰かけながら、枝を口にくわえている。
「なんかこう、人間としてどんどん落ちぶれていってる気がする……ちくしょう……もう二度とギャンブルなんかしねえぞ……ぐすん」
涙目でシロッテの枝をかじりながら、グレンはどんよりと淀んだ目で遠くを見た。
「へへっ……今日は、なんだか妙に目にゴミが入りやがる……」
目元を拭うグレンの腹の虫が盛大に鳴った、その時だった。
「あ、先生~」
遠くできょろきょろと何かを探していたらしいルミアがグレンの姿を見つけると、ぱたぱた駆け寄ってくる。その手には何かを大切そうに抱えていた。
「……ルミアか。どうした?」
「あの……先生に差し入れを届けに来ました」
「差し入れ?」
訝しむように構えるグレンに、ルミアは布包みを差し出した。
「これ、サンドイッチの包みです。先生、最近、ずっとお腹が空いているみたいだったから、もしよかったらと思―――」
「ありがとうございます天使様! 喜んで謹んで、頂戴いたしますぅ――ッ!?」
狂喜と共にグレンがルミアの手から布包みをひったくり、布をむしり取るように開く。中身は特になんの変哲もない、トマトサンドやハムサンドなど、ごくありふれた普通のサンドイッチだったが、今のグレンにはそれが最高級の宮廷料理に見えた。
「ぅおおおおお!? 生きてるって、なんて素晴らしいんだぁああああ――ッ!?」
「お、大げさだなぁ……」
グレンは夢中でサンドイッチに噛みついた。瑞々しいトマトの酸味が、ほどよい塩加減のハムの旨味が、薄くスライスされたチーズのコクが、飢えきった舌の上で極上のハーモニーとなって踊る。粗挽きされた黒胡椒の辛みと香りにとめどない感動が溢れる。
ルミアはグレンの隣に腰を落ち着けると、隣で号泣しながら中身のサンドイッチを頬張るグレンを苦笑いしながら眺めていた。
「ところで……これ、お前が作ってくれたのか?」
「はい、私が先生のために作りました……なぁんて言ってみたいんですけど、実は私じゃないんです」
と言って、ルミアがいたずらっぽく笑う。
「あはは、私、不器用だから料理とか苦手で……」
「そうなの? じゃ、これ誰が作ったんだ?」
「それは秘密です。本人たっての希望なので……うちのクラスのとある可愛い女の子が作った、とだけ言っておきますね?」
「ふーん。ま、別にこの弁当の出所なんてどうでもいいけどな」
「実はですね……その可愛い女の子は、とあるちょっと気になる男性のために、以前、お世話になったお礼にと、その弁当を早起きして一生懸命作ったらしいんですが、その女の子はどうも素直じゃなくて、つい渡しそびれちゃったらしくて……」
「誰か知らんが、そりゃご愁傷様だったな……」
グレンが同情するようにため息をついた。
「つーか、その男の方も大概だなぁ……せっかく女の子が弁当作ってきてくれたんだからそこは察してやれよ……ったく、そんな空気の読めないスケコマシ野郎なんざ、どーせロクな奴じゃあるまい。やれやれ、その女の子とやらも男の趣味が悪いぜ」
「あ、あはは……」
なぜかルミアは脂汗をかいているが、グレンは気付かない。
「ま、まぁ、それはとにかくですね、その子がせっかく作ったお弁当を捨てようとしていたので、もったいないから私が受け取って、こうして先生の所に持ってきたんです」
「ったく……俺はゴミ箱の代わりかよ。ま、別にいいけどな。助かったし」
グレンはふて腐れたように鼻を鳴らし、それでもサンドイッチをかじり続ける。
「ねぇ、先生。どうです? そのサンドイッチ、美味しいですか?」
問われて、グレンは改めて口の中に広がる味に思いを馳せる。
「美味い」
率直に思ったことをグレンは素直に言った。
「工夫はないが丁寧に作られてる。オーソドックスだけど、スゲー美味い」
「ふふっ、そうですか。きっと、それを作った子も喜ぶと思いますよ?」
そう聞いて、ルミアはにっこりと笑った。
まるで自分が作った料理を褒められたかのようだった。
しばらくすると、結構多めに作ってあったサンドイッチは全て空になった。
「ふー、食った、食った……ごちそうさん」
「ふふ、お粗末様です……って、私が言うべき言葉じゃないですけど」
「これで寿命が三日ほど延びたかな……よし、ぎりぎり行けるぞ……」
「……?」
グレンの意味不明な呟きにルミアが小首をかしげる。
「さて、人心地もついたし、そろそろ競技場に戻るか」
「はい」
グレンとルミアがベンチから立ち上がった。
その時。
「そこの貴方はグレン、ですよね? あの……少し、よろしいですか?」
立ち去ろうとする二人の背後から、不意に女性の声がかかる。
呼び止められたグレンは、いかにも面倒臭そうに振り返った。
「はいはい、全然よろしくありませーん、俺達、今、すっごく忙し――って、ぇえええええええええええええええええええええ――ッ!?」
グレンは背後から声をかけて来た人物の正体を知ると、素っ頓狂な叫びを上げた。
「じょ、じょ、じょ、女王陛下――ッ!?」
そこにいたのは他でもない、アルザーノ帝国女王アリシア七世その人だった……。
「さて、アリスのやつ、うまく接触できたかな?」
バルコニー型の貴賓席で、セリカは紅茶を傾け、優雅な一時を過ごしていた。
「それにしても傑作だったなぁ。アリスが居なくなったことに気付いたときの、王室親衛隊連中の顔!」
笑いを堪えきれず、セリカは肩を震わせている。
「相変わらず神をも恐れぬ女じゃのう、セリカ君は……」
こんなセリカの態度には、リック学院長も呆れ顔だ。
「ははは、何を言うか学院長。私に言わせれば、ぶっちゃけ神より人間の方が怖いぞ? 神はただ人間には及びもつかない強大で絶対的な力を持ってて、やたらめったら強いだけだけど、一方、人間ときたら――」
そんな、ご機嫌なセリカの下に。
「セリカ様……」
何やら深刻な表情で、エレノアがやってくる。
「ん? どうした?」
「大変なことが起きてしまいました……どうしてもお耳に入れて欲しいことが」
「……何事だ?」
エレノアのそのただならぬ様子に、セリカが表情を引き締める。
そして。
「実は…………………」
エレノアがそっと耳打ちしてきたその話の内容に。
「な――なんだと!? そんな、馬鹿な――」
セリカは顔色を蒼白にして目を剥き、エレノアを凝視していた。
「ど、ど、どうしてアナタのような高貴なお方が、下々の者のたむろするこのような場所に、護衛もなしで――ッ!?」
突然、現れた女王の前に、グレンはひたすら恐縮しまくっていた。
「あ、いえ、その、さっきは無礼なことを言って申し訳ございませんでした――ッ!」
いつもの横柄で傍若無人な態度はどこへやら。
グレンは畏まって片膝をつき、その場に恭しく平服する。
「そんな、お顔を上げてくださいな、グレン。今日の私は帝国女王アリシア七世ではありません。帝国の一市民、アリシアなんですから。さぁ、ほら、立って」
「いや、そうは言ってもその……し、失礼します……」
グレンはおそるおそる立ち上がって、恐縮する。
「ふふっ。一年ぶりですね、グレン。お元気でしたか?」
「あ、はい、そりゃもう。へ、陛下はお変わりないようで……」
「……貴方にはずっと謝りたいと思っていました」
ふと、アリシアは目を伏せた。
「あ、謝る……って、そんな……」
「貴方は私のために、そして、この国のために必死に尽くしてくださったのに……あのような不名誉な形で宮廷魔導士団を除隊させることになってしまって……本当に我が身の不甲斐なさと申し訳なさには言葉もありません……」
「いえいえ、全然、気にしてませんって! いや、ホントです! ていうか、俺ってぶっちゃけ仕事が嫌になったから辞めただけの単なるヘタレですから! マジで!」
ぶんぶんと頭を掌を左右に振りながら、グレンはアリシアの謝罪を固辞する。
「そうですね……私は貴方に頼るばかりで、貴方の辛さや苦しさをわかってあげられなかった……女王失格ですね。思えば三年前のあの時も……」
「いやいやいやいや!? 俺みたいな社会不適格者に女王たるあなたが頭下げちゃダメですって!? 誰かに見られたらどうするんですか!?」
グレンが戦々恐々と周囲を見渡す。都合の良いことに――いささか都合が良過ぎる気もするが――周囲には誰もいなかったが、グレンは気が気ではなかった。
「で、陛下……その、今日はどういった御用向きで……?」
「ふふ、そうですね。今日は……」
アリシアは視線を横にずらす。
その視線が捕らえた先に、呆然と立ち尽くしているルミアがいた。
「……お久しぶりですね、エルミアナ」
そんなルミアに、アリシアは優しく語りかけた。
「………………」
ルミアは無言でアリシアの首元に視線をさまよわせる。そこに翠緑の宝石が納まった金細工のネックレスがかけられているのを確認すると、なぜかルミアは目を伏せた。
「元気でしたか? あらあら、久方見ないうちに、ずいぶんと背が伸びましたね。ふふ、それに凄く綺麗になったわ。まるで若い頃の私みたい、なぁんて♪」
「…………ぁ……ぅ……」
「フィーベル家の皆様との生活はどうですか? 何か不自由はありませんか? 食事はちゃんと食べていますか? 育ち盛りなんだから無理な減量とかしちゃだめですよ? それと、いくら忙しくても、お風呂にはちゃんと毎日入らないとだめよ? 貴女は嫁入り前の娘なのですから、きちんとしておかないと……」
「…………ぁ……そ、その……」
硬直するルミアをよそに、アリシアは本当に嬉しそうに言葉を連ねていく。
「あぁ、夢みたい。またこうして貴女と言葉を交わすことができるなんて……」
そして、感極まったアリシアは、ルミアに触れようと手を伸ばす。
「エルミアナ……」
だが――
「……お言葉ですが、陛下」
ルミアはアリシアの手から逃げるように、片膝をついて平伏した。
「!」
「陛下は……その、失礼ですが人違いをされておられます」
ルミアがぼそりと呟いた言葉に、今まで嬉しそうだったアリシアが凍りついた。
「私はルミア。ルミア=ティンジェルと申します。恐れ多くも陛下は私を、三年前に御崩御なされたエルミアナ=イェル=ケル=アルザーノ王女殿下と混同されておられます。日頃の政務でお疲れかと存じ上げます。どうかご自愛なされますよう……」
「…………」
慇懃に紡がれるルミアの言葉に、アリシアもグレンも気まずそうに押し黙った。
「……そう、ですね」
そして、アリシアは寂しそうに薄く微笑み、目を伏せた。
「あの子は……エルミアナは三年前、流行病にかかって亡くなったのでしたね……あらあら、私ったらどうしてこんな勘違いをしてしまったのでしょう? ふふ、歳は取りたくないものですね……」
そんなアリシアの哀愁漂う言葉に、グレンは複雑な表情で頭を掻く。
ルミアは淡々と言葉を続ける。
「勘違いとは言え、このような卑賤な赤い血の民草に過ぎぬ我が身に、ご気さくにお声をかけていただき、陛下の広く慈愛あふれる御心には感謝の言葉もありません……」
「いえいえ、こちらこそ。不愉快な思いをさせてしまって申し訳ありません」
しばらくの間、重たい沈黙が周囲を支配する。
ルミアは何も言わない。アリシアは何かを言おうとして口を開きかけ……そして、諦めたかのように口を閉ざす。その繰り返しだった。
そして――
「……そろそろ、時間ですね」
未練を振り切るように、アリシアはグレンを振り返った。
「グレン。エル――……ルミアを、よろしくお願いしますね?」
「……わかりました、陛下」
グレンが何か物言いたげな表情で見送る中、アリシアは静かに去って行った。
やがてアリシアの姿が、中庭から見えなくなる。
「…………」
その場に恭しく平服したままのルミアはついぞ一度も、去り行くその背中に目を向けることはなかった……。
「やっぱり、私を母親とは認めてはくれませんか……そうですよね……」
競技場の貴賓席へ、アリシアは肩を落としながらとぼとぼと向かっていた。
アリシアは往来を堂々と歩いているというのに、すれ違う誰もがアリシアの存在を気にとめることはない。セリカの高度な人避けの魔術が効いているのだ。
「エルミアナ……」
触れようとした瞬間、まるで他人のように振る舞った我が子を思い出す。
どのような理由があれ、確かに自分は娘を裏切り、捨ててしまったのだ。エルミアナという少女を亡き者とし、エルミアナとして生きてきた半生を全否定したのだ。
エルミアナは聡明な娘だ。母親であると同時に女王である自分がそうせざるを得なかったことは理解しているのだろう。だが、頭で理解はしていても、心で納得できるものではない。おまけに追放当時のエルミアナはまだ幼かった。報告によれば、王宮から放逐された直後のエルミアナは、しばらくの間、相当に荒れていたらしい。母親が恋しい多感な年頃に、一方的に放り出されれば、誰だってそうなるだろう。
それでも、彼女は誰からも好かれるような優しい子に育った。それは母親から捨てられたエルミアナとして生きたからではない、フィーベル家の一員として新たな人生を歩むことを選んだルミアとして生きたからなのだろう。
なるほどそう考えれば、さっきアリシアの前に立っていた少女は、確かにエルミアナではなく……ルミアだったのだ。
「……残念、です。本当に……」
こんなに惨めで辛い思いをするくらいなら、セリカやエレノアの提案に安易に乗らず、遠くから見るだけにしておけば良かったか。そんな考えが思い浮かぶ。
だが、彼女達のせいにはできない。結局、娘に会うことを望んだのは自分自身。セリカとエレノアは、そんなアリシアの心に燻る思いに気を利かせただけに過ぎないのだから。
暗鬱な気分でアリシアが魔術競技場へと歩を進めていた、その時だった。
「……陛下」
自分を呼ぶ声にふと、アリシアが顔を上げる。
周囲を見渡せば、並木道に並び立つ木陰に見知った姿があった。
王室親衛隊、総隊長ゼーロスだ。
なにやら切羽詰まった鬼気迫る表情でこちらの様子を伺っていた。
(おや、変ですね。どうして私のことを認識できたのでしょう? まだセリカの魔術が効いているはずなのですが……)
不思議に思いながらも、アリシアはこの忠義あふれる衛士に声をかける。
「あらあら、見つかってしまいましたね。勝手に外を出歩いてしまって、すみません、ゼーロス。ところで……どうかしましたか?」
「少し、お話があります、陛下」
ゼーロスは音もなく木陰から出ると、アリシアの前に立ち、手を振り上げた。
それが合図だったのか。
「――ッ!?」
どこからともなく現れた数名の衛士が、あっという間にアリシアを取り囲んでいた。
「……どういうことでしょうか?」
そのただ事ではない雰囲気にも動じず、アリシアが静かに問う。
「ご無礼をお許し下さい、陛下。しばらくの間、我ら一同、力尽くでも御身を拘束させていただきます。けれど、この狼藉は決して御身に、そして帝国に対する敵対行為に非ず。一重に御身と祖国に対する忠義ゆえとご理解願いたい。ゆえに今しばらくご辛抱を」
「ゼーロス……」
アリシアとて素人ではない。セリカには到底およばないが、それなりの位階の魔術師である。有象無象の賊共から、自分の身を守ることくらいは充分にできる。
だが、対魔術装備に身を包み、近接戦闘に優れた凄腕の衛士数人に、この至近距離で取り囲まれてしまったら、もうどうしようもない。
「……わかりました。まずはお話を聞きましょう」
観念して、アリシアはゼーロスに従うことにするのだった。
「……信じられんな」
言葉とは裏腹に、アルベルトは冷静沈着そのものの声色で、淡々と告げた。
「どうしたの? 遠見の魔術で何を見たの?」
「王室親衛隊が――動いた」
「……? それは動くでしょう? 彼らも生きた人間なのだから」
「……………………」
アルベルトが険しい表情を微塵も揺らさず押し黙る。二人の間に沈黙が流れる。
「……王室親衛隊は、武力をもって女王陛下を本格的に自分らの監視下に置いた。これは事実上の軟禁状態と考えていい。しかし、総隊長ゼーロス……短慮を起こすような人物ではなかったと記憶していたが、認識を改める必要があるようだ」
「そう」
それを聞いたリィエルが早速、迷わず歩き始める。
「何処へ行く気だ?」
そんなリィエルの後ろ髪を、アルベルトは手を伸ばして掴んだ。
「決まってる。敵は、わたしが全部斬る」
「待て。相手が多過ぎる。幾らお前でも無理だ」
「敵の戦力の方が上だというなら、こちらがそれを上回ればいいだけ」
「援軍を呼ぶ気か?」
「ううん、気合い」
「……………………」
アルベルトが険しい表情を微塵も揺らさず押し黙る。また二人の間に沈黙が流れる。
「……帝国王室親衛隊は直系右派の筆頭、女王陛下に最も忠義厚き者達だ。陛下に直接的な危害を加えるとは考えられん。この行動には必ず何らかの思惑があるはず。俺達は連中のこの無謀な行動の裏に隠された意図を探り、事態を収拾すべく行動すべきだ」
「そう。わたしにはよくわからないけど」
「だろうな」
沈黙。少女の後ろ髪を掴む男、という奇妙な構図で二人が静止している。
そして、先に口火を切ったのはリィエルだった。
「作戦を考えた。わたしが正面から敵に突っ込む。アルベルトはわたしの後に正面から突っ込んで」
「……………………」
アルベルトが険しい表情を微塵も揺らさず押し黙る。
いつものように、二人の間に沈黙が流れた。
魔術競技祭、午後の部が始まった。
午後の部最初の競技は、念動系の物体操作術による『遠隔重量上げ』だった。白魔【サイ・テレキネシス】の呪文で、鉛の詰まった袋を触れずに空中へ持ち上げる競技である。より重い袋を浮かせることができた選手に多くの得点が入るルールだ。
アリシアとの密会の後、消沈するルミアをつれて競技場に戻ってきたグレンは、午前同様に盛り上がるクラスの生徒達とは裏腹に、上の空で重量上げの競技を眺めていた。
ぼんやりと考えていることは、当然、ルミアとアリシアのことだ。
グレンとて、ルミアの正体とその身の上の複雑な事情を、一ヶ月前の事件の後、政府上層部から極秘に聞かされた者の一人だ。
帝国女王としての立場がありながら、ルミアとの関係を勘ぐられる危険性を犯してでもルミアに会いたかったアリシアの気持ちも理解できるし、そんなアリシアを拒絶したルミアの気持ちもなんとなくわかる。
わかるのだが――
(……かと言って、俺にどうしろってんだ?)
結局のところ、あの二人の間の問題は、あの二人にしか解決できないのだ。部外者が何を口出ししても、それは嘘になる。問題の根底にある物が理屈ではなく感情である以上、どんな正論も教唆も慰めも、まったく役に立たない。
「……ったく、やれやれだ」
グレンは深くため息をつく。問題は次から次へと発生し、まるで息つく暇もない。周囲のやたらハイテンションなクラスの生徒達がまるで異世界の住人のようだった。
そんな風に、グレンがぼんやりと考え事に浸っていた、その時だった。
「……先生」
むぅ~っ、と不機嫌そうにむくれたシスティーナが、突然グレンに声をかけてきた。
「うお!? な、なんだよ、白猫!? やんのかコラ!?」
昼休み中のやりとりを思い出し、グレンは思わず拳闘の構えで身構える。
「……ルミアがいなくなったんだけど」
「は、はぁ!?」
「考えてみれば、あの子……先生に会いに行って、帰って来てから、ずっと様子がおかしかった」
「あれ? なんでお前、俺がルミアと会っていたことを知ってるんだよ?」
「うるさい!」
「ひゃい! ごめんなさい!?」
ぴしゃりと切り返され、グレンは情けなく縮こまる。
「午後の部には、もうあの子の出番はないけど、だからと言ってサボるような子じゃないわ。だから、何も言わずに姿を消したのはおかしいなって、思って」
「……まぁ、そうだな」
システィーナはグレン同様、ルミアの身の上の事情を知る数少ない人間の一人だ。
だが、つい先刻ルミアが実の母親――女王陛下と密かに面会していたことは知らない。ならば、そういう雑感だろう。
システィーナも関係者だ。何が起きたか知っておいた方がいい、とグレンは判断した。
「おい、白猫。ちょっとこっち寄れ。耳を貸せ」
「……?」
そして、グレンは訝しむような表情のシスティーナに、先ほどのアリシアとルミアの顛末を声を潜めて話した。
「そんなことが……」
全てを知ったシスティーナは、なんとも複雑そうな表情だった。
「じゃあ、あの子がいなくなったのって……」
「十中八、九、お前の想像通りだろうな。そんな状況、俺だって一人になりたいわ」
やれやれ、とグレンはため息をついた。
「だが、一人になりたい気分はわかるが、一人になり過ぎるのもよくないな。なんの解決にもならんが、仲間達と一緒に騒いでいた方が気も幾ばくか紛れるだろ。どーせ、一人で塞ぎ込んで解決する話でもねーし。探して、連れ戻して来てやるよ」
頭を掻きながら面倒臭そうに物言うと、グレンは席を立ち上がった。
「白猫。お前も来るか?」
「そうね、私も――」
と、システィーナが反射的に首肯しかけて……
「――ううん、私はここで待ってる。先生が、あの子を迎えに行ってあげて。先生が戻ってくるまで、私がクラスをまとめておくから」
なぜか、そんなことを言った。
「おいおい、薄情だな。お前達、親友同士じゃなかったか?」
「親友同士だからこそ、よ」
ぷい、と。システィーナがそっぽを向いた。
「こんな時……あの子が誰に一番そばにいて欲しいかくらい……不本意だけど……」
何事かをぼそぼそ呟くその横顔は、怒ったような、諦めたような、むくれたような、拗ねたような、嫉妬しているような、なんとも複雑な表情だ。
「なんだかよくわからんが、俺に任せる、それでいいんだな?」
と、グレンがルミアを探すために歩み去ろうとした、その背中に。
「……ちょっと、待ちなさいよ」
システィーナが不意に言葉を投げつける。
「なんだよ?」
首だけ軽く回して、振り返る。システィーナは相変わらず不機嫌そうだ。
「一つだけ聞きたいことがあるの。先生……ルミアから何かもらわなかった?」
「あー? サンドイッチくれたぞ? どっかの誰かが作った廃棄寸前の物を回収したらしいな。それが何か?」
「その……どうだったのよ、それ」
「はぁ?」
「どうせ不味かったんじゃない? ふん……哀れな残飯処理、ご苦労様なことね」
「……いや、別に? すっげぇ美味かったが?」
途端に、なぜかシスティーナはグレンに、くるりと背を向けた。
そんなシスティーナに、グレンは眉をひそめ、頬を掻きながら忠言する。
「……なぁ、どーでもいいが、そんな作り手に失礼なこと言うもんじゃねーぞ? お前らしくもない。お前は俺以外の人間には優しいやつだったはずだ」
「わ、わかってるわよ! 早く行きなさいよ、もう!」
ぴしゃりと返ってきた言葉は、こちらを見もしないで放たれている。今の言葉の何が癪に障ったのか不明だが、耳まで真っ赤にして怒っているようだ。
「ったく……やれやれ」
このシスティーナという少女だけはどうも扱いに困る。なにしろ何を考えているのかさっぱりわからないし、おまけにすぐ怒るときたものだ。ルミアの百分の一くらいでも、わかりやすい可愛さがあればありがたいのだが。
そんな無い物ねだりなことを考えながら、グレンは競技場の外へ向かって歩き始めた。
先ほどの中庭にルミアの姿は無かった。
仕方ないので、グレンは学院内を直感に任せて歩き回る。
「まずいな……マジでどこ行ったんだ……?」
まずは学院校舎本館、西館、東館の周囲を一回りし、学院付属図書館と図書館前広場を足早に通り過ぎ、迷いの森入り口周辺、薬草菜園、魔術実験塔周辺に足を運んでみた。
だが、ルミアの姿は見当たらない。めげずに、競技場に人が集まることで閑散としてしまった学院内を延々と宛てもなく回り続ける。延々と探し続ける。
流石にグレンが焦りを覚え始めた頃、学院敷地の南西端、学院を取り囲む鉄柵のかたわら、等間隔に植えられた木々の木陰にちらりと、見覚えある金髪が見えた。
「……見つけた」
グレンがその木陰に歩み寄る。
そこには木に背を預け、神妙な面持ちで手元を見つめているルミアがいた。
「……ルミア? 何、見てんだ? ……ロケットか?」
特に覗くつもりはなかったのだが、ルミアに歩み寄る角度と身長差の関係から、偶然、ルミアの手元が見えてしまったのだ。
ルミアの小さな手の中には簡素な作りのロケット・ペンダントがあった。ルミアはその蓋を開いて、その中をじっと見つめているようだった。
「このロケットにはですね、何も入っていないんです……」
グレンの接近を察したルミアは、ぱちんとロケットの蓋を閉じ、それを握りしめた。
「昔は、誰か大切な人達の肖像が入っていたような気がするんですが……いつの間にかなくなっちゃいました」
「…………」
沈黙するグレンの前で、ルミアは寂しげに笑い、ロケットの鎖を首の後ろで繋ぎ、ロケット本体を胸元から衣服の中に落とし込んだ。
「これ自体、特に価値があるものでもないのに……変ですよね。こんなものを今でも大事に肌身離さず持ち歩いているなんて」
「……別に変じゃねーよ」
グレンはそっぽを向いて頭を掻きながら、ぶっきら棒に応じた。
「その中身を紛失した経緯ってのはわかんねーけどな。でも、今でも何か大事なもんが詰まってんじゃないのか? それ」
「…………先生は」
意を決したかのように、言葉を切って、ルミアが問いかける。
「知っているんですよね? ……私と、女王陛下の関係を」
「あぁ。こないだの事件の後、政府のお偉いさんから聞かされたよ」
そして、グレンはくるりと踵を返し、ルミアに背を向ける。
「だーが、どうでもいい。おい、行くぞ、ルミア。皆がお前のことを待っている。楽しい楽しい魔術競技祭、後半戦開始だぜ?」
そのまま歩き去ろうとして……
「ふふっ、先生はいつだって先生ですね」
くすり、と。ルミアはほんの少しだけ微笑んだ。
「ここは落ち込んだ女の子に、何か優しい言葉をかけてあげる場面ですよ?」
「ぶっちゃけ、何を言ってやればいいのかさっぱりわからん」
堂々と甲斐性なしなことを言ってのけるグレン。
そんなグレンを見て、ルミアはくすくすと含むように笑う。
「あの……じゃあ、もう少しだけ私のお話に付き合ってくださいませんか?」
「……ああ」
そしてルミアは再び木に背を預け、グレンはルミアに背を向けたまま空を見上げた。
とつとつとルミアが語り始める。
ルミアが話すことは実に取り留めのないことだ。
まだ、自分が王女だった頃の話。日々の政務で忙しい中、それでも時間を作って遊んでくれた優しい母親。いつも自分の面倒を見てくれた優しい姉。王室直系の娘として何一つ不自由なく、王室直系の娘としてやはりどこか不自由だった日々。それでも、確かに幸せと呼べた在りし日の記憶――
それは恐らく、王女としての地位を剥奪され、王宮を放逐されたルミアがフィーベル家の一員になろうとして、全て忘れ去ろうとして――結局、忘れきれずにまだ心の奥底に燻っている思い出達なのだろう。
「……私、どうすればよかったんでしょうか?」
一通りの思い出語りが終わると、ルミアはグレンに静かに問う。
「陛下が私を捨てた理由……わかるんです。王室のために、国の未来のためにどうしてもやらなければならない必要なことだったって。それでも……私は心のどこかで陛下を許せなかった……怒っているんだと、思います……」
「ま、理屈じゃねーからな、そういうの」
「だけど、あの人を再び母と呼びたい、抱きしめてもらいたい……そんな思いも、どこかにあるんです……ずるいですよね……私……」
「ま、理屈じゃねーしな、そういうの」
「でも、あの人を母って呼んだら、私を引き取って、本当の両親のように私を愛してくれたシスティのお母様やお父様を裏切ってしまうようで……それが申し訳なくて……」
「ああ、理屈じゃねえんだよな、そういうの」
「だから、私、わからないんです。どうしたらよいのか、どうすればよかったのか……」
目を伏せるルミア。
グレンは面倒臭そうに、ため息を一つ吐いて、言った。
「持論だがな。人は、どうも人生においてあらゆる選択と決断をする際に、後悔し、傷つかずにはいられない生き物らしい。一般的には後で悔いが残らないような選択をしろってよく言われているだろ? 断言してやる。ありゃ嘘だ……ていうか、無理だ」
「そう、なんですか……?」
グレンは頷いて続ける。
「神様ってホント意地悪な奴だと思わないか? 目の前に道が二つあれば、どんなに悩んで考えて一方の道を進んでも、もう片方の道にしておけばよかった……って、後で何かしら後悔するように人間をお作りになったんだからな。ご丁寧にまぁ、道の選択そのものから逃げたとしても、選ばなかったこと自体を後で悩み苦しむ、クソ仕様だ」
グレンはふと、自分を振り返る。
かつて、グレンは絵本に出てくるような正義の魔法使いに憧れ、魔術師を志した。今では安易にそんな道を選んだことを激しく後悔している。自分が選んだこの道は間違いだった。別の道にしておけばよかった。何度そう思ったかわからない。
だが――夢を捨て、別の道を歩めば、あんなに悩むことも苦しむこともなかったのだろうか? 否、やっぱり夢を諦めずに頑張ればよかった……その道を選ばなかったことを、後になってから延々と悩み苦しむのだろう。
「だからこそ、本音が重要だと思ってる」
「……本音、ですか?」
「ああ、その道を本音で選んだなら、どっちにしろ後悔することになるなら、ちったぁマシだと、そう思わないか? 散々、後悔した後で前に進める気がしないか?」
「で、でも……私……自分の心がわからなくて……」
すると、グレンは頭を掻きながら言った。
「俺は昔、帝国軍に所属する魔導士だった。……意外に思うだろうが」
意図の読めないグレンの台詞と告白に、ルミアは戸惑った。
「で、仕事柄、宮廷に赴く機会も結構あってな、さっきお前が大切そうに見つめていた物とまったく同じ物を、宮廷内でとある偉い人が身に着けていたのを見たことがある。……意味、わかるな?」
「……っ!」
ルミアがはっとして、思わず胸を押さえた。
「今の今まで後生大事に肌身離さず持っていた、お揃いのそれ。捨てるタイミングなんていくらでもあったハズだ。……もう、答えはとっくに出ているんじゃないのか?」
「答え……」
「恨み辛みでも文句でも、なんでもいい。まずは言葉をぶつけることから始めてみたらどうだ? さっきのお前みたいに向き合うことから逃げるだけじゃ、なんにもならんだろ。まぁ、散々向き合うことから逃げ続けてきた俺が言うのも……なんだがな」
ルミアはしばらくの間、無言でうつむいていた。
グレンはそんなルミアに相変わらず背を向けながら、返答を静かに待つ。
そして。
「私……怖いんです」
ぽつりと、ルミアは消え入りそうな声で、そんなことを呟いた。
「私を追放した前日まで、あの人はとても優しかったんです。でも、私が追放されたあの日、あの人に呼び出されたら、国の偉い人達が険しい顔で沢山集まっていて……あの人は凄く冷たい目で私を見つめていて……まるで別人のように豹変していて……」
「…………」
「さっきのあの人はとても優しかったけど……また、いつ私に対して、突然、あの冷たい目を向けてくるかと思うと……怖くて……だから……その……」
意を決したように、ルミアは真っ直ぐとグレンの背中を見つめた。
「先生、一緒についてきてくれませんか?」
「……やれやれ、なんつーか、お前にもそういうガキっぽいトコあったんだな」
グレンは肩をすくめて苦笑いしながら、ルミアに振り返った。
「いいぜ? 付き合ってやるさ」
「本当ですか?」
「……ここで嘘だって言ったら、単なる極悪人だろ」
「もう、先生ったら」
面倒臭そうに息をつくグレン、おかしそうに笑うルミア。
グレンはルミアを伴って歩き始める。
二人の間に流れる、穏やかで気安い空気。
さて、とは言ったものの、どうセッティングすればいいのやら。いつの間にか、また厄介事が一つ増えてしまっていることに気付き、グレンは再び頭を悩ませていた。
――だが。
「……ん?」
ふと、グレンは奇妙な集団が、自分達の行く手に現れていたことに気付いた。
その集団は全員が全員、体の要所を守る軽甲冑に身を包み、緋色に染め上げられた陣羽織を羽織り、腰には細剣(レイピア)を佩剣している。
その数、総勢五騎。
弧を描くような陣形を組み、通りの向こうから、足早にこちらへ向かってやって来る。
「あの陣羽織は……王室親衛隊か?」
帝国軍の精鋭中の精鋭。もっとも女王陛下に忠義厚い者達で構成された、王室一族を何よりも優先して護衛する、王室の守護神――それが王室親衛隊だ。
ゆえに王室親衛隊は今回の女王陛下の学院訪問の際、当然のように女王の近辺警邏と護衛を務めているはずなのだが――
「なんで連中が女王陛下の護衛サボって、こんな所をほっつき歩いてるんだ?」
疑問に首をかしげていると、王室親衛隊の面々はグレン達の前で足を止め、グレンとルミアの二人を囲むように、音もない足捌きで素早く散開した。
「ルミア=ティンジェル……だな?」
二人の正面に立った、その一隊の隊長格らしい衛士が低い声で問いかけてくる。
グレンとルミアは顔を見合わせた。
「……ルミア=ティンジェルに間違いないな?」
「え? は、はい……そ、そうですけど……」
念を押すように再び重ねられた問いかけに、ルミアは戸惑いながらも答える。
ルミアが返答した次の瞬間。
衛士達は弾けたバネのように一斉に抜剣し、ルミアにその剣先を突きつけていた。
「――ッ!?」
自分に向けられた鋭い切っ先に、思わず硬直してしまうルミア。
「……どういうつもりだ、お前ら」
同時に。
ルミアを自分の背後に庇っていたグレンが、恫喝的な声で衛士達を威嚇する。
「傾聴せよ。我らは女王の意思の代行者である」
一隊の隊長格らしい衛士は、そんなグレンを忌々しそうに一瞥し、朗々と宣言した。
「ルミア=ティンジェル。恐れ多くもアリシア七世女王陛下を密かに亡き者にせんと画策し、国家転覆を企てたその罪、もはや弁明の余地なし! よって貴殿を不敬罪および国家反逆罪によって発見次第、その場で即、手討ちとせよ。これは女王陛下の勅命である!」
あまりにも現実離れした、その現実に。
グレンとルミアは凍りつくしかなかった。