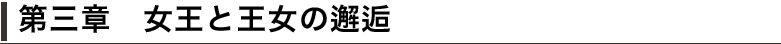一方、競技フィールド上では、この予想外の展開に男爵も困惑気味だった。
「むぅ、なんと……ジャイル君はともかく、まさかルミア君がここまで粘るとは正直予想外だったよ……ちっ」
『……ちょっと、男爵。なんで微妙に悔しそうなんですかね?』
「さて、そろそろ白魔【マインド・ブレイク】の呪文に行ってみようか」
実況の突っ込みを華麗に無視して、ツェスト男爵は次の呪文を宣言する。
『とうとう来ました! 第二十七ラウンドからは【マインド・ブレイク】だ――ッ!? この呪文はあらゆる思考力を一時的に破壊する、精神操作系の白魔術の中では最も高度で危険な呪文の一つ! 下手をすると相手を一瞬で廃人に追いやってしまうこともある恐怖の呪文だぁあああああ――ッ!?』
「いくらなんでもそこまで強くは唱えぬよ。せいぜい三日くらい放心状態で寝込む程度に抑える! 倒れた場合、ルミア君の治療と看病は私が責任持ってせんじよう!」
『……ジャイル君の看病は?』
「――いざ行くぞッ!」
そして、ツェスト男爵が粛々と【マインド・ブレイク】を唱えた。
応じて、ルミアとジャイルも【マインド・アップ】を唱える。
男爵の呪文が起動し、キーンとかん高い金属音が辺りに響き渡って……
「ふむ、大丈夫かね? 二人とも。大丈夫ならば返事を――」
「……ちっ。この程度がなんだっつうんだよ」
「――はい、私も平気です」
一瞬、返答に間があったが、しっかりとした目で二人が応じた。
『なんと【マインド・ブレイク】すら耐えたぁあああ――ッ!? 凄い! この二人は本当に凄いぞぉおおお――ッ!?』
この熱い展開に、どっと沸き立つ観客席。
洪水のような歓声と嵐のような拍手の中、ジャイルがルミアに声をかける。
「ふん。お前……女のくせにやるじゃねえか。ここまで気合い入ってるやつは野郎でも、めったにいやしねえ」
「そ、そうかな?」
「へっ。だが、そろそろきついんじゃねえか? 脂汗浮いてるぜ?」
「あ、あはは……わかる? うん、実は結構、きついかも……今も一瞬、くらっとしちゃったし……」
「棄権したらどうだ? 三日昏睡は嫌だろ?」
「心配してくれてありがとう、ジャイル君。でも……だめ。私だって負けるわけにはいかないんだ」
気丈に笑うルミア。誰がどう見ても、やせ我慢感がありありと見て取れた。
ジャイルがやれやれと肩をすくめる。
「はっ……わからねえな。どいつもこいつもが自己顕示欲と名誉欲にまみれたこのクソくだらねえ競技祭ごときに……一体、何がお前にそこまでさせている?」
「先生が言ってたの。俺達は全員で勝つって。皆は一人のため、一人は皆のためにって」
「先生? あぁ、お前んトコのあの噂のアホ講師か。ふん、余計わからんな。そんな馬鹿馬鹿しい義務感のどこに……」
「楽しいの」
ルミアの端的な言葉に、ジャイルが押し黙る。
「皆と一緒にね、何か一つのことを目指すって凄く楽しいよ? ジャイル君。先生のおかげで私も初めて知ったんだ。だから、私も頑張らなきゃ」
「…………ふん、そうかい」
それ以降、ジャイルはルミアに対して何一つ言わなくなった。堅い信念を持って立ち塞がる好敵手に語る言葉などない、ということなのだろう。
『では、次! 第二十八ラウンド――ッ!』
いよいよ、勝負も佳境。観客席は盛り上がりに盛り上がっていた。
その過熱ぶりは、まるで止まるところを知らないようだ。
「では……さっきよりもう少しだけ【マインド・ブレイク】の威力を上げよう。いくぞ、心の準備はいいかな、お二方!」
ツェスト男爵が慎重に呪文の威力を調整しながら呪文を唱えていく。
二度、三度と重ねられる呪文に、ルミアもジャイルも【マインド・アップ】を次々に唱え、【マインド・ブレイク】に耐えていく。
続く、第二十九ラウンド。
さらに、第三十ラウンド。
じりじりとラウンド数が上がっていって――
そして――第三十一ラウンド。膠着状態だった戦況に変化が訪れた。
『ああ――ッとぉおおお!? ここでルミアちゃんがよろめいたぁあああ――ッ!?』
初期と比べてかなり威力が上がった【マインド・ブラスト】の呪文によって、喪神を引き起こす金属音が辺りに一際強く、鳴り響いた瞬間。
とうとう、【マインド・アップ】の守りを貫通したのだろうか。
ぐらり、とルミアの体が傾いでいた。
「……ッ!」
バランスを崩したルミアは、がくりと片膝を折って無言でうつむいている。
『一方、ジャイル君はまったく動じず仁王立ちしたまま! こ、これは流石に決まったかぁあああ――ッ!?』
「大丈夫かね、君……ギブアップかね?」
「………………いえ」
少し意識が朦朧としていたらしい。
返答にラグが数秒あったが、ルミアは頭を振って気丈に顔を上げ、立ち上がった。
「……大丈夫です。まだ、行けます!」
力強く言い放つその言葉と目にはまだまだ力が灯っている。
『な、なんとぉおおお――ッ!? 続行です、続行――ッ!? まだまだ勝負の行方はわからない――ッ!?』
実況のアナウンスに観客達が総出で大歓声を上げた。紅一点だった少女の最後の奮闘に会場のテンションは最高潮だった。ここまで来ると、誰もが見てみたいのだろう――可憐な少女が屈強な男に勝つその光景を。
会場の期待が渦巻き、それに応じるように実況が声を張り上げ――
『では! 張り切って行きましょう! 次は第三十二――』
「棄権だ!」
突然、上がったその叫びに、会場が水を打ったように、しん、と静まり返った。
「……え? 先生?」
その声に、ルミアが振り返る。
そこには、いつの間にかやって来たグレンが立っていた。
『え、えーと? 今、なんておっしゃいましたか? 二組の担当講師グレン先生……』
「棄権だ、棄権。二組は第三十一ラウンドクリア時点で棄権だ。何度も言わせんな」
微妙な沈黙が競技場全体に流れていく。
『な、なんと……二組ルミアちゃん、棄権……これはまた、あっけない幕切れ……』
実況が残念そうに呟いた、次の瞬間。
ふざけんな、最後まで勝負させてあげろ、ひっこめ馬鹿講師!
嵐のような大ブーイングが観客席から巻き起こった。
だが、そんな大ひんしゅくの空気をまったく意に介さず、グレンは突然終わった勝負に放心するルミアの頭に手を乗せ、ねぎらいの言葉をかけた。
「よくここまで頑張ったな、ルミア」
はっと我に返り、ルミアがグレンに抗議する。
「そ、そんな、先生! 私はまだ……」
「いーや、もういい。本当はお前、わかってんだろ? 今が限界だって。次はないって」
「……そ、それは……その……」
見事に図星らしい。しゅん、とルミアはうつむいた。
「でも、優勝が……ここで私が勝たないと……」
「そりゃ確かに惜しいがな。かと言って、流石にお前に三日間も昏睡させるような真似はさせられん。いや、本当によくやったよ。……だが、相手が悪かった」
すまなそうに、グレンは目を伏せた。
そして、ちらりと隣で仁王立ちしているジャイルに目を向ける。
「お前ならさしたる苦労もなく勝てると思ってたんだ。だが、あんな化け物がいたとは完全に予想外だった。キツかっただろ……マジですまん」
すると、ルミアは小さく首を振って薄く微笑んだ。
「ううん、そんなことないです、先生。楽しかったですよ? 負けちゃったのはちょっと悔しいけど……私も皆のために戦えているんだって気持ちになれたから」
「……そうか」
そんな二人をそっちのけに、実況の話題は勝者インタビューに移ったようだった。観客の意識を、なんとかブーイングからそらそうと実況者も必死のようだ。
『えー、それでは、去年に続いて見事、精神防御の勝負を制した五組代表ジャイル君。何か一言お願いします』
「ふっ、流石だね、ジャイル君。……ん? ……ジャイル君?」
呼びかけても、まったく微動だにせず終始無言を貫くジャイルを不審に思い、ツェスト男爵がジャイルの顔を覗き込んだ。途端に、その顔色が変わる。
『おや? どうかしましたか? 男爵』
「じゃ、ジャイル君はすでに――」
『え? ジャイル君がどうしたんですか?』
「た、立ったまま気絶している――」
『…………は?』
今の今までグレンに対するブーイングの嵐だった場内が、再び静まりかえる。
『えーと? ということは……?』
「……ルミア君の勝ちだろう。棄権したとはいえ、第三十一ラウンドをクリアできなかったジャイル君に対し、ルミア君は一応、クリアはしたからね」
数瞬の間。そして――
『……な、なんとぉおおおお――ッ!? なんというどんでん返し! この勝負を制したのは紅一点、二組のルミアちゃんだったぁああああ――ッ!?』
再び爆音のような大歓声が渦巻いた。
「……せ、先生……?」
「……マジかよ」
突然のことにルミアもグレンも目を白黒させていた。
「やったぁ! やったじゃない! ルミア!」
「きゃ!?」
そんなルミアの背中に、誰かが体当たりするかのように抱きついた。
「システィ?」
「もう、無茶するんだから! もし、途中で辛くなったら我慢しないで大人しく棄権しろって言ったでしょ、この意地っ張り! ……でも、おめでとう。無事でよかった」
見れば、二組の生徒達が観客席から飛び降り、一直線に駆け寄って来てルミアを取囲み、その健闘を次々と口早に讃えてくる。
ルミアは困ったような表情を浮かべ、遠巻きにその様子を眺めるグレンに視線を送る。
グレンは口元を笑みの形に歪め、肩をすくめて、それに応じた。
ルミアは一つ頷いて、そして、クラスメイト達に振り返って――
「ありがとう、みんな!」
嬉しそうに笑うのだった。
それは何一つ曇りも憂いもない、花のような笑顔だった――
「……少しは安心したか? アリス」
セリカは、ルミアの試合を食い入るように見守っていたアリシアに声をかけた。
「……っ! ……はい」
アリシアは、自分の応対を務めるセリカとリックが一ヶ月前の事件の後、最高機密であるルミアの正体を知らされた者達だったことを思い出して、頷いた。
「あの子が、良き師、良き友人達に恵まれ、あんな風に笑う姿をこの目で確認することができて……本当によかった」
「ったく、あの子のことをそこまで母親として愛しているなら、どうして最初から私に声をかけてくれなかったんだ。私がどうとでもしてやったのに……」
「それは……」
「無茶を言ってはいかんよ、セリカ君。きっと陛下には陛下の事情があったのだろう」
リックが、たしなめるように口を挟む。
「わかってるさ。ただ、予言だの統治正統性だの王室権威の危機だの……そんな、くっだらない理由で実の母子が引き裂かれなきゃならなかったことにムカついただけさ」
「……そうですね、私は……母親失格ですね」
悔恨の表情でアリシアはうつむいた。
「アリスを責めてるわけじゃないさ。実際、お前はあの子を救うために相当無茶したんだろ? 王女が病気で崩御したように見せかけるために裏で物凄い工作をしたようだし、あの子の引き取り先も色々と手を回して……それにアイツから聞いたんだが――」
「いいんですよ。……いいんです」
アリシアは、しぃ~っと口元に指を当て、あいまいに微笑んだ。
「私が裏で何をしたとしても、私が帝国と王家の威信のために、あの子を捨てた事実は変わらないんですから……」
そんなことを言われてしまっては、セリカは何も言えなくなってしまう。
「今日はとても満足しました。ずっと気がかりだったあの子の元気な姿を、遠くからとはいえ、こうしてこの目で見ることができたんですもの。これから先、もう二度とあの子の姿を見る機会はないのでしょうが……きっと、私は大丈夫です」
「…………」
「後はあの子が幸せになってくれることを祈るばかりです。なんだか長年の胸のつかえが取れた感じ。ふふっ、これで明日から、なんの気兼ねもなく政務に励めますね」
「…………」
「あ、もう少し欲を言えば、あの子の花嫁姿を一目見てみたかったのですが……流石にそれは無理ですね。一市民の結婚式に女王が参列するわけにもいきませんし」
「…………」
「あ、そうそう、結婚と言えば……さっき、あの子の試合を止めるためにグレンが割って入りましたが、あの子のグレンを見る目、何か怪しくありませんでした? あの子、ひょっとしたら……ふふふ」
まるで自分を納得させるように続くアリシアの独白に。
「……それでいいのか? アリス」
セリカはストレートに核心を突いた。
「……え?」
「このまま遠くから見ているだけで、話も何一つせずに……本当にそれでいいのか?」
「それは……でも、そんなの無理なことで……」
「まったく、お前は私を誰だと思っているんだ?」
やれやれとセリカが肩をすくめた。
「私は、北大陸に名高き第七階梯(セプテンデ)、セリカ=アルフォネアだぞ? 全知全能――とまでは流石にいかんが、あらかたのことはできるんだぜ? 例えば、王室親衛隊の連中の目をごまかして、久しぶりに母娘水入らずで会う機会を作ってやる、くらいはな」
「……セリカ」
「で? どうするんだ? アリス。娘に会いたいのか? 会いたくないのか?」
セリカの誘いに、アリシアがどうしたものか迷っていると。
「今日、この時くらい、ご自分に素直になられてはいかがでしょうか? 陛下」
意外なことに、迷えるアリシアに助け船を出したのは、先刻から静かにアリシアの背後に控え、ことの顛末を伺っていたエレノアだった。
「エレノア?」
思い出のロケットすら置いていくよう進言したあの慎重深いエレノアが、まさかそんなことを言い出すとは思わなかったので、アリシアは驚きに目を瞬かせていた。
「大丈夫ですよ、セリカ様は大陸屈指の魔術師。きっと悪いことにはなりませんわ」
「ほら、お付きの者はこう言ってくれてるぞ?」
我が意を得たりとセリカがいたずらっぽく笑う。
学院長リックは、その強引なセリカの手引きに、密かに苦笑をこぼしていた。
学院生徒達で賑わう魔術競技場――その観客席を通う通路の一角にて。
黒を基調とした揃いのスーツと外套に身を包む、奇妙な男女の二人組がいた。
一人は二十歳ほどの青年だった。藍色がかった長い黒髪の奥から、鷹のように鋭い双眸が覗いている。すらりとした長身で痩せ肉だが骨太。その物腰は、落ち着いていると称するよりはむしろ冷淡さを色濃く感じさせ、ナイフのように触れてはならない致命的な鋭さをどこかに隠している――そんな雰囲気の男である。
もう一人はまだ十代半ばの少女だった。ろくに櫛も通されてない伸び放題の青髪を後ろ髪だけうなじの辺りで雑に括り、印象的な瑠璃色の瞳は常に眠たげに細められている。華奢で小柄なその肢体や、精巧に整ったその細面はアンティーク・ドールを想起させる。笑えばさぞかし魅力的に映るのだろうが、その相貌には表情という表情が死滅しており、いかなる感情の欠片すらも読み取れない。
二人が着用する外套は要所要所を金属板やリベット、護りの刻印ルーンなどで補強されており、明らかに魔術戦用のローブであることがわかる。
そんな二人の姿は、学院の生徒達で賑わう観客席において特に異彩を放っていた。衣装もそうだが、何より身に纏う雰囲気が明らかに堅気のものではない。
だが奇妙なことに、その二人に対して奇異の視線が集まることはない。まるで二人が道端に落ちている石であるかのように、その存在が気に留まらないようだった。
「――グレン、だな」
ぼそり、と。青年が冷淡に呟いた。
「……ん。どう見てもグレン」
それに応じるように、少女も感情の色が見えない呟きをこぼす。
二人の視線が注がれる先には、たった今、『精神防御』の終わった中央競技フィールド上で、金髪と銀髪の少女二人に挟まれて何か言い合いをしているグレンの姿があった。
「俺達に何も言わずに去って行ったと思ったら……こんな所に居たとはな」
青年が冷酷に獲物を見定める猛禽のような目でそう言うと、青年の隣の少女は無言で音もなく、グレン達がいる中央のフィールドに向かって歩き始めた。
「待て」
威嚇するような固い声と共に青年は手を伸ばし、少女の後ろ髪を無慈悲に掴む。
がくん、と少女の頭が引っ張られ、後ろに傾いだ。
「……何をするの? アルベルト」
無表情を微塵も揺るがさず、少しも感情をにじませず、少女が青年に問う。
「それは俺の台詞だ。何をする気だ? リィエル」
青年は青年で、その険しい猛禽の表情を微塵も揺るがさず、端的に問い返す。
すると、リィエルと呼ばれた少女はさも当然とばかりにこう答えた。
「決まってる。……グレンと決着をつけに行く」
ぐい、と。青年――アルベルトは掴んだリィエルの後ろ髪をさらに引っ張った。
「痛い。どうして引っ張るの?」
言葉とは裏腹に、まったく痛くなさそうに、リィエルは淡々と応じた。
「余計な事はするな。任務を忘れたのか?」
「任務?」
リィエルが少し考え込むように間を置いて。
「……グレンと決着をつけること?」
「……………………」
アルベルトが険しい表情を微塵も揺らさず押し黙る。二人の間に沈黙が流れる。
「……今回、俺達に与えられた任務は二つ。その内の一つは、今、女王陛下の護衛を務める王室親衛隊の監視だ」
「なぜ? 彼らはわたし達の仲間」
「俺達は一枚岩じゃ無い。王室直系派、王室傍系派、反王室派、過激派極右、保守的封建主義者、マクベス的革新主義左派、帝国国教会右派……さらに、それぞれに青い血側と赤い血側……アルザーノ帝国は様々な思想主義と派閥が渦巻く混沌の魔窟だ」
「そう。わたしにはよくわからないけど」
「だろうな」
また、二人の間に沈黙が流れる。
「右派の筆頭、王室親衛隊に最近不穏な動きがあるとの情報が入った。異能者差別に対する新しい法案が円卓会で閣議されるようになって特に顕著になったとの事だ」
「どうして?」
「世間一般的に、異能者は悪魔の生まれ変わりだと信じられている。そして、法は女王陛下の名の下に発令されるものだ。つまり、異能者を女王の名の下に法的に保護する事は神聖なる王室の威光に傷がつく、と考えているからだ」
「そう。わたしにはよくわからないけど」
「だろうな」
さらに、二人の間に沈黙が流れる。
「よって、俺達は王室親衛隊を監視している。その確率は限りなくゼロに近いが、今回の陛下の学院訪問を機に、連中は陛下に対し、何らかの行動を起こす可能性がある。もし、そんな事態になれば、政府上層部の派閥争いに重大な影響を及ぼす事になるだろう」
「なるほど、わかった」
リィエルは一つ頷いて、合点がいったように言った。
「話をまとめると、わたしはグレンと決着をつけなければいけない……そういうこと?」
「……………………」
アルベルトが険しい表情を微塵も揺らさず押し黙る。再び二人の間に沈黙が流れる。
「……ん。頑張ってくる」
「頑張るな」
再び歩き始めたリィエルの後ろ髪を、アルベルトが再び容赦なく引っ張った。
「アルベルトはグレンに会いたくないの?」
二度邪魔されたリィエルが、淡々と問う。
「……知れた事を。あの男には色々と言いたい事がある」
アルベルトは言葉尻に怒気を微かに滲ませて言った。
「そう。なら、わたしがグレンをボコる。アルベルトは色々言いたいことを言えばいい」
「だから、待てと言っている。俺達はあいつに会わない方がいい」
「なぜ?」
「久々、あいつの姿を見てわかった。あいつの居るべき世界は……やはり俺達が居るような血に濡れた闇の世界ではなかったらしい」
二人は再び競技場に目を向ける。何があったのか、グレンが銀髪の少女の足下で土下座している。金髪の少女が何かを言いながら銀髪の少女をなだめているようだ。
「あいつの居るべき場所は、あそこだ。眩い陽の光が当たるあの場所こそ、恐らくグレンという男が真に生きている場所なのだろう」
「女の子の足下が? それはなんとも面妖」
「……………………」
アルベルトが険しい表情を微塵も揺らさず押し黙る。さらに二人の間に沈黙が流れる。
「……?」
リィエルはそんなアルベルトの様子に、ほんの少しだけ小首を傾げて……
結局、奇妙な沈黙が二人の間に流れていった。
魔術競技祭は午前の部と午後の部に分かれており、その間に小一時間ほどの昼休みが入る。競技場に集まっていた生徒達は学院内の学食に行く者、学院外の外食店に赴く者、あるいは弁当を用意してきた者と分かれて、ぞろぞろと移動し始めていた。
グレンのクラスの生徒達も一旦解散し、昼食のために各自分かれて移動し始めている。
「はぁー……さて……俺はどうしたもんかね……?」
憔悴しきったような、何かを悟って諦めたような表情でグレンが呟いた。
腹が減っていた。とにかく腹が減っていた。冗談抜きにお腹と背中がくっつきそうだ。
クラスの生徒達の何人かは、持参した弁当を、この場でこれ見よがしに広げ始めている。この場にとどまるのは精神的にも辛かった。
とは言え、金がないので食事のアテはない。仕方なく、グレンはおいしそうな匂いが漂い始めたこの場からの戦術的撤退もかねて、今日もシロッテの枝――非常食になる――を拾いに行こうと席から立ち上がった。
「あ、あの……先生……?」
ふと、呼ばれて振り向けば、どこか小動物的な雰囲気を持つ小柄な少女が立っていた。グレンのクラスの生徒の一人、リンだ。
「……どうした? リン」
「そ、その……ちょっと相談したいことが……あって……その……」
「相談?」
グレンは頭をがりがり掻きながら周囲を見渡す。
「……その相談とやらはここじゃダメな類いのものか?」
「え? その、はい……できれば、あまり人のいない場所で……」
正直、七面倒臭かった。相談事に頭を回すエネルギーすら、今は惜しい。
だが、なぜか少し泣きそうになっているリンの様子を見て、流石に甲斐性なし男世界選手権代表グレンも邪険に扱うことはできそうになかった。
「……わかった。じゃ、場所を移すか」
そうして、グレンはリンを伴って競技場を後にし、学院中庭の方へやってきた。
青々と広がる芝生、庭師によってよく手入れの施された植樹達、端の方で色とりどりの花を咲かせる花壇。おなじみの光景がそこにはある。
普段は昼になるとこの場所は弁当を開く生徒で賑わうが、今日は競技場が開放されているため、そのまま競技場内で弁当を開く生徒が多い。それゆえに中庭は閑散としていた。
「で? その相談ってなんだ? 金以外のことなら大体、聞いてやるぞ」
「そ、その……」
リンがおどおどとしながら、少しずつ心の中をまとめるように呟いていく。
「あ、あの、私、『変身』の競技を任されているんですけど……その、自信がなくて」
「……はぁ?」
「変身の魔術は一生懸命練習してきたんですけど……今日になったら緊張してきて……全然、上手くいかなくなっちゃって……それで、私を他の誰かに代えてくれないかと……」
「…………」
「せ、せっかくクラスの皆が一丸になって一生懸命、優勝のために頑張っているのに……私が足を引っ張っちゃったら、皆に申し訳なくて……その……だから……私を、他の誰かに代えて……下さい……ッ!」
肩を震わせ、目尻に少し涙を浮かべてリンが懇願してくる。
グレンは頭をがりがりと掻きながら、ため息をついた。
「……お前はそれでいいのか? 本当は出場したいんじゃないのか?」
「そ、それは……」
「まずはそこをはっきりさせてくれ。じゃないと、なんとも言えん」
しばらくの間、リンは自分の心の内をさらうように押し黙って、そして――
「本当は……私も出たい……です……でも、皆に迷惑がかかるから……」
「じゃ、決まりだ」
グレンは、ぽんとリンの頭に手を乗せた。
「出ろ。何も問題ない」
「え!? で、でも! 私が出たら、皆に迷惑が――」
「あのなぁ、魔術競技祭。お祭りだぞ? お祭りに足を引っ張るも迷惑もあるもんか」
「で、でも、皆で優勝目指すって盛り上がってて……先生もそう言って……」
「……あー、そうか。あれがお前に気負わせちまったのか……」
グレンは自分の軽率な言動を今になって少し後悔した。
「確かにちょい身勝手な諸事情により、ついノリであんなこと言っちまったがな。もう、どーでもいいのさ。まずはお前らが目一杯楽しめりゃそれでいい。その上で優勝できれば最高だ。ま、その程度だよ。気にすんな」
「……そう……なんですか?」
「ああ。だから、お前も皆の足を引っ張るとか優勝のためとかうんぬんより、楽しんで来い。お前、変身の魔術、好きなんだろ?」
「は、はい……私……昔から気が弱くて、優柔不断だけど……変身の魔術は、その……なんだか違う私になれるようで……」
「なら、それでいいじゃねえか」
だが、グレンがここまで言ってもリンはどこか不安そうだ。
「……仕方ねーな。じゃあ、ちょっと、特別講義といこうか」
そんな自信なさげなリンに、グレンは気まぐれで、ちょいとお節介してやることにした。
リンは驚いて、うつむきがちな目をグレンに向ける。
「……特別、講義?」
「ああ。なぁ、リン。まずは復習だ。変身の魔術には二種類あったな。そう、【セルフ・ポリモルフ】と【セルフ・イリュージョン】だ。その違いがなんだかわかるか?」
少し考え込むように沈黙してから、リンが答える。
「え、ええと……【セルフ・ポリモルフ】は白魔術で、【セルフ・イリュージョン】は黒魔術です」
「ははは、それじゃ六十点だぜ?」
「す、すみません……え、えと……ええと……【セルフ・ポリモルフ】は……その、肉体の構造そのものを作り変えて変身する魔術で……【セルフ・イリュージョン】は光を操作することで変身したように見せかける幻影の魔術です」
グレンのダメ出しに、慌てて答え直すリン。
「まぁ、そんなとこだ。ゆえに【セルフ・ポリモルフ】は肉体と精神を操る白魔術、【セルフ・イリュージョン】は運動とエネルギーを操る黒魔術ってわけだ」
グレンは右腕の袖をまくって、三節のルーンで呪文を唱えた。
すると、その右腕がめきめきと変化する。筋肉がふくれあがり、黒い剛毛がびっしりと生えそろい、爪が伸び……あっという間に狼の前足になった。
「【セルフ・ポリモルフ】は術式で決まる。例えば狼に変身するなら狼に変身する【セルフ・ポリモルフ】、竜に変身するなら竜に変身する【セルフ・ポリモルフ】だ。そして、失敗すると元に戻れなくなってしまう危険性はあるが、変身したものの能力を得ることが可能だ。馬に変身すれば馬の速度で走れるし、鳥に変身すれば飛ぶことができるし、竜に変身すれば火が吹ける」
グレンが再び呪文を唱えると、狼の腕に変化した右腕は元に戻った。
「だが、【セルフ・イリュージョン】はそうはいかない。光を操作して、そう見せかけているだけだ。だから、馬に変身しようが鳥に変身しようが、速く走れるようにはならんし、空も飛べん。じゃあ、変身魔術としては【セルフ・ポリモルフ】の方が上か……と言えば必ずしもそうじゃない。えーと、そうだな……例えば……」
グレンがこめかみを指でつつきながら、【セルフ・イリュージョン】の呪文を唱える。
すると、グレンの周囲の空間が一瞬、ぐにゃりと揺らいで……グレンの姿の焦点があやふやになり……再び焦点が結像した時。
「る、ルミア……ッ!?」
そこにグレンの姿はなく、腕組みして不敵に笑うルミアの姿があった。とても幻影には見えない。その質感はルミアが本当にそこに立っているかのようだ。
「ま、こんなもんか」
声もルミアになっている。どうやら声の波長と周波数も即興で変えたらしい。
「呪文と変身対象が一対一対応している【セルフ・ポリモルフ】系の魔術とは異なり、【セルフ・イリュージョン】にはこの通り、術者のイメージを反映する術式が組み込まれている。つまり、イメージ次第で何にでも変身できるというわけだな。張りぼてだけど」
ルミアの姿と声で、仕草はグレンのまま、淡々と説明が続く。
「結論すると、【セルフ・イリュージョン】による変身が上手くいかなくなったってことは、まだイメージがあやふやだっていうことだ。逆に言えばイメージさえ固め直せば必ず上手くいく。俺の首を賭けてもいい」
にやりと、ルミアの姿のグレンが不敵に笑う。
「さて、リン。お前は【セルフ・イリュージョン】の呪文で『変身』の競技に参加する予定だったな? 何に変身するつもりだ?」
「え? ええと、天使様に変身しようかと……『時の天使』ラ=ティリカ様……」
「ったく、元ネタ自体が伝説上の存在とか、また難しいの選んだな……まぁ、いい。そういうことなら、今から学院の附属図書館に行って、聖画集でも借りてこい。競技開始までそれをずっと眺めてろ。それで大分違うはずだ」
「わ、わかりました。さっそくやってみます」
そして、最後にルミアに変身したグレンは、リンにまっすぐ向き直って言った。
「なぁ、リン。お前なら大丈夫だ。お前はお前が思っている以上に優秀だ。ちょっと自分に自信がないだけだ。お前の力は俺が保証してやる」
「せ、先生……」
「失敗しても気にすんな。優勝しろとは言ったが、どうせ祭りだ、祭り。誰も死にゃせんし、文句も言わん。もし負けて、それを責めるような奴がいたら、俺がそいつを鉄拳制裁してやる。だから気楽にな。わかったか?」
と、そこでリンはとうとうこらえきれなくなったかのように腹を押さえ、くすくすと含むように笑い始めた。
「……なぜ笑うんだ」
せっかく真面目に話したのにどうにも締まらず、グレンはふて腐れたように言った。
「だ、だって、先生がルミアの姿と声で男前なこと言うのが……おかしくて……」
「ぐぅ……そ、そうか……まぁ、そりゃそうだ……」
まったく、その通りだった。真面目なことを言うなら術を解いてから言うべきだった。
やれやれと、グレンが頭を掻きながら術を解こうとした、その時だった。
「ルミアったら、こんな所にいたんだ。探したわよ?」
中庭に、いつの間にかシスティーナがやって来ていた。
「あ、システィ。どうしたの?」
システィーナの存在にいち早く気付いたリンが応じる。
「あはは、私、ちょっとルミアに用があってさ」
「あ、いや、俺は……」
グレンが正体を明かす暇もなく、システィーナはグレンに笑いかけながら言った。
「早くお弁当食べよう? ルミア。言ったでしょ? 今日のお昼は私がルミアの分まで作っておいたって。ルミアの好きなトマトのサンドイッチもあるわよ?」
「え……? 弁当……?」
気付けば、システィーナは大きめのバスケットを手に提げている。
(まさか、この中には……ッ!?)
思わずグレンは喉を鳴らした。
「後はアイツなんだけど……アイツ、一体、どこ行ったのかしら……?」
システィーナが何かわけのわからないことを呟いているが、それどころではない。
弁当を作ってきたシスティーナが、変身魔術でルミアに変身したグレンを、ルミアと勘違いしている……これは、ひょっとして凄まじいチャンスなのではないだろうか?
上手く立ち回れば、システィーナが作ってきたサンドイッチをゲットすることができるのではないだろうか?
(……馬鹿な、冷静になれよ、グレン)
グレンは脂汗を額に浮かべながら、心の中でその邪な思考を一笑する。
(教師が、生徒のお弁当を騙し盗るだと? そりゃ流石に最低最悪じゃあねーか! いくらなんでも俺はそこまで堕ちたくねぇ! 堕ちてたまるものかぁッ!?)
「ルミア?」
頭を抱えてそっぽを向き、ぶつぶつ言い始めたルミア姿のグレンに、システィーナが小首をかしげる。
(そも、全部自業自得じゃねえか……そのシワ寄せを生徒達に向けるのは、教師というか男として、人としてどうなんだ? せっかくのチャンスだが、ここは素直に変身魔術を解いて、大人の対応を……)
と、その時だ。
ぐぅ~~。
グレンの腹が盛大に鳴った。
「ぷっ、あはは! ルミアったらそんなにお腹空いていたの?」
(……うん。やっぱ、背に腹は変えられないよね。俺は悪魔に魂を売った)
そして、ルミア姿のグレンはシスティーナに詰め寄って、その両肩に手をかけた。
「……今すぐここで食お……食べよう? 白ね……システィ! 俺……じゃねぇ、私、とってもお腹空いちゃってさーッ!、あは、あはははは……ッ!」
「な、なんか随分必死ね……」
不思議な威圧感を放つルミアの姿に、システィーナも額に脂汗を浮かべる。
「あっ。でも、ちょっと待って? その前にアイツを探さないと」
「え? アイツ?」
「そ、アイツ。その……せっかく、一応、私達の分を作るついでに、アイツの分も作ってやったわけだし……ホント、その、ついでのついでに仕方なく、だけど……」
ぷい、とあさっての方を向くシスティーナの頬にはほんの少し、赤みがさしていた。
「探さなくていい! アイツって誰かわかんないけど、探さなくていいって!」
「ルミア?」
「そんなことしてるうちにルミアに見つかったら……じゃなくて! わ、私、もうすっごくお腹空いちゃってさぁ! 早く食べないと割とマジで死んじゃうかも! だから――」
「あのぉ……先生……?」
あまりにも必死過ぎるグレンの背中を、リンが突っつく。
途端、グレンは今度はリンに取り縋り、リンにしか聞こえない声でまくし立てる。
(頼む、リン様! 武士の情けだ! 見逃してくれッ!)
(いえ、そうじゃなくて……)
(大丈夫だ! もちろん、ルミアの分を全部食べたりはしない! ほんの一切れ、二切れ、ご相伴に預かるだけだ! だから頼む! 今回ばかりは! 今回ばかりは~~ッ!)
(その……言いにくいんですけど……本物が……)
「……え?」
グレンが硬直した、その時だった。
「あ、システィ、ここに居たんだ?」
背後から、聞き覚えのある声がした。
「待たせちゃって、ごめんね。私、ちょっと用事があって……あれ?」
とことことやって来たルミアは、自分の姿をした何者かがそこにいるのを見て、小首をかしげた。
……………………。
圧倒的に気まずい沈黙が辺りを支配する。
「な、なんてことなの……俺……あ、私が二人!? ま、まさかどっちかがニセモノ……困ったわ! ここまでそっくりじゃ、どっちが本物かなんてわから……」
「《力よ無に帰せ》」
ぼそりと、システィーナが【ディスペル・フォース】を唱える。
たちまちグレンにかかっていた変身魔術が中和され、化けの皮が剥がれる。
「……まぁ、そういうわけで」
ふっ、と。
正体を暴かれたグレンが不敵に笑い、髪をかき上げ、くるりと踵を返す。
「グレン先生はクールに去るぜ」
そのまま何事もなく、歩き去っていこうとするグレンの背中に……
「こ、の、お馬鹿ぁあああ――ッ!」
システィーナが唱えた【ゲイル・ブロウ】の突風が容赦なく叩きつけられて……
「ぎゃあああああああああああああああああ――ッ!?」
グレンは情けない悲鳴を上げて、吹き飛んでいくのであった。
「信じられない! 最低! 教師が生徒のお弁当を掠め盗ろうとするとか、ありえないでしょ!? せっかく私が朝早く起きて……ふんっ! もう、知らないッ!」
顔を真っ赤にして、わめき立てるシスティーナ。ため息をつくリン。
状況をよく飲み込めず、ルミアは目をぱちくりさせるのであった。