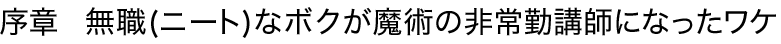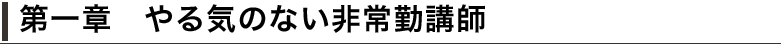それは、とある早朝の一風景。
「なんつーかさ。俺、つくづく思うんだよ。働いたら負けだなって」
長き修行の果てに悟りを開いた聖者のような表情で男——グレンは言った。気だるげに頬杖をつきながら、テーブルを挟んで正面に腰かける妙齢の女に穏やかな視線を送る。
「お前のおかげで俺は生きている。お前がいてくれて本当によかった」
グレンの視線を受け、女は優雅な振る舞いで組んでいた足を組み変えると、ティーカップを傾けながらこう返した。
「ふ、そうか。死ねよ、穀潰し」
さらりと毒を吐く女の細面には、可憐な微笑が花咲いていた。
「あっはっは! セリカは厳しいなぁ! ……あ、おかわり」
グレンはあっけらかんと笑い飛ばしながら、空になったスープの皿をずいっと目の前の女——セリカの鼻先に突きつける。
「清々しいな、お前は」
セリカは遠い何かに憧れるような表情で、やはり微笑んでいる。
「普通、働きもしない居候って、もうちょっと謙虚になるもんな」
「あー、今日のメシはちょっと塩味がきつかったぞ? 俺はもっと薄味の方がいいね」
「その上、ダメ出しとは恐れ入る」
セリカはしばらくの間、にこにこと笑って——
「《まぁ・とにかく・爆ぜろ》」
不意にルーン語で三節の奇妙な呪文を唱えた。
その刹那、耳をつんざく爆音が轟き、視界を紅蓮の衝撃が埋め尽くす。セリカが唱えた呪文によって起動した魔術の爆風が、グレンを容赦なく吹き飛ばしたのだ。その余波で高価な調度品が並ぶ豪華な食堂は一瞬にして無惨に半壊した。
「ば、馬鹿野郎! お前、俺を殺す気か!?」
真っ黒焦げになったグレンが床で、ごほごほと咳き込みながら、わめき散らす。
「殺す? 違うな。ゴミをかたす行為は掃除と言うんだぞ? グレン」
「子供の間違いを優しく諭す母親みたいなノリでひどいこと言うな!? せめて人間扱いして下さい!」
口の減らないグレンに、セリカは肩を落としてため息をついた。
社会的負け犬然としたグレンとは対照的に、セリカはいかにも超然とした美女だ。
外見は二十歳ほどだろうか。黄昏に燃える麦穂のように豪奢な金髪、鮮血を想起させる真紅の瞳。その相貌は間近からのぞき込めば、思わずぞっとするほど見目麗しく整っており、仄かに漂う妖しい色香が魔性を感じさせる。すらりと伸びる手足が艶めかしいその肢体は、まるで美術モデルのように、いかにも女性らしく過不足ない完璧なプロポーションを誇っている。身にまとうは丈長の黒いドレス・ローブ。貞淑な雰囲気を漂わせながらも、開放された胸元や、ベルトで強調されたボディラインはそれを超えてなお、艶美。
なんとも派手で妖艶な出で立ちだが、それを着慣らす圧倒的な器量と華がある——セリカはそんな、どこか浮き世離れした雰囲気の娘だ。しかし、その全身から醸し出される風格は高貴で誇り高い貴族のそれであり、さらに言えば二人が住む、この山のように大きな貴族屋敷の主人もセリカであり、グレンは単なる居候に過ぎない。
二人の社会的地位の格差は素人目にも歴然としていた。
「それはそうと、なぁ、グレン……お前、いい加減に仕事探さないか?」
セリカは真紅の瞳で、真っ直ぐとグレンを見下ろしながら言った。
よろよろ起き上がろうとしていたグレンの動きが一瞬止まる。
「お前が前の仕事を辞めて、私の家の居候になってから早一年。お前は毎日毎日、食って寝て、食って寝て、何をするでもなくぼんやりとするばかり。寿命の無駄遣いだぞ?」
ため息混じりのセリカに、グレンはやおら胸を張り、自信満々に応じた。
「大丈夫。俺は今の自分が好きだ。社会の歯車として緩慢に死に続けていた昔の俺より、今の俺の方がずっと輝いている!」
「何とどう比較したら、引きこもりの無駄メシ喰らいな生き様の方が輝いていることになるんだ、もう死ね、頼むから」
爽やかな笑顔で親指すら立てて見せるグレンに、もはやセリカは呆れるしかなかった。
「まったくお前と言う奴は……昔のよしみでお前の面倒を見てやっている私に少しは申し訳ないとでも思わないのか?」
「ふっ、何を水臭い。俺とお前の仲だろ?」
「《其は摂理の円環へと帰還せよ・五素は五素に・象と理を……》」
流石にキレたらしい。セリカは据わった目で何やら物騒な呪文を唱え始める。
「ちょ!? それ、【イクスティンクション・レイ】の呪文じゃねえか!? ま、待て!? それだけはやめて!? 粉々になっちゃう!? 嫌ァアアア——ッ!?」
それを見たグレンは高速で後退りし、焼け焦げた壁を背に声を裏返して悲鳴を上げた。
セリカはそんな情けないことこの上ないグレンの姿を前に、直接手を下すのもアホらしいとばかりに起動しかけていた魔術を解除した。
「まぁ、いい。お前ごときを魔術で処分するなんてそれは魔術に対する冒涜だからな。ゴキブリに伝説の剣を向けるようなものだ」
「ひどくね? それ。ゴキブリに失礼だろ」
「そっちかよ!? 一応自覚はあるのか、タチ悪いな、お前は!」
どっと疲れたように、セリカはがくんと頭を垂れる。
「まぁ、とにかくだ。そろそろお前も前に進むべきだと思う。いつまでもこうして時間を無駄にし続けるわけにもいくまい? お前自身も本当はわかっているんだろう?」
「つってもなぁ……今さら働くとして……一体、俺、何をやればいいんだ?」
グレンは子供のようにふて腐れて、そっぽを向く。
「お前がそう言うだろうことはわかっていた。だから、ここは一つ、私がお前に仕事を斡旋してやろう」
「仕事?」
「ああ。実は今、アルザーノ帝国魔術学院の講師枠が、ちょうど一つ空いてしまってな」
「魔術学院?」
グレンが怪訝そうに眉をひそめる。
「急な人事だったものだから、当分、代えの講師が用意できないんだ。で、だ。お前にしばらくの間、非常勤講師を務めてもらおうかと思っている」
「ちょっと待てよ。そこで、なんで俺なんだよ? あの学院、どうせ暇人な教授共がたむろってんだろ? そいつらに臨時講師やらせりゃいーじゃねーか?」
「まぁ、そう言うな。私達教授陣は近々帝都で開催される帝国総合魔術学会への参加準備で皆忙しいんだ。残念ながら今の時期、生徒達にかまっている余裕はない」
「あー、そういえばそんな時期か」
「とにかくだ。期間は一カ月、給与も特別に正式な講師並に出るよう計らう。一カ月のお前の働き次第で正式な講師に格上げすることも考えよう。どうだ? 悪くない話だろ?」
考えるまでもなく破格の条件だが、グレンは憂いに表情を曇らせていた。
「ふん……」
今までのふざけた調子をひそめ、自嘲気味に鼻で笑うと窓際へと歩いていく。
「……無理だな」
窓越しに遠くを見つめながらグレンはつぶやいた。
霞がかった朝空はどこまでも蒼い。窓の外にはいつものように鋭角の屋根の建物が立ち並ぶ古風な町並みと——そして、その遙かなる上空に浮かぶ、半透明の巨大な古城の偉容があった。
荘厳かつ勇壮な姿を誇るその古城の名は『メルガリウスの天空城』——この都市フェジテの象徴であり、近づくことも触れることも叶わぬ、なにゆえその城が空にあって、いつからそこに見えていたのかもはっきりしない、幻影の城だ。
「無理? なぜだ? グレン」
「わかるだろ? 俺には誰かを教える資格なんてないさ……」
そう語るグレンの背中はどこか寂しげに煤けていた。
「そりゃ、資格ないよな。だって、お前、教職免許持ってないし」
「やめてよね、人がせっかく渋く決めてんのに現実を突きつけんの」
的確なセリカの突っ込みに、グレンは不満そうに唇を尖らせ抗議する。
「ま、資格うんぬんに関しては安心しろ。学院内における私の地位と権限でどうにでもなる」
「ちょ、おい!? 職権乱用!?」
「魔術講師としてのお前の能力は問題ないはずだ。お前だって昔はそれなりに魔術かじってたんだからな。どうだ? やってみないか?」
「どうしようかな……よーし、ボクちょっぴり不安だけど、ここは一つ、思い切って断っちゃおうかな♪」
立てた人差し指を唇に当てて首をかしげる、女の子がやれば可愛い仕草をするグレン。
「この上なくキモウザイな、そのリアクション。しかも断るのか。心底、死ねと思った」
ぴきぴき、とセリカのこめかみに青筋が走った。忍耐の限界も近そうである。
「ちなみに、お前に拒否権はないからな」
「ほう? 嫌だと言ったら?」
「稲妻に撃たれるのが好みか? それとも炎でバーベキュー? あぁ、氷漬けも候補としてあげようか?」
「ふっ、言葉が通じなければすぐ暴力か? それが根本的な解決になるのか?」
「忌々しいほど正論だが、お前に言われたくないわ!」
すごご、と凄まじい魔力がセリカの掌に集まっていく。
「馬鹿が。まだお前は俺の本当の恐ろしさをわかっていないようだな……」
だが、グレンはそれに微塵たりとも臆せず不敵に笑って、セリカに向き直る。
「お前は知っているはずだ。俺が『その気』になれば、お前程度の魔術師など、どうとでもできてしまうということを——」
「——ち」
グレンの言葉はセリカの表情に微かな緊張を走らせた。
「お前の安い脅しは俺を『その気』にさせてしまっただけだ——ッ!」
言うが早いか、グレンは床を蹴り、天井すれすれまで跳躍する。そのまま、ふわりと鮮やかに背面宙返りをして——セリカの足下に、両膝と両手と額で着地した。
「養ってくださいッ!」
見事なフライング土下座だった。
「……確かに私はお前に戦慄を覚えた」
「お願いしますセリカさん! 俺、絶対に働きたくないんです!? どうか養って下さぁあああいッ!? 靴でもなんでも舐めますからッ!」
「もうね……お前、人間としての誇りないの?」
「馬鹿が! 誇りでメシが食えるのか!? あぁ!? 言ってみろコラ!?」
「よりにもよって逆ギレか。もう、ホント殺したい」
「……ふっ、お前に俺を養う権利をやろう」
「死ね!」
土下座の体勢から見上げてくるグレンの顔面を、セリカは容赦なく踏んづけた。人には図太さで知られるセリカも、もはや涙目だった。
「ええい、とにかく働け! 働かないならもう出て行け! 出て行かないならマジで分解してやるぞ!? 私、もうお前のそんな情けない姿見るのこりごりなんだよ!?」
「あ、悪魔かお前は!? 俺は別に世界の平和なんて大それたことは望んじゃいない! ただ、ごく普通の平穏で平和な引きこもり生活を続けたい、それだけなんだ! そんなささやか願いを抱くのも罪なのか!? 大体、お前、俺を一生養うだけの金なんて余裕で持ってるんだからいいじゃん!?」
グレンは何ら悪びれることもなくダメ人間ぶりを発揮し続けている。
「それに、お前も知ってるだろ!? 俺が魔術のことを、名前を聞くのも嫌なくらいに大っ嫌いだってことを!」
「……グレン」
「とにかく俺はもう、絶対! 金輪際! 二度と魔術なんかに関わらないからな! へーんだ! 魔術講師なんかやるくらいだったら道端で物乞いでもやってる方がマシ——」
「《其は摂理の円環へと帰還せよ・五素は五素に・象と理を紡ぐ縁は乖離せよ》」
セリカが口早に呪文を紡いだ刹那、グレンのかたわらを光の波動が駆け抜け、何かが空間に吸い込まれるような音が壮絶に響き渡った。
グレンが波動の駆け抜けていった方向に目をやると、自分のすぐ横の壁に滑らかな切断面を持つ円形の大穴がごっそりと開いていた。明らかに物理的な破壊の結果ではない。言わば、消滅とでも表現すべき超常的な現象——魔術の為せる業だった。
「ち……狙いが甘かったか」
口をぱくぱくさせて硬直するグレンに、セリカは据わった目と掌を向けた。
「次は外さん……《其は摂理の円環へと帰還せよ・五素は五素に・象と理を……」
「ま、ママぁあああああああああああ——ッ!?」
こうして、半ば強制的にグレンの再就職先は決まったのであった。グレンが一年ぶりに手にした職は、栄えあるアルザーノ帝国魔術学院の非常勤講師。一ヶ月という期間限定のなんとも将来的に不安が残る職だった。
アルザーノ帝国。北セルフォード大陸は北西端、冬は湿潤し夏は乾燥する海洋性温帯気候下の地域に国土を構える帝政国家。
その帝国の南部、ヨクシャー地方にはフェジテと呼ばれる都市がある。
フェジテの最大の特徴はアルザーノ帝国魔術学院が設置された、北大陸でも有数の学究都市だという一点に尽きるだろう。魔術学院の設立と共に生まれ、魔術学院と共に発展した町、フェジテ。立ち並ぶ建物の造りは鋭角の屋根が特徴的な古式建築様式でまとめられ、重厚で趣深い町並みを演出している。その一方で、魔術的な素材や物品に対する、魔術学院の莫大な需要を受けて他所との交易も盛んに行われ、人の出入りも活発であるため、必定、常に国内流行の最先端を行く——新古の息吹に満ちた町だ。
微かに朝もや立ち込める、そんな町の一角にて。石畳の街路の脇に並ぶランプ式の街路灯、そのふもとに一人の少女がたたずんでいた。
綿毛のように柔らかなミディアムの金髪と、大きな青玉色の瞳が特徴的な、年の頃十五、六くらいの少女である。きめ細やかな肌はまるで上質のシルクのよう。清楚で柔和な気質がその容姿や立ち振る舞いから匂い立ち、その楚々と整った顔立ちはまるで聖画に描かれた天使のように可憐だった。一見、儚げな印象を見る者に与えながらも、同時にどこかに通う芯の強さを感じさせる——そんな少女だ。
一方、すれ違う誰もを振り向かせるその美しい容貌とは裏腹に、少女の衣装は少々奇妙だった。涼しげなベストにプリーツスカート、その上から羽織るケープ・ローブ……フェジテは夜になれば夏でも冷え込む気候区分下であるというのに、なぜかその衣装はやや軽装だ。そして、なぜか左手だけに手袋がはめられていた。
「~♪」
少女は誰かを待っているらしい。背中に背負った皮製カバンのベルトに手をかけ、機嫌良さそうにハミングしながら時間をつぶしている。
と、その時だった。
「……痛っ!」
背後から上がった苦痛の声に、何事かと少女が振り返る。
すると、そこには指を押さえて顔をしかめている一人の老人の姿があった。足元には落ち葉や小枝が詰められた金属バケツ。そして、火打石が落ちていた。
「ど、どうしたんですか? お爺さん」
見知らぬ老人ではあったが、少女は心配そうな表情を浮かべ、迷わず老人の元へと駆け寄った。
「おや? いやぁ、ははは……お嬢ちゃんには格好悪い所を見せてしまったのう」
心優しい少女を前に、老人は相好を崩し、照れ臭そうに苦笑いする。
「実は片付けたこのごみを燃やそうとしたのじゃが、わしとしたことが、手元が狂って火打石で指を打ってしまってのう……いやぁ、歳は取りたくないわい」
見れば、老人の指が少し腫れて血が出ている。かなり強く打ってしまったらしい。特に大事はなさそうだが、それなりに痛そうだった。
「やれやれ、帰ったら婆さんに薬草を出してもらわんとな……」
少女は老人の指の様子を確認すると、周囲をきょろきょろと見渡す。誰もいないことを確かめ、老人にいたずらっぽく微笑みかけながら人差し指を口元にあて、ウインクする。
「内緒ですよ? お爺さん」
「……ん?
首をかしげる老人の手を、少女は柔らかく取り、ルーン語で呪文を唱えた。
「《天使の施しあれ》」
すると、老人の手を包む少女の手が淡く発光し、光に包まれた老人の手の怪我がみるみるうちに癒されていく。
白魔【ライフ・アップ】。被術者の自己治癒能力を高めて傷を癒す白魔術だ。
「……お、おぉ……!?」
老人はその様子を、目を丸くして見つめていた。
「うん、よし。それから……《火の仔らよ・指先に小さき焔・灯すべし》」
少女は次に、黒魔【ファイア・トーチ】の呪文を唱えた。すると少女の指先に小さな炎が灯る。その小さな炎を金属のバケツの中に落とすと、中に入っていたごみが、めらめらと燃え始めた。
「お嬢ちゃん……今の不思議な力……話に聞く魔術ってやつかい?」
「はい。本当は学院外で魔術を使ったら罰則があるんですけど」
驚きながらも感心したような表情を浮かべる老人に、少女はぺろっと小さく舌を出して茶目っ気たっぷりに破顔した。
「そういえば、その服……あの奇妙な学院の生徒達の制服じゃな。お嬢ちゃんのお友達は皆、今みたいな不思議な術が使えるのかい?」
「はい。皆、私よりも上手で色々なことができますよ?」
「ほえぇ……便利なものじゃのう。わしらもそんな不思議な術が使えたら色々と楽になるんじゃがのう……」
「あはは、そうかもしれませんね。ところでお爺さん、私が魔術を使ったことは、その……できれば……」
「おうおう、内緒にしておけばいいんじゃろ? わかっとるよ」
「はい、ありがとうございます」
「なんの、こちらこそ。ありがとうな、お嬢ちゃん。助かったよ」
少女と老人が笑みを交わし合っていると。
「ルミア——っ! 遅くなってごめん——っ!」
遠くから駆け足の音が近づいてくる。見れば、通りの向こうから少女と似たような衣装に身を包んだ、もう一人の少女が駆け寄って来ている。
「おや、あの子は……お嬢ちゃんのお友達かね?」
「はい。今、私がお世話になっている家の娘さんで、私の親友です。それじゃあ、お爺さん。私、そろそろ行きますね? ごきげんよう」
「おう、お勉強、頑張ってな」
最後に少女は会釈をして老人に別れを告げ、駆け寄ってくる友人の元へ向かった。
早朝ゆえに閑散としたフェジテの表通り。
花崗岩で綺麗に舗装された道を、二人の少女は並んで歩いていた。
「もう、ルミアったら律儀なんだから……先に行っててって言ったのに……」
「うぅ、そんな……お嬢様を置いて行ったら、しがない居候に過ぎない私は、旦那様と奥様にお叱りを受けてしまいますわ……」
「馬鹿。冗談でもやめてよね、私達は家族なんだから」
「あはは、ごめん、システィ」
「それにしても、珍しいね。システィが忘れ物するなんて」
老人と別れ、友人と合流した少女——ルミアは隣を歩く友人を不思議そうに見つめた。
「そのせいで屋敷まで往復することになって、貴女まで待たせて……本当にごめん」
ルミアの隣で少し肩を落として、とぼとぼ歩く少女——システィーナは憂鬱そうにため息をついていた。
システィーナは純銀を溶かし流したような銀髪のロングヘアと、やや吊り気味な翠玉色の瞳が特徴的な、ルミアと同い年くらいの少女である。雪も欺く白い肌、彫像のように硬く精緻に整った端麗な容姿はいかにも誇り高く勝ち気そうで、まるで妖精のように凜々しく、眩い。今、その表情はいささか消沈しているものの、それでも涼やかながら凛とした覇気が、その立ち振る舞いの端々から見てとれる——そんな少女だ。
ルミア、そしてシスティーナ。二人の少女にはタイプこそ違うが、ただの町娘には決して真似できない、生まれながらの美と気品——華があった。着用している衣服こそ魔術学院の生徒が着る制服だが、なんの変哲もないはずの町の一角が、その二人がいる場所だけ社交界のように華やいでいるようだった。
「ひょっとして……システィ、やっぱり……あのことが響いてる?」
ルミアが心配そうにシスティーナの顔をのぞき込む。ルミアが知るシスティーナは、忘れ物をしてしまうなどという隙とは無縁の存在なのだ……基本的には。
「かも、……ね」
親友に心配かけまいと、システィーナは健気に笑みを作って応じる。だが、どうにも消せない憂鬱さが表情の端々に残っていた。
「やっぱり、残念でさ……ヒューイ先生、なんで急に講師を辞めちゃったのかなぁ?」
「仕方ないよ。先生にだって色々と都合があるもの」
「あぁ、惜しいなぁ……ヒューイ先生の授業は凄くわかりやすくて、質問にもちゃんと答えてくれて……凄くためになったのに……」
「それに凄く格好良い人だったもんね?」
「ばっ! 何を言ってるの! 格好良さなんて関係ないでしょ!?」
からかうようなルミアの言葉に、システィーナはぱっと頬を赤らめていた。
「私は誇り高き魔術の名門フィーベル家の次期当主として、魔術の勉強のために学院に通っているの! 講師に求めるものなんて授業の質だけよ!」
だが、システィーナのまくし立てに、ルミアは訳知り顔でくすくすと笑うだけだ。
「あ、そうそう、システィ。話は変わるけど、今日、代わりの人が非常勤講師としてやって来るみたいだよ?」
「……知ってるわ」
いかにも興味なさそうにシスティーナは応じた。
「せめてヒューイ先生の半分くらいは良い授業してくれるといいんだけど」
「そうだよね。ヒューイ先生の授業に慣れちゃうと、他の講師の方の授業じゃちょっと物足りない気がするよね」
二人がそんな会話を交えながら、十字路に差しかかった時だ。
「うぉおおおおおおお!? 遅刻、遅刻ぅうううううううううううッ!?」
目を血走らせ、修羅のような表情で口にパンをくわえた不審極まりない男が、右手の通路から二人を目掛けて猛然と走って来た。
「……え?」
「きゃあっ!?」
「な、何ィいいいッ!? ちょ、そこ退けガキ共ぉおおおお——ッ!」
勢いのついた物体は急には止まれない。そんな古典物理法則を正しく踏襲し、男が二人のいたいけな少女を轢き飛ばそうとしていた——その時。
「お、《大いなる風よ》——ッ!」
システィーナがとっさに一節詠唱で、黒魔【ゲイル・ブロウ】の呪文を唱えた。瞬時にその手から巻き起こる猛烈な突風が男の身体を殴りつけるようにかっさらい、そして——
「あれ——ッ!? 俺、空飛んでるよ——ッ!?」
首の角度を上に傾けなければ捕捉できないほど、男の身体は天高く空を舞い——放物線を描いて——通りの向こうにあった円形の噴水池の中へと落ちた。
遠くで盛大に上がる水柱を、二人の少女は遠巻きに呆然と眺めるしかなかった。
「あの、システィ? ……やりすぎじゃない?」
「そ、そうね……あはは……つい。どうしよう?」
二人の注視を受けながら男は無言で立ち上がり、ばしゃばしゃと水を蹴りながら噴水池から這い出る。そして、つかつかと二人の前まで歩み寄って、そして言った。
「ふっ、大丈夫かい? お嬢さん達」
「いや、貴方が大丈夫?」
男は爽やかな笑みを浮かべて精一杯決めているつもりなのだろうが、哀しいくらいに決まっていなかった。
妙な男だった。システィーナ達よりも、幾ばくか年上の青年だ。黒髪黒瞳、長身痩躯。容姿そのものに特筆する所はないが、問題はその出で立ちだ。仕立ての良いホワイトシャツに、クラバット、黒のスラックス。かなり洒落た衣装に身を包んでいる。だが、この男はこの服を着るのがどれほど面倒臭かったのか、徹底的にだらしなく着崩していた。服を選んだ人と、着用する本人が別人であったことが素人目に見ても明らかであった。
「あはは、道を急に飛び出したら危ないから気をつけた方がいいよ?」
「いや……急に飛び出して来たのは貴方だったような……」
思わずシスティーナが突っ込んだ、その時だ。
「だ、だめよ、システィ!」
ルミアが頬を膨らませてシスティーナと男の間に割って入る。
「この人ばっかり責められないよ! システィだって、いきなり人に向かって魔術を撃つなんて……一歩間違ったら怪我じゃすまなかったんだよ?」
「う……ごめんなさい」
バツが悪そうにシスティーナは目を伏せる。
「ほら、システィ。ちゃんとこの人に謝って」
「うん。あの……本当にすみませんでした。どうかご無礼をお許し下さい」
「まったく親の顔が見たいね! 一体、お前はどういう教育を受けているんだ? あ?」
「……こっちが下手に出れば、途端にこの態度……なんなの? この人」
「あ、あはは……ここは抑えて抑えて」
流石に若干引き気味のルミアも改めて男に向き直り、ぺこりと頭を下げる。
「本当に申し訳ありませんでした。私からも謝りますから許してくださいませんか?」
「あー、もう仕方ないな! 俺はちっとも悪くなくて、お前らが一方的に悪かったのは明確だけど、そこまで言うなら超特別に許してやらんでも……ん?」
ぶつぶつ愚痴をこぼしていた男がルミアを見て、何かに気づいたように眉根を寄せる。
「ん? ん?」
「あ、あの……私の顔に何かついていますか?」
戸惑うルミアに構わず、男はずいずいと顔をルミアに寄せていく。
いきなり、ぶしつけな視線をぶつけられてルミアは目を瞬かせた。
「いや……お前……どこかで……」
首をかしげながら男は指でルミアの額を突っつく。頬をむにーっと引っ張る。細い肩と腰をなで回し、前髪をつまみ上げ、目をのぞき込んだところで……
「アンタ、何やっとるかぁあああああああああああああああ——ッ!?」
システィーナ怒りの上段回し蹴りが男の延髄を見事に捉え、男を吹き飛ばした。
「ズギャァアアアアアアアアア——ッ!?」
情けない悲鳴を上げて男が地面を転がっていく。恐らく卸したてだったであろう男の衣服はずぶ濡れの上に、擦り切れて汚れて、もはや洒落た原型の見る影もなかった。
「不注意でぶつかってくるのはまだいいとして、何よ今のは!? 女の子の身体に無遠慮に触るなんて信じられないッ! 最ッ低!」
「ちょっと待て、落ち着け!? 俺はただ、学者の端くれとして、純然たる好奇心と探究心でだな!? やましい考えは多分、ちょっとしかないッ!」
「なお悪いわッ!」
「ごぼほぉっ!?」
脇腹に良い角度で刺さったシスティーナの拳に、男は悶絶する。
「ルミア、警備官の詰め所に連絡。この男を突き出すわよ。やっぱりただの変態だわ」
「え!? ちょ、勘弁してください!? 仕事の初日からそんなんなったらセリカに殺される! マジごめんなさい! 許してください! 調子乗ってすんませんでしたッ!」
確実に自分より年下であろう少女達の足元で、恥も外聞もなく土下座する情けない大の男の姿がそこにあった。
「あの……反省はしているみたいだし許してあげようよ」
「はぁ? 本気? 貴女って本当に甘いわね、ルミア……」
「ありがとうございます! このご恩は一生忘れません! ありがとうございます!」
そして、すっくと男は立ち上がり居丈高に言った。
「さて、お前達。その制服は魔術学院の生徒だろう? こんな所で何やってる?」
「許してもらえるとなった途端に、これよ……なんなの? この人」
「あ、あはは……」
もはや、呆れるしかない二人だった。
「今、何時だと思っている? 急がないと遅刻だぞ? わかっているのか? おぉ……今の俺、なんかスゲェ教師っぽい……」
自分の台詞に陶酔しているらしい男をよそに、少女達は顔を見合わせて首をかしげた。
「……遅刻? ですか?」
「嘘よ、そんなの。まだ余裕で間に合う時間帯じゃない?」
「んなわけねーだろ! もう、九時じゃねーか!」
男が懐から取り出した懐中時計をシスティーナの眼前に突き出す。
「その時計、ひょっとして針が進んでませんか? ほら」
システィーナも負けじと懐中時計を取り出し、男の眼前に突きつける。
時計の針が指すのは八時だ。
「…………」
しばらくの間、不思議な沈黙が両者を包み込む。
そして。
「撤収!」
「逃げた——ッ!?」
出会ったときと同様、男は猛然とした勢いで二人の前から走り去っていく。
チクショーッ! あの女、時計ズラしやがったなぁ!? などと意味不明なことを叫びながら遠ざかるその背中を、二人の少女は呆然と見送るしかなかった。
「な……なんなの? あの人」
「……うん。でも、なんだか面白い人だったね?」
「面白いを通り越して、だめ過ぎるわよ、アレは」
相も変わらず親友の感覚のズレっぷりにシスティーナは嘆息する。
「私はああいう手合いにはもう二度と会いたくないわね。見ててイライラするのよ、あんな情けないダメ男は! やっぱり容赦なく警備官に引き渡すべきだったかしら?」
「あはは……」
あいまいに笑うルミアを伴い、システィーナは学院への道を再び歩き始める。そして、そのままあの奇妙な変態男のことを忘れるように努めた。魔術師にとって記憶整理は基礎中の基礎だ。事実、システィーナの頭の中からその男の存在は見事に抹消された。
もっとも——後にその存在は再び強烈に記憶へ焼き直されることになるのだが。
「さてと、今日も一日頑張りましょう? ルミア」
「うん」
やがて歩く二人の前に、その敷地を鉄柵で囲まれた魔術学院校舎の壮麗な威容がいつものように現れるのであった——