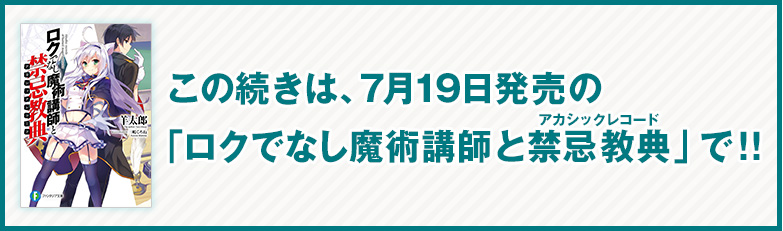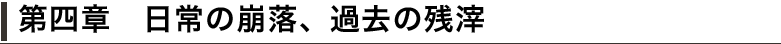――――。
――あっと言う間に時間が過ぎた。グレンの授業は別に、よくいる似非カリスマ講師の授業――奇抜なキャラクター性や巧みな話術で生徒達の心をつかむような物でも、やたら生徒達に迎合し、媚を売るような物でもない。ただ、教授する知識を真の意味で深く理解して、それらを理路整然と解説する能力があるゆえに為せる、本物の授業であった。
「……ま、【ショック・ボルト】の術式と呪文に関してはこんな所だ。何か質問は?」
グレンは小奇麗な文字や記号、図形でびっしりと埋まった黒板をチョークで突いた。
質問者は誰一人いない。グレンの存在感に圧倒されていることもあるが、質問の余地がないというのが本音だった。
「今日、俺が話したことが少しでも理解できるなら、三節を一節に切り詰めた呪文がいかに綱渡りで危険極まりない物だったか多少はわかったはずだ。確かに魔力操作のセンスさえあれば実践することは難しくない。だが、詠唱事故による暴発の危険性は最低限理解しておけ。軽々しく簡単なんて口にすんな。舐めてると、いつか事故って死ぬぞ」
そして、グレンはかつてないほどの真剣な表情を生徒達に向けた。
「最後にここが一番重要なんだが……説明の通り、魔力の消費効率では一節詠唱は三節詠唱に絶対勝てん。だから無駄のない魔術行使と言う観点では三節がやはりベストだ。だから俺はお前らには三節詠唱を強く薦める。別に俺が一節詠唱できないから悔しくて言ってるんじゃないぞ。本当だぞ。本当だからな?」
(やっぱり、悔しいことは悔しいんだ……)
その瞬間、生徒達の心中は見事に一致した。
「とにかくだ、今のお前らは単に魔術を使うのが上手いだけの『魔術使い』に過ぎん。将来、『魔術師』を名乗りたかったら自分に足らん物はなんなのかよく考えておくことだな。まぁ、お薦めはせんよ。こんな、くっだらねー趣味に人生費やすくらいなら、他によっぽど有意義な人生があるはずだしな……さて」
グレンは懐から懐中時計を取り出し、針を見る。
「ぐあ、時間過ぎてたのかよ……やれやれ、超過労働分の給料は申請すればもらえるのかねぇ? まぁ、いいや。今日は終わり。じゃーな」
ぶつぶつ愚痴をこぼしながらグレンは教室から退室していく。
生徒達はそれを放心したように見送る。ばたんと扉が閉まった瞬間、それがまるで合図であったかのように、生徒達は一斉に板書をノートに取り始めた。皆、何かに取り憑かれているかのような勢いだった。
「なんてこと……やられたわ」
システィーナが顔を手で覆って深くため息をついた。
「まさか、あいつにこんな授業ができるなんて……」
「そうだね……私も驚いちゃった」
隣に座るルミアも目を丸くしていた。
「悔しいけど……認めたくないけど……あいつは人間としては最悪だけど、魔術講師としては本当に凄い奴だわ……人間としては最悪だけど」
「あ、あはは、二回も言わなくたって……」
「でも……あいつ、なんで突然、真面目に授業する気になったのかしら? 昨日はあんなこと言っていたのに……あれ?」
何気なくルミアに目を向けて、システィーナは気づいた。
「ルミア……貴女、どうしてそんなに嬉しそうなの? なんか笑みがこぼれてるわよ?」
「ふふ、そうかな?」
「そうよ。なんかかつてないほど、ごきげんじゃない。何かあったの?」
「えへへ、なんでもないよー?」
「嘘よー、絶対何かあったってその顔は」
「えへへへ……」
何度聞いても、のらりくらりとかわして嬉しそうな微笑みを崩さない親友にシスティーナは首をかしげるしかなかった。
ダメ講師グレン、覚醒。
その報せは学院を震撼させた。噂が噂を呼び、他所のクラスの生徒達も空いている時間に、グレンの授業に潜り込むようになり、そして皆、その授業の質の高さに驚嘆した。
これまで学院に籍を置く講師達にとっては、魔術師としての位階の高さこそが講師の格であり、権威であり、生徒の支持を集める錦の御旗だった。だが、学院に蔓延する権威主義に硬直したそんな空気は一夜にして破壊された。まさに悪夢の日だった。
「セリカ君の連れてきた彼、凄いそうじゃないか!」
ごきげんなリック学院長の興奮気味な声が、学院長室に響き渡った。
「最初の十日はえらく評判が悪くて、どうなることやらと懸念してたが杞憂に終わったようで何より何より」
「……くっ」
ハーレイが悔しげにうめく。グレンが真面目に授業し出した日以来、自分が行う授業の出席率が微妙に目減りしたからだ。つまり、ハーレイの授業を欠席してまでグレンの授業に参加しようとする生徒がいるのだ。
「ふふふ……何を隠そう、グレンはこの私が一から仕込んだ自慢の弟子だからな」
ここぞとばかりにセリカは胸を張って宣言した。
「なんと! セリカ君、君、弟子を取っていたのかね!? 弟子は取らない主義じゃなかったのかな?」
「アイツが唯一の例外だ。ま、デキは悪かったけどな」
「ほう、なんとなんと。でも、なぜ今までそのことを隠されていたのかな?」
「ん? 決まってるだろ? グレンが講師としてダメダメだったら、師匠の私が恥ずかしいだろ? だから黙ってた」
「根本的に似た者師弟だな、あんたら!」
学院長室にハーレイのツッコミが虚しく響く。
「よせよ、ハーレイ。そんなに褒めても何も出ないさ」
「やかましい! 褒めてないわッ! この師匠バカめ!」
「いやぁ、グレンって魔術の才能は残念なやつなんだが、これがまた努力家でさー、あいつが子供の頃、お前には向いてないから別のことやれって何度言っても、アイツ、私みたいな凄い魔法使いになりたいって聞かなくてさぁー、それが今では三流とは言え、一応人並みの魔術師になっただろ? だから私は知ってたんだよなー、やればできる子だって。あ、そうそう、そう言えば、アイツに魔術を教え始めた頃、こんなことがあってな――」
にへらにへらと。
セリカは普段の鉄面皮からは信じられないほど緩んだ顔で、弟子自慢を始める。
まったくもって聞きたくも知りたくもないマル秘情報開示に、ハーレイはぶるぶると肩を震わせながら、こめかみに青筋を浮かべていく。
(おのれ……グレン=レーダスめ……ッ!)
ハーレイは苛立ちに打ち震えながら、ふと、つい先日の出来事を思い出す――
「おい、グレン=レーダス。おい、聞いてるのかグレン=レーダス! 返事をしろ!」
その日。
ハーレイは素行の悪さで有名なグレンを先輩講師として締め上げてくれようと、学院内廊下をのそのそ歩くグレンの背中に威圧的な言葉を浴びせかけた。
するとグレンは突然、きょろきょろと周囲を見渡し、ちらりとハーレイを一瞥すると、不思議そうに首を傾げ、ハーレイを無視して再び歩き始めたのだ。
「って、おい!? 貴様、なんだその『アイツは一体、誰に声をかけているんだ?』的な態度は!? グレン=レーダスはお前だろ!? お前しかいないだろ!?」
ハーレイはグレンの前に回り込んで進路を塞ぎ、凄まじい形相でグレンを睨みつけた。
「違います。人違いです」
「んなわけあるか!? この間抜けな面は間違いなくグレン=レーダスだッ! そもそもこの間、貴様の採用面接をしてやったのはこの私だろうがッ!」
「あ、誰かと思ったら先輩講師のハーレムさんじゃないっすか! ちぃ~っす!」
「ハーレイだッ! ハーレイッ! 貴様、舐めてるのか!?」
「いえいえ、そんなコトはないっすよ、えーと、ハー……何とか先輩」
「貴様、そんなに覚えたくないか? 私の名前……」
ハーレイは怒りと屈辱に身を焼き焦がしながらも、本題に入った。
「噂は聞いているぞ、グレン=レーダス。貴様、講師にあるまじき態度らしいな?」
「…………」
「調子に乗るなよ? 貴様が今のような破格の立場を享受できるのは貴様の器でも実力でもなんでもない! あの魔女……セリカ=アルフォネアの増上慢があってこその物であると知れ! いくらセリカ=アルフォネアが――」
「そのいちいち姓名合わせて呼ぶの疲れね?」
「やかましい! 話の腰を折るな! いくらセリカ=アルフォネアが神域の第七階梯(セプテンデ)に至った魔術師とは言え、このような横暴がいつまでも通るとは思わないことだ!」
「ですよねー? セリカって最近、調子乗り過ぎですよねー? ありゃいつか絶対、天罰下るわー」
「なんでそんなに他人事なのお前!? とにかく契約期間は一カ月だが、貴様、一ヶ月間もこの学院にいられると思うなよ!? あらゆる手を尽くして貴様をこの学院からすぐに叩き出してやる、覚悟しろ……ん?」
ハーレイが気付くとグレンはハーレイの前で深々とお辞儀をしていた。
「ありがとうございます! どうかよろしくお願いします! 俺、めっちゃ期待してますから頑張って下さい! えーと、ハー……? あ、ユーレイ先輩!」
「き、き、き、貴様ァアアアアアアアア――ッ!?」
……。
未だかつて、あれほどこの自分をコケにした輩がいただろうか。
(あんなふざけた男が講師としては私より格上だとぉッ!? 認めん! 認めんぞぉ!)
「それでさー、アイツが一生懸命頑張って、初めてその魔術を成功させてさー、セリカありがとうって泣きついてきてさー、いやー、可愛い時期もあったなぁー。とにかく、あの一件で私はアイツを見直したね。お前もそう思うだろ? ん?」
ハーレイの煮えたぎる胸中など露知らず、セリカの誰得弟子自慢は続いている。
本当に師弟そろって鬱陶しい連中だった。
(ぐぬぬ……おのれ、グレン=レーダスッ! いつか、絶対、この学院から追い出してやるぞ……ッ! 覚悟しろ……ッ!)
顔を真っ赤にして、ハーレイは打倒グレンを密かに誓うのであった……。
専属講師としてグレンがあてがわれたシスティーナ達二年次生二組のクラスはとにかく、学院の生徒達の羨望を集めた。教室で空いている席は日を追うごとに他のクラスからの飛び入り参加者で埋まっていき、さらに十日経つ頃には立ち見で授業を受ける者も現れた。
グレンが生徒達に一目置かれるようになるにつれ、学院の講師達の中には今まで自分達が行っていた『位階を上げるために覚えている呪文の数を増やすだけの授業』に疑問を持ち始める者も現れる。若く熱心な講師の中にはグレンの授業に参加して、グレンの教え方や魔術理論を学ぼうとする者もいた。
だが、自分がそんな注目を集めていることなど露知らず、相も変わらずグレンはやる気なさげな言動を繰り返しながら、今日も面倒臭そうに授業を行っていた。
「……魔術には『汎用魔術』と『固有魔術(オリジナル)』の二つがあって、今日はお前らが誰でも扱えるからと馬鹿にしがちな汎用魔術の術式を詳しく分析してみたが、固有魔術(オリジナル)と比較して汎用魔術がいかに緻密に高精度に完成された術なのか理解できたかと思う」
黒板に書かれた魔術式の一節をチョークで突きながらグレンは言った。
「そりゃ当然だ。【ショック・ボルト】みたいな初等の汎用魔術一つをとっても、お前らの何百倍も優秀な何百人もの魔術師達が何百年もかけて、少しずつ改良・洗練させてきた代物なんだからな。そんな偉大なる術式様に向かって、やれ独創性がないだの、古臭いだの……もうね、お前らアホかと」
授業の当初、固有魔術(オリジナル)こそ至高だと主張していた生徒達は肩を落とすしかない。
「お前らは個々の魔術師にオンリーワンな術である固有魔術(オリジナル)をとてつもなく神聖視しているが、実は固有魔術(オリジナル)を作るなんて全然、たいしたことじゃねーんだ。魔術師としちゃ三流の俺だって余裕で作れる。じゃ、固有魔術(オリジナル)の何が大変かと言えば、お前らの何百倍も優秀な何百人もの魔術師達が何百年もかけてやっと完成させた汎用魔術を、固有魔術(オリジナル)は自分たった一人で術式を組み上げて、かつ、それら汎用魔術の完成度をなんらかの形で越えてなければならないという一点に尽きる。じゃねーと固有魔術(オリジナル)なんて使う意味がない」
あからさまに意気消沈する生徒達を見て、グレンは底意地悪そうに笑った。
「ほーら、頭痛くなってきただろ? 今日見たとおり、お前らが小馬鹿にした汎用魔術はとっくに隙も改良の余地もない完成形だ。並大抵のことじゃ、固有魔術(オリジナル)は汎用魔術の劣化レプリカにしかならんぜ? 俺も昔やってみたけど、ロクなものができんかったから馬鹿馬鹿しくなってやめたわ。はっはっは、時間の盛大な無駄遣いだった」
この物言いに、くすくすと笑う生徒が半分、眉をひそめる生徒が半分。グレンの授業手腕は認めても、魔術に対して欠片の敬意も払わないその態度に反感を覚える者は多い。
「この領域の話になってくると、センスとか才能とかが問われるな。だが、それでも先達が完成させた汎用魔術の式をじっくりと追っていくことには意味がある。自身の術式構築力を高める意味でも、ネタ被りを避ける意味でもな。お前らが将来、自分だけの固有魔術(オリジナル)を作りたいなんて思っているなら、なおさらだ。ま、そんな屁の突っ張りにもならん自己満足に時間費やすくらいなら他に有意義な人生の過ごし方がある気がするがな……さて」
グレンが懐から取り出した懐中時計を見る。
「……時間だな。じゃ、今日はこれまで。あー、疲れた……」
授業終了を宣言するとクラスに弛緩した空気が蔓延し始める。
グレンは黒板消しをつかんで、黒板に書かれた術式や解説をおもむろに消し始めた。
「あ、先生待って! まだ消さないで下さい。私、まだ板書取ってないんです!」
システィーナが手を上げる。
すると、グレンは露骨にニヤリと意地悪く笑って、腕が分身する勢いで黒板を消し始めた。クラスのあちこちから悲鳴が上がる。
「ふはははははははは――ッ! もう半分近く消えたぞぉ!? ザマミロ!?」
「子供ですか!? 貴方はッ!」
システィーナは呆れ果てて机に突っ伏した。
「あはは、板書は私が取ってあるから後で見せてあげるね? システィ」
「ありがとう……しかしまぁ、良い授業してくれるのはいいんだけど、ホントあのねじ曲がった性格だけはなんとかならないかしら?」
システィーナが目を向ければ、黒板を消している最中にグレンは爪で黒板を引っかいてしまったらしい。耳を押さえて悶えていた。なんとも哀愁漂う間抜けな姿である。
「そう? 私、先生はあれでいいって思うな」
「ルミア……それ、本気?」
「うん、なんだか子供っぽくて可愛い人だと思う」
「私、貴女の感性、よくわからない……」
「……あ、先生!」
その時、突然ルミアが席を立ち、子犬のようにグレンの下へと駆けていった。
「あの、それ運ぶの手伝いましょうか?」
見ればグレンは分厚い本を十冊ほど抱えて、教室から出て行こうとする所だった。
「ん? ルミアか。手伝ってくれるなら助かるが……重いぞ? 大丈夫か?」
「はい、平気です」
「そうか……なら少しだけ頼む。あんがとさん」
グレンは本を二冊取ってルミアに手渡した。普段は決して見せない穏やかな表情をグレンはルミアに向けている。それを受けてルミアは実に嬉しそうに笑っている。まるで仲睦まじい兄妹のような光景。その様子を見ていたシスティーナはどうにも面白くない。
「ま、待ちなさいよ!」
渋々と言った表情でシスティーナもグレンに歩み寄る。
「ん? お前は……えーと、シス……テリーナ? だっけ?」
「システィーナよ! システィーナ! 貴方、わざと言ってるでしょ!?」
「へーいへいへい。そのシスなんとかさんがボクになんの御用でしょうか?」
「わ、私も手伝うわよ……ルミアだけに手伝わせるわけにもいかないでしょうが……」
「……ほう? じゃ、これ持て」
ニヤリと口の端を吊り上げて、グレンは持っていた残りの本をいきなり全部システィーナに押しつけた。
「きゃあっ!? ちょ、重い!?」
よろめいて倒れそうになるのをすんでの所で、こらえるシスティーナ。
「いやぁ、あはは、手ぶらは楽だわー」
それを尻目にグレンは意気揚々と歩き始める。
「な、何よコレ!? アンタ、ルミアと私でどうしてこんなに扱い違うの!?」
「ルミアは可愛い。お前は生意気。以上」
「この馬鹿講師……お、覚えてなさいよ――ッ!?」
背中に罵声を浴びながらも、グレンの口元は笑みを形作っていた。
生徒達がすっかりと帰宅した放課後。
グレンは一人学院の屋上の鉄柵に寄りかかり、閑散とした風景を遠目に眺めていた。夕日に燃え上がるフェジテの町並みは、紅に染め上げられた幻の城は、やはりあの頃と変わらない。変わったのは自分だけだ。
ふと、グレンはこの学院に非常勤講師としてやって来てからの日々を思い出す。なんと言っても強く思い出されるのは、自分によく絡んできた二人の少女の姿だ。
なぜか妙に懐いてくる、可愛い子犬みたいな少女、ルミア。
なぜか妙に突っかかってくる、生意気な子猫みたいな少女、システィーナ。
彼女達が何を思って自分のような人間に積極的に接してくるのかはわからない。だが、なんだかんだで彼女達との交流を心地良いと感じる自分がいなかったか?
それに見てみたいとも思ったのだ。彼女達がこれからどう成長するのか。どんな道を歩むことになるのか。
魔術と言うロクでもない物に新しい可能性を切り開いてくれるかもしれないルミア。
かつて自分が見失った魔術への情熱を胸に抱き、なんの迷いなく突き進むシスティーナ。
いまだ若く、そして幼い彼女達は何をやってくれるのか、どう成長していくのか。その手助けをしてやりたくないと言えば……嘘になる。
「まぁ、なんつーか……」
相変わらず魔術は嫌いだ。反吐が出る。こんなもの早くこの世からなくなるべきだ。この考えはきっとこれからも変わらないだろう。だが、こんな穏やかな日々は――
「悪くない……か」
自分でも気づかずグレンは笑みを浮かべていた。
「おー、おー、夕日に向かって黄昏ちゃってまぁ、青春しているね」
突然、背中に冷やかすような声を浴びせられ、グレンは首だけ回して振り返る。
「いつからいたんだよ? セリカ」
そこには淑女然とすました顔のセリカが静かにたたずんでいた。燃える紅に染まる美女。夕日に輝く麦畑を思わせる美しい髪が優しい風に揺れていた。
「さ、いつからだろうな? 先生からデキの悪~い生徒に問題だ。当ててみな」
「アホか。魔力の波動もなければ、世界則の変動もなかった。だったら、たった今、忍び足で来たに決まってる」
「おお、正解。あはは、こんな馬鹿馬鹿しいオチが皆、意外とわかんないんだよな。特に世の中の神秘は全部魔術で説明できると信じきっちゃってる奴に限ってね」
グレンの即答に、セリカは満足そうに微笑んだ。
「何しに来たんだよ? お前、明日からの学会の準備で忙しいんだろ?」
「おいおい、母親が息子に会いにきちゃ悪いのか?」
「なにが息子だ。俺とお前は元々赤の他人だっつーの」
「だが、私はお前がまだこんな、ちっちゃな頃からお前の面倒見ているんだ。母親を名乗る権利は充分にあるんじゃないか?」
「年齢差を考えろ魔女め。母親と息子っつーより婆さんと孫、下手すりゃ曾孫かそれ以上だろ」
セリカの外見はどこをどう見ても二十歳前後の妙齢の女だ。
だが、グレンはセリカが外見通りの年齢でないことは知っている。なにしろグレンとセリカは、グレンの幼少の頃からのつき合いだと言うのに、セリカの外見は出会った当初からまったく変化していないのだ。
セリカがなぜ歳を取らないのか。本当は一体何歳なのか。セリカは自身について頑なに語ろうとしないが……三桁は確実に達しているだろうとグレンは踏んでいる。
「あーあ、子供の頃はあんなに素直で可愛い男の子だったのに、今じゃこんなスレた男になっちゃって……時の流れは残酷だな」
「……放っとけ」
ふて腐れたようにグレンはセリカから視線を外した。
「元気が出たようで……よかった」
「はぁ?」
意図のわからないセリカのつぶやきに、グレンは間抜けな声を上げた。
「お前、気づいてないのか? 最近のお前、結構生き生きしてるぞ? まるで死んで一日経った魚のような目をしている」
「……おい」
「前は死んで一ヶ月経った魚のような目だった」
それを聞いたグレンはため息をついて頭をかいた。
「……心配かけたな。悪かったよ」
「いや、いい。私のせいなんだからな」
セリカは目を伏せ、いつもの自信に満ちた声とはかけ離れた、か細い声で言った。
「きっと、親馬鹿だったんだろうな。私はお前のことが誇らしかったんだ。だから――」
「よせよ。何度も言ったがお前は関係ない。浮かれてのぼせて現実を見てなかった俺が馬鹿だっただけだ」
「でも、お前はまだ魔術を嫌悪してる」
その一言でグレンはようやくセリカの真意を悟った。
「……なるほどな。で、少しでも魔術の楽しさを思い出して欲しくて、魔術の講師か?」
グレンは思い出した。そう言えば、子供の頃の楽しかった記憶は、いつだってセリカと一緒に行った魔術の勉強や実験の中にあった気がする。
「ったく、お前、何年生きてんだよ? 意外とガキだよな。俺とお前を結びつけているのは魔術だけじゃねーだろ。確かに俺は魔術が嫌いになったが、だからと言ってお前まで嫌いになることはありえねーよ」
「そうか。うん、そうだよな……よかった」
グレンの言葉を聞いてセリカは穏やかに笑った。どこか晴れやかな笑みだった。
「あー、くそ、そういうことかよ。じゃあなんだ? 最初にそう言ってやれば、俺は非常勤講師なんぞにねじ込まれずに済んだのか?」
「馬鹿、それとこれとは別だ。いい加減、自分の食い扶持くらい自分で稼げ」
「あー、あー、聞こえなーい」
「このダメ男が……」
セリカは呆れたように肩をすくめて、言葉を続ける。
「まぁ、いい。何はともあれ、社会復帰が順調そうでなによりだ。その調子で例の病気も治しておけよ?」
「病気? 何、言ってんだ。俺は健康――」
「自分には他人と深く関わる資格がないと思ってる、なるべく他人を自分に近づけたくないと思ってる――それゆえにあえて他人の神経を逆なでするような態度を取ったり、好意を向けてくれる人を素っ気なくあしらう――そんな病気」
「…………う」
セリカの指摘に、グレンは脂汗を額に浮かべて頬を引きつらせた。
そして、セリカは底意地悪くにやにやしながら、肩をすくめてみせる。
「なぁ、グレン。お前の場合は過去が過去だが、それ、普通、子供の病気なんだぞ? その歳にもなってこんなに拗らせちゃって、まぁ。社会復帰ついでに、いい加減治し――」
「う、うっさいわい! 放っとけ!?」
羞恥で真っ赤になりながら、グレンは叫いた。
「大体、好意を向けてくれる人うんぬんってのは俺のせいじゃねーぞ!? ガキの頃からお前みたいなスタイル群バツの女に見慣れちまってたら、そんじょそこらの女に興味なんか持てるかっつーの!?」
「おや? ということは、つまり、お前は母親に欲情してたのか? このド変態」
嗜虐的で妖しげな笑みを浮かべながら、セリカが背後からグレンへと歩み寄って身を寄せ、両腕をグレンの首に絡めた。
「んなワケあるか! そして、いちいち母親面すんな! ええい、寄るな! 胸を押しつけんな! 耳に息を吹きかけんな! 気色悪い!」
「ふふ、つれない男だな。何、たかだか親子のスキンシップじゃないか」
そんなグレンの反応に、満足そうに口の端を釣り上げながらグレンから離れ、セリカはグレンに背を向けた。
「じゃ、私は明日からの魔術学会の準備があるからそろそろ行くぞ?」
「……ああ。帝国北部地方にある帝都オルランドまで行くんだろ?」
ぶすっとした態度でグレンが応じる。セリカのこの手の悪ふざけは今に始まったことではないので流して忘れるのが一番だ。
「そうだ。私を含めた学院の学会出席者は今夜、学院にある転送法陣を使って帝都まで転移する予定だ」
「早馬で三、四日かかる距離を一瞬で移動できるなんてな……やれやれ、魔術は偉大だ」
「まぁ、お前も明日からの授業、頑張れよ?」
「……は? 明日から学院は一週間休みだろ?」
想定してないことを言われ、グレンは焦った。
「俺は非常勤だから参加しないが、明日からお前達教授陣や講師達は揃って件の魔術学会だろ? それに合わせて学院は休校になるんじゃなかったか?」
「ああ、それ、お前の担当クラスだけ例外だぞ。なんだ? 聞いてなかったのか?」
「はぁ!?」
「お前の前任講師だったヒューイがある日、なんの前触れもなく突然、失踪してな。お前のクラスだけ授業の進行が遅れてんだ。だからお前のクラスだけその穴を埋める形で休み中に授業が入っているんだ」
「なっ……聞いてねーぞ!?」
「守衛が学院の門番している以外には、学院の関係者は明日からいないからな? お前、学院で変なイタズラすんなよ?」
「するかっ!? ……いや、ちょっと待て」
グレンはセリカの話の違和感に気づいた。
「前任の講師が……失踪? ちょっと待て。そりゃどういう意味だ?」
「どういう意味も何も……そのままの意味だよ。お前の前任だった講師、ヒューイ=ルイセンはある日、突然、失踪した。足取りはいまだにつかめない。行方不明だ」
「おい、話が違うぞ。ヒューイとかいう奴は一身上の都合で退職したって……」
「そりゃ、一般生徒向けの話だ。そもそも、正式な手続きで退職するなら、代わりの講師が一カ月も用意できないなんて事態は起こらんよ」
グレンはなんとも言えないしかめ面で頭をかいた。
「どーにも、きな臭い話になってきたな……」
「ま、近頃はこの近辺も何かと物騒だ。お前に心配はいらんと思うが、まぁ、私の留守中気をつけてくれ」
「……ああ」
失踪と言う言葉には確かに事件性が感じられる。だが、それが何か自分に影響するかと言えば間違いなくそんなことはない。だが、グレンはなんとなく心に棘のような不安が刺さった感覚が抜けなかった。
と、その時だ。
「あ、やっぱりここにいた! 先生!」
屋上への出入り口の扉が開かれ、もうすっかり見慣れてしまった、いつもの二人組が姿を見せた。片や笑顔で、片や仏頂面で。
「あれ? アルフォネア教授。ひょっとして、私達お邪魔でしたか?」
「いいや。私はもう上がるところだ。どうした? グレンに用か?」
「はい」
花のように笑ってルミアはグレンの前に歩み寄る。
不機嫌そうなシスティーナがそれに渋々続く。
「お前ら、帰ったんじゃないのか?」
「あ、私達、学院の図書館で板書の写し合いと今日の授業の復習をしていたんですけど、どうしても先生に聞きたいことがあるって……システィが」
「ちょ、ちょっと!? それは言わないって約束でしょ!? 裏切り者ッ!」
真っ赤になってシスティーナが怒鳴り立てるが、すでに後の祭りだった。
「ほーう? つまりなんだ? システィーチェ君。まさかまさか、君はこの稀代の名講師、グレン=レーダス大先生様に何か質問があるとでも言うのかね? んー?」
グレンは清々しいほど、なんの迷いもなく図に乗った。上から目線で、思わず拳を顔面のど真ん中にめり込ませたくなるような、実に腹立たしい笑いを浮かべている。
「だからアンタにだけは聞きたくなかったのよ! 後、私はシスティーナよ! いい加減覚えてよ!?」
「なーんか覚えにくいから、やっぱ、お前は白猫でいいや」
「ああ、もう――っ!」
とうとうシスティーナは涙目になってしまう。
「先生、今からお時間少しよろしいですか? 私もその部分、後で考えてみたら実はよくわかってなくて……」
「ああ、悪かったな、ルミア。俺も今日の授業に関しちゃ少し言葉足らずな所があった気もしたんだ。多分、そこだろ。見せてみな」
「だ、だから、私とルミアのこの扱いの差はなんなの……ッ!?」
「ルミアは可愛い。お前は生意気。以上」
「む、ムキィイイイイイ――ッ!」
やんややんやと騒ぎ立てる三人をしばらくの間、セリカは微笑ましく見守って。何かに安堵したようにそっと屋上を後にした。
グレンに頭を下げて教えを請うという屈辱の一時をなんとか耐えきったシスティーナは、その苛立ちと不機嫌さを隠そうともせず、ルミアを伴って帰路についた。
「……まったく、なんなのよ、あいつ!」
そんなシスティーナの心境とは裏腹に、フェジテの町はいつも通り平和そのものだ。夕方ゆえに閑散とした中央表通りに、システィーナの荒げた声は虚しく霧散していく。夕焼けの緋色が目に優しい、落ち着いた顔色の町並み。自分一人こうしてカリカリしているのが馬鹿みたいである。
「ルミアもホント、あいつのどこが良いわけ? 妙に気に入ってるみたいだけど!」
「え? だって、先生、優しいよ?」
「ええ、そうね! 貴女だけには、妙に優しいわね! 貴 女 だ け に は!」
腹立たしさのあまり、システィーナはぷるぷると拳を振るわせていた。
「普通、あそこまであからさまに、露骨に贔屓する!? いくらなんでも、もうちょっと人の目とか、世間体とか気にするものじゃない!? それなのにあいつったら……ッ!」
ルミアが、まぁまぁ、と苦笑いする。
「これは絶対、何かあるわ! そうだ! きっと、あいつ、ルミアの優しさに勘違いして、ルミアに邪な下心でも持っているに違いないわ! ええ、そうよ! きっとそう! いい? ルミア、あいつがいるときは私から離れちゃだめだからね!? あいつめ……ルミアに手を出したら、今度こそ、本当に容赦しないんだから……ッ!」
と、その時である。
「ふふっ」
ルミアが含むように笑い始めた。
「……どうしたの? ルミア」
「うん、その、システィがそこまで私の心配してくれているのが、おかしくて」
「心配するに決まってるじゃない、私達は家族なんだから!」
怒ったような素振りのシスティーナに、ルミアがぽつりとつぶやいた。
「三年前のこと、覚えてる?」
「三年前……貴女が私の家にやって来た頃よね? それがどうかしたの?」
なぜ突然、そんな話が出てくるのか。システィーナにはルミアの意図が読めない。
だが、ルミアは懐かしむような笑みを絶やさず、言葉を続けていく。
「あの頃の私達って、いつも喧嘩ばっかりだった」
「そ、それは……だってほら、あの頃のルミアって卑屈で、わがままで、泣き虫でさ……その、実の両親から捨てられた当時の貴女の心情を汲めなかった私も私だけど……」
気まずそうにシスティーナが頬をかく。
「そんなある日、私がシスティと間違えられて、悪い人に誘拐されちゃって」
「……そんな事件、そう言えばあったわね」
「私、なんとか無事に帰って来て、そうしたら、システィがいきなり抱きついてきて」
「……う」
「あの時は一晩中、一緒に抱き合って泣いたね。ごめんね、無事でよかった、って」
「…………ぅ、そ、それは……その……」
気恥ずかしさにシスティーナの顔が、夕日もかくやと言わんばかりに染まっていく。
「思えば、あの時からかな。私とシスティがこうして仲良くなったの」
そんなシスティーナに、ルミアは暖かな笑みを向けていた。
だが、ここまで聞いても、ルミアがどうして突然そんなことを蒸し返したのか、システィーナには見当もつかなかった。
「……どうしたの? 急に」
「なんかね、最近、よく昔のことを思い出すの」
そして、ルミアはシスティーナに少し切なげな笑みを向けた。
「……なんでだろうね?」
問われてもシスティーナにわかるわけがない。何が切欠で、ルミアが三年前のことを物思うようになったかなど、ルミアのその真意は知る由もない。ただ、ルミアにとって三年前の記憶は、色々な不幸が重なった辛い思い出であろうことはわかる。
だから――
「私達は家族よ」
ぽつり、と。システィーナは素直な思いを口にする。
「なんで貴女が突然、三年前のことを思い悩むようになったかはわからないけど、いつだって私はルミアの隣にいるわ。だからさ、その……」
照れたようにしどろもどろ言葉を紡ぐシスティーナに。
「……ありがとう、システィ」
ルミアは春風のように微笑みかけるのであった。
黄昏の夕日に燃える、フェジテの町並み。
二つの影が寄り添うように、どこまでも延びていた――
次の日。
「うぉおおおおおおお!? 遅刻、遅刻ぅうううううううううううッ!?」
どこかで見たような光景が、学院へと続く道中で展開されていた。
叫び声の主は言わずもがな、グレンである。
しかも今回ばかりは時計のズレはない。正真正銘の寝坊による遅刻だった。
「くそう! 人型全自動目覚まし時計が昨夜から帝都に出かけていたのを忘れてた!」
パンを口にくわえ、必死に足を動かし、ひたすら駆ける。
「つーか、なんで休校日にわざわざ授業なぞやんなきゃならんのだ!? だから働きたくなかったんだよっ! ええい、無職万歳!」
とにかく遅刻はまずい。遅刻したら小うるさいのが一人いるのだ。今は一刻も早く学院に辿り着くのが先決である。上手く行けば、なんとかぎりぎり間に合うかもしれない。
グレンは居候しているセリカの屋敷から学院までの道のりをひたすら駆け抜けた。表通りを突っ切り、いくつかの路地裏を通り抜け、再び表通りへ復帰する。
そして学院への目印となるいつもの十字路に辿り着いた時。
グレンは異変に気づき、ふと、脚を止めていた。
「……っ!?」
不自然なまでに誰もいない。朝とはいえこの時間帯なら、この十字路には行き交う一般市民の姿が少なからずあるはずなのだ。なのに、その日に限っては辺りはしんと静まりかえり、人っ子一人いない。周囲に人の気配すら感じられない。明らかに異常だった。
「いや、そもそもこれは……」
間違いない。周囲の要所に微かな魔力痕跡を感じる。これは人払いの結界だ。この構成ではわずかな時間しか効力を発揮しないだろうが、結界の有効時間中は精神防御力の低い一般市民は、この十字路を中心とした一帯から無意識の内に排除されるだろう。
(……なぜ、こんなものが、ここに?)
危機感がちりちりとこめかみを焦がすような感覚。こんな感覚は一年振りになるか。
グレンは感覚を研ぎ澄ませ、周囲に油断なく意識を払う。
そして。
「……なんの用だ?」
グレンは静かに威圧するように問う。
「出てきな。そこでこそこそしてんのはバレバレだぜ?」
グレンは十字路のある一角へ、突き刺すように鋭い視線を向けた。
すると――
「ほう……わかりましたか? たかが第三階梯(トレデ)の三流魔術師と聞いていましたが……いやはや、なかなか鋭いじゃありませんか」
空間が蜃気楼のように揺らぎ、その揺らぎの中から染み出るように男が現れた。
ブラウンの癖っ毛が特徴的な、年齢不詳の小男だった。
「まずは見事、と褒めておきましょうか。ですが……アナタ、どうしてそっちを向いているのです? 私はこっちですよ?」
「……………………別に」
グレンは気まずそうに自分の背後に出現した男へと改めて振り返る。
「ええーと。一体、どこのどちら様でございましょうかね?」
「いえいえ、名乗るほどの者ではございません」
「用がないなら、どいてくださいませんかね? 俺、急いでいるんですけど?」
「ははは、大丈夫大丈夫。急ぐ必要はありませんよ? アナタは焦らず、ゆっくりと目的地へとお向かい下さい」
噛み合わない男の言葉に、グレンは露骨に眉をひそめた。
「あのな……時間がないっつってんだろ、聞こえてんのか?」
「だから、大丈夫ですよ。アナタの行先はもう変更されたのですから」
「はぁ?」
「そう、アナタの新しい行先は……あの世です」
「――っ!?」
一瞬、グレンが虚を突かれた瞬間、小男の呪文詠唱が始まった。
「《穢れよ・爛れよ・――」
(や、やべ――ッ!?)
場に高まっていく魔力を肌に感じ、グレンの全身から冷や汗が一気に噴き出した。
先手を許してしまった。警戒を怠ったつもりはないが、これほどまでに問答無用の相手とは予想外だった。こうなればグレンの三節詠唱ではどんな対抗呪文(カウンター・スペル)も間に合わない。
(しかも、あの呪文は――)
とある致命的な威力を持つ、二つの魔術の複合呪文。しかも極限まで呪文が切り詰められている。呪文の複合や切り詰めができるのは超一流の魔術師の証だ。
「――朽ち果てよ》」
小男の呪文が三節で完成する。
その術式に秘められた恐るべき力が今、ここに解放される――
樹木と鉄柵で囲まれる魔術学院敷地の正門前に今、奇妙な二人組がいた。
一人はいかにも都会のチンピラ風な男。もう一人はダークコートに身を包む紳士然とした男だ。手ぶらなチンピラ男と異なり、ダークコートの男は巨大なアタッシュケースを手にしている。
「キャレルの奴、上手く殺ったかな?」
「上手くやったに決まっている。あの男が標的を討ち損じたことがあったか?」
「ケケケ、ねえな。ま、つーことは……」
「今、あの学院校舎内に講師格以上の魔術師は一人として存在しない」
「ケハハハ! 例のクラスで可愛い可愛いヒヨコちゃん達だけがぴよぴよ言ってるワケか! はーい、よちよち、お兄サン達が可愛がってあげるよー?」
「キャレルのことは放って置けばいい。我々は我々の仕事をするぞ」
その二人は言動も装いも、まるで印象正反対な者同士の組み合わせであり、さぞかし好奇の視線を集めそうだが、なぜかその日に限っては周囲に人が誰一人いなかった。
「うーん、レイクの兄貴。やっぱ、オレ達じゃ中に入れないみたいだぜ?」
チンピラ風の男が、一見、何も阻む物がないアーチ型の正門に張られている、見えない壁のようなものを叩きながらぼやいた。これは学院側から登録されていない者や、立ち入り許可を受けていない者の進入を阻む結界だった。
「遊ぶなジン。早くあの男から送られてきた解錠呪文を試せ」
「へーいへい」
と、その時だ。
「おい、アンタ達、何者だ!?」
正門のすぐ隣に据えられている守衛所から、守衛が二人の姿を見とがめてやって来る。
「学院敷地内には特殊な結界が施されているぞ。学院関係者以外は立ち入りが――」
その時、ジンと呼ばれたチンピラ風の男が、守衛の左胸に指を当て、一言つぶやいた。
「《バチィ》」
その瞬間、守衛はびくんと大きく身を震わせ、それが不運な彼がこの世界で耳にした最後の言葉となった。
「えーと、よし、これだな」
打ち捨てられた人形のように倒れ伏した守衛になど目もくれず、ジンは懐から一枚の符を取り出し、そこに書かれているルーン語の呪文を読み上げる。すると、ガラスか何かが砕けるような音が辺りに響き渡った。
「おおー、事前調査通りじゃん! さっすが!」
門を覆っていた見えない壁がなくなったことを確認し、ジンが子供のようにはしゃぐ。
「ふっ。あの男の仕事は完璧というわけだ」
「ま、時間かけただけあったもんね。じゃ、報告と行きますかい」
二人は正門を潜って学院敷地内に侵入。
ジンは懐から半割りの宝石を取り出し、耳にあてた。
「はいはい、こちらオーケイ、オーケイ。もう〆ちゃっていいよーん」
数秒後。正門から金属音が響き渡る。学院を取り囲む結界が再構築されたのだ。
「恐ろしいな、あの男は」
ダークコートの男――レイクが氷の笑みを浮かべた。
「仮にも帝国公的機関の魔導セキュリティをこうまで完璧に掌握するとはな」
「執念ってヤツかな? へへ、噂の魔術要塞もこうなりゃカタナシだぜ」
「さて、行くぞ」
二人は正面を見上げる。
左右に翼を広げるように別館が立ち並ぶ、魔術学院校舎本館がそこにあった。
「標的は東館二階のニ‐二教室だ」
「へーいへいっと」