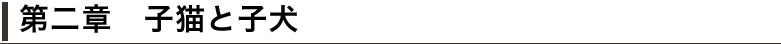「痛ぇ……マジで痛ぇ……こ、ここまでやるか? 普通……」
現在十二時過ぎ。昼休みの時間。
全身引っかき傷と痣だらけ、衣服ズタボロの姿となったグレンが、涙目でゾンビのようによろよろと学院内廊下を徘徊していた。すれ違う生徒達が無様な姿のグレンを見てぎょっとするが、人の目を気にしている余裕は今のグレンにはない。
「しっかし、最近のガキ共は発育が良いな……一体、何を食ったらあんなにすくすく育つんだ? ……一人発育不良なのもいたけど。まぁ、いいや、メシだ、メシ」
と、当の本人に聞かれたら命を落としかねない恐ろしいセリフをつぶやきながら、グレンは魔術学院の食堂へと足を運んでいた。
アルザーノ帝国魔術学院の食堂は、巨大な貴族屋敷のような学院校舎本館の一階に存在する。出される料理は安くて美味しいと、生徒達からは伝統的に評判がある食堂だ。
「ここを利用するのも久しぶりだなー」
食堂内には、白いクロスがかけられ、燭台で飾られた長大なテーブルが何列もあり、午前の授業を終えて食事を取りに来た生徒達で混雑していた。
基本的に、食堂の利用者は奥の厨房カウンターで料理を注文し、代金を支払って料理を受け取る。そして、各自、自由にテーブルに腰かけ、食事を取る。そういう方式だ。
グレンも奥のカウンターごしに、食堂のコックに向かって料理の注文をした。
「あー、地鶏の香草焼き、揚げ芋添え。ラルゴ羊のチーズとエリシャの新芽サラダ。キルア豆のトマトソース炒め。ポタージュスープ。ライ麦パン。全部、大盛りで」
グレンはいわゆる、やせの大食いと呼ばれる人種だ。おかげで無職のスネかじりだった頃、セリカに何度嫌みを言われたかわからない。
しばらく待っていると料理ができ上がった。グレンは皮袋の財布からセルト銅貨を数枚取り出して給仕の人に手渡し、木製お盆に乗せられた料理を受け取る。
「さて、空いている席は……と」
食事をする生徒達で賑わい、ほとんどの席が埋まっていたが、向かって右端のテーブルの隅、隣り合う席が二つほど空いているのが見えた。
誰かに席を取られてはかなわない。グレンは早足でそこに向かう。
そして、ふと、気づいた。
「だからおかしいのよ、去年発表されたフォーゼル先生の魔導考古学論文の説は。貴女もそう思わない? ルミア」
グレンが座ろうと思っていた席の正面に、見覚えある顔が二つ並んでいる。
「あの人の説だと、メルガリウスの天空城が建造されたのは、聖暦前4500年くらいになっちゃうの。確かに次元位相に関する術式が古代文明において本格的に確立したとされているのが古代中期なんだけど、フェジテ周辺で多々発見された古代遺跡の壁画や、発掘された遺物からすると、聖暦前5000年にはもうすでにメルガリウスの天空城らしきものが空に浮かんでいたってされてるの。この事実を無視して、魔導技術的に不可能だからってだけで、4500年説をごり押しするのはどうかと思うわけ。あの人が新しく考案した年代測定魔術は、どうもこの500年を誤魔化すために作られたこじつけのような気がしてならないわ! 机の上の思考や文献調査を過剰に重視するあまり、フィールドワークをおろそかにしがちな現代の魔術師らしい説ね。そもそも、古代中期の次元位相術式で、本当に天空城が空に隠されているのだとしたら、もうとっくに時間切れになってるはずじゃない? だって、当時の大気のマナ密度からして、エクステンション限界が――(略)――古代文明が滅ぶ切欠になった二度のマナの冬もあったし――(略)――マナ半減期の値だって矛盾――(略)――そもそも表意系古代語の経時進化過程に三つの素流分枝系統があるのは明らかで――(略)――要するに紋章象徴学的な意味合いとしての神と民間信仰の対立が――(略)――テレックスの神話分解論でも古代文明が単一文化じゃなくて――(略)――(略)――(略)――」
「そ、そうなんだ……」
食事も忘れてひっきりなしにまくし立てる銀髪の少女に、聞き手に徹していた金髪の少女――ルミアが、少し脂汗を垂らしながらあいまいな笑みを浮かべていた。
どうやら二人は魔導考古学議論の真っ最中(やや一方的だが)らしい。
魔導考古学とは、超魔法文明を築いたとされる聖暦前古代史を研究し、当時の魔導技術を現代に蘇らせることを目的とする魔術学問である。その中でも、特にメルガリウスの天空城に執心する魔術師達をメルガリアン、などと呼んだりする。
どうやら、あの銀髪の少女は典型的なメルガリアンのようだった。
「失礼」
一応、一言断って、グレンは金髪の少女の正面、銀髪の少女の対角線上の席に、どかっと腰を落ち着けた。
それで銀髪の少女はようやく我に返り、グレンの存在に気づいたらしい。
「――ッ!? あ、あ、貴方は――」
「違います。人違いです」
華麗にスルーして、グレンは食事を開始した。
鶏の香草焼きをナイフで適当な薄さに切り分け、ライ麦パンに細切りの揚げ芋とチーズサラダを挟んでかぶりついた。新芽サラダの苦みが炭火焼き地鶏の香ばしい脂とマッチして、さっぱりと食べられる。鼻孔をくすぐる香草の匂いも実に食欲をそそる。
「美味ぇ。なんつーか、この大雑把さが実に帝国式だなぁ……」
キルア豆のトマトソース炒めをスプーンですくって口に含む。唐辛子とニンニクが効いたトマトソースの風味が実に良い。
一方、先刻の事件からこの矢先、グレンのこのふてぶてしい態度に銀髪の少女――システィーナは口をぱくぱくさせるしかなかった。
かちゃかちゃ、と食器が鳴る音が響いていく。
意外なことに、重苦しい沈黙のまま進む、気まずい食事風景……とはならなかった。
「あの……先生ってずいぶん、たくさん食べるんですね? ひょっとして食べるの好きなんですか?」
「ん? ああ、食事は俺の数少ない娯楽の一つだからな」
「ふふっ、その炒め物、すごく美味しそう。なんだか凄く良い匂いします」
というのも、グレンの登場により、すっかり不機嫌そうに押し黙ってしまったシスティーナに代わり、なぜかルミアが積極的にグレンへ話しかけるからだ。
あからさまに敵意を向けてくるシスティーナと違い、このルミアという少女は、どうやら先ほどの事件をあまり禍根に思っていないようである。そう言えば、さっきもグレンに対する折檻には参加してなかったようだった。
「お、わかるか? ちょうどこの時期、学院に今年の新豆が入るんだ。キルアの新豆は香りが良いんだ。これを食べるなら今が旬ってやつさ」
グレンは自発的に人に話しかけるタイプではないが、話しかけられればそれなりにきちんと応じるタイプである。どうもルミアとの会話の相性は良いらしかった。
「そうなんですか? 私も今度、キルア豆の炒め物、食べてみますね」
「おう、マジお薦め。なんなら今、一口食ってみるか?」
「え? いいんですか? 私と間接キスになっちゃいますよ?」
小さく笑いながら、いたずらっぽく首をかしげ、指を唇に当てるルミア。
「ふん……ガキじゃあるまいし」
呆れたように肩をすくめ、グレンが豆炒めの皿を差し出す。
ルミアは嬉しそうに自分のスプーンで一杯それをすくって口に含んだ。
ルミアの気安く人懐っこい物腰や、常に笑みを絶やさない柔らかな雰囲気も手伝ったのだろう。グレンも気づかないうちに口元を笑みの形に緩めていた。
「……………………」
だが、その場においてただ一人、重苦しい雰囲気を放つ少女がいる。
システィーナである。彼女だけはルミアとグレンの談笑に参加せず、ただ刺々しい視線でグレンを射抜き続けている。
「……ところで、そっちのお前。お前はそんなんで足りるのか?」
流石にそこまで凝視されていると食べにくいので、グレンはため息混じりにシスティーナに話しかけた。突然、話しかけられたシスティーナは一瞬動揺したようだが、すぐに平静を取り戻し、きつめの言葉を投げ返してくる。
「食事に関して先生に文句言われる筋合いはないはずですけど?」
「とは言ってもな……」
グレンは少女二人の前の食事に眼を向ける。
ルミアのメニューはポリッジと呼ばれる麦粥と、香辛料の効いた鳩のシチュー、そしてサラダ……ルミアが比較的しっかり食べているのに対し、システィーナのメニューはレッドベリージャムを薄く塗ったスコーンが二つ、それだけである。
「お前、成長期だろ? 食わないと育たないぞ?」
実際に育ってねーし、とはこの状況において流石のグレンも言えなかった。
「余計なお世話です。私は午後の授業が眠くなるから、昼はそんなに食べないだけです。真面目ですから。まぁ、先生にはそんなこと、関係なさそうですけどね」
システィーナはグレンの前に並んだ大量の料理を一瞥して言い放った。
そんな挑発的な言葉に、グレンとシスティーナの間の空気が一気に重たくなる。
「……回りくどいな」
食事を続けるグレンの声が半オクターブ下がる。
敏感にそれを察知したシスティーナの表情に緊張が走った。
「言いたいことがあるなら、はっきり言ったらどうだ?」
「……わかりました。このままだとお互いのためになりませんからね。この際、はっきりと言わせてもらいます。私は――」
システィーナが、きっとグレンを正面からにらみつけて何か言いかけて……
「わかった、わかったよ。降参だ。そんな必死な顔すんなって」
「……え?」
グレンが突然、両手を上げた。
「そこまで思い詰めていたとは、流石の俺も予想外だよ……俺の負けだ」
あっけに取られるシスティーナを前に、グレンはスプーンでキルア豆を一粒すくうと、それをシスティーナの皿にちょこんと乗せた。
「ほれ、お前も食いたいんだろ? そんなにたくさんあるんだから少しくらい分けろ、だろ? ……まったく、いやしんぼめ」
呆れたようにシスティーナを流し見て、グレンは食事を再開した。
「……ち、ち、違いますッ! 私が言いたいのはそんなんじゃなくて――」
グレンのひどい勘違いに、システィーナは屈辱に肩を震わせ、机を叩いて立ち上がる。
だが、グレンはそれに一向にかまうことなく――
「代わりにそっちも少し寄こせ」
フォークを伸ばし、ざくりと、システィーナのスコーンの一つに突き立て、あっと言う間にかっさらった。
「うむ、たまに食うとスコーンも美味いな……」
「ああ――――ッ!? 何、勝手に取ってるのよ!?」
「いや、まぁ、等価交換?」
「ど こ が 等価なの!? どこが!? ええい、もう許さないんだから! ちょっとそこに直りなさい――ッ!」
「うぉわッ!? 危っ!? ちょ、おま、お食事はお静かにお願いします――ッ!?」
テーブルごしにナイフとフォークでチャンバラを始めるグレンとシスティーナ。
何事かと集まる周囲の痛い視線。
ルミアはそれを苦笑いで見守るしかなかった。
ありていに言えば、非常勤講師としてやってきたグレン=レーダスという男にはとにかく、やる気がなかった。
前任講師の後を引き継ぎ、二年次生二組の必修授業を全て受け持つことになったグレンだが、黒魔術に白魔術、錬金術に召喚術、さらに神話学、魔導史学、数秘術、自然理学、ルーン語学、占星術学、魔法素材学、魔導戦術論に魔道具製造術……ありとあらゆる授業が、いい加減で投げやりに行われた。なぜなのかは誰も知るよしはなかったが、不真面目に授業をやることに、ムキになっている節すら感じられた。
とにかく、この学院に関わる全ての人間達が等しく持っているはずである魔術に対する情熱、神秘に対する探究心という物が、グレンにはまるでなかったのである。
ゆえにグレンと生徒達、他の講師達の間には凄まじいまでの温度差が生まれ、余計な軋轢が生まれた。特にグレンが受け持ったクラスのリーダー格であるシスティーナは毎日ようにグレンに小言をぶつけた。だが、グレンのやる気ない態度が改善される気配は一向になかった。それどころか、むしろ日に日に悪くなっていく一方であった。
最初のうちはグレンも教科書の内容を一応説明し、要点を一応黒板に書き、授業のようなものを一応していた。だが、そのうち面倒臭くなったらしい。それが段々、黒板に教科書の内容をそっくりそのまま書き写すだけの作業になった。やがて、それも面倒臭くなったのか、ちぎった教科書のページを黒板に貼りつけていくようになった。
最終的にそれすらも面倒臭くなったらしい。グレンが黒板に教科書を釘で直接打ちつけ始めた時、とうとうシスティーナの怒りは頂点に達した。
グレンの講師着任から一週間、その日、最後の授業となる第五限目のことである。
「いい加減にして下さいッ!」
システィーナは机を叩いて立ち上がった。
「む? だから、お望み通りいい加減にやってるだろ?」
グレンは抜け抜けとそんなことを言い放ち、教科書を黒板に打ちつける作業を堂々と続けている。金槌を肩に担ぎ、釘など口にくわえている姿はまるで日曜大工だ。
「子供みたいな屁理屈こねないで!」
肩を怒らせ、システィーナは教壇に立つグレンにずかずかと歩み寄っていく。
「まぁ、そうカッカすんなよ? 白髪増えるぞ?」
「だ、誰が怒らせていると思っているんですか!?」
「ほら、そんなに怒るからその歳でもう白髪だらけじゃないか……可哀想に」
「これは白髪じゃなくて銀髪です! 本当に哀れむような顔で私を見ないで! ああ、もう! こんなこと、言いたくありませんけど、先生が授業に対する態度を改める気がないと言うなら、こちらにも考えがありますからね!?」
「ほう? どんなだ?」
「私はこの学院にそれなりの影響力を持つ魔術の名門フィーベル家の娘です。私がお父様に進言すれば、貴方の進退を決することもできるでしょう」
「え……マジで?」
「マジです! 本当はこんな手段に訴えたくありません! ですが、貴方がこれ以上、授業に対する態度を改めないと言うならば――」
「お父様に期待してますと、よろしくお伝え下さい!」
グレンは紳士の微笑を満面に浮かべていた。
「――な」
このグレンの反応に、システィーナは言葉を失うしかない。
「いやー、よかったよかった! これで一ヶ月待たずに辞められる! 白髪のお嬢さん、俺のために本当にありがとう!」
「貴方って言う人は――ッ!」
もうシスティーナの忍耐も限界だった。
システィーナには、このグレンという男が本当に講師を辞めたくてそんなことを言ったのか、それともフィーベル家の力を侮っているだけなのかは判断がつかない。
だが、どちらにせよシスティーナはもはや、このグレンという男の素行を看過することはできなかった。魔術の名門として誇り高きフィーベルの名において、魔道と家の誇りを汚す者を許しておくわけにはいかない。
ゆえに決断は早かった。システィーナ自身の若さと未熟さもそれを後押しした。
システィーナは左手に嵌めた手袋を外し、それをグレンに向かって投げつけた。
「痛ぇ!?」
手首のスナップをきかせて放たれた手袋は、グレンの顔面に当たって床に落ちる。
「貴方にそれが受けられますか?」
しん、と静まり返る教室の中、システィーナはグレンを指差し、力強く言い放った。
その様子を注視していたクラス中から、徐々にどよめきがうねり始める。
「お前……マジか?」
グレンも眉をひそめ、柄になく真剣な表情で床に落ちた手袋を注視している。
「私は本気です」
グレンを険しくにらみつけるシスティーナの元へ、ルミアが駆け寄った。
「し、システィ! だめ! 早くグレン先生に謝って、手袋を拾って!」
だが、システィーナは動かない。烈火のような視線でグレンを射抜き続ける。
「……お前、何が望みだ?」
その視線を受け、グレンが半眼で静かに問う。
「その野放図な態度を改め、真面目に授業を行ってください」
「……辞表を書け、じゃないのか?」
「もし、貴方が本当に講師を辞めたいなら、そんな要求に意味はありません」
「あっそ、そりゃ残念。だが、お前が俺に要求する以上、俺だってお前になんでも要求していいってこと、失念してねーか?」
「承知の上です」
途端に、グレンが苦虫を噛みつぶしたような、呆れたような表情になる。
「……お前、馬鹿だろ。嫁入り前の生娘が何言ってんだ? 親御さんが泣くぞ?」
「それでも、私は魔術の名門フィーベル家の次期当主として、貴方のような魔術をおとしめる輩を看過することはできません!」
「あ、熱い……熱過ぎるよ、お前……だめだ……溶ける」
グレンはうんざりしたように頭を押さえてよろめいた。
クラス中がハラハラしながら逼迫した二人の動向を見守っている。
グレンはシスティーナを見た。強気に見せてもシスティーナの身体は緊張でこわばっていた。それもそのはずだ。これから行う魔術儀礼の結果次第では、システィーナはグレンに何を要求されても文句は言えないのだから。
だが、それでもシスティーナはグレンに立ち向かったのだ。魔術への信念と、血の誇りにかけて。システィーナ=フィーベルはこの年齢にして誰よりも何よりも一流の魔術師だったらしい。
「やーれやれ。こんなカビの生えた古臭い儀礼を吹っかけてくる骨董品がいまだに生き残っているなんてな……いいぜ?」
グレンは底意地悪そうに口の端を吊り上げた。床に落ちている手袋を拾い上げ、それを頭上へと放り投げる。
「その決闘、受けてやるよ」
そして、眼前に落ちてくる手袋を横に薙いだ手で格好良くつかみ取ろうとして――失敗。グレンは気まずそうに手袋を拾い直した。
「ただし、流石にお前みたいなガキに怪我させんのは気が引けるんでね。この決闘は【ショック・ボルト】の呪文のみで決着をつけるものとする。それ以外の手段は全面禁止だ。いいな?」
クラス中が固唾を呑む中、グレンはルールを提示する。
「決闘のルールを決めるのは受理側に優先権があります。是非もありません」
「で、だ。俺がお前に勝ったら……そうだな?」
グレンはシスティーナを頭の天辺からつま先まで舐め回すように見つめる。そして、顔を近づけ、にやりと口の端を吊り上げて粗野な笑みを見せた。
「よく見たら、お前、かなりの上玉だな。よーし、俺が勝ったらお前、俺の女になれ」
「――っ!」
その一瞬。ほんの一瞬だけ、システィーナが慄いた。ルミアも息を呑んで青ざめた。
こんな要求があるかもしれないことは、システィーナも覚悟していたはずだ。が、それでもいざそんな取り返しのつかない言葉を聞くと思わず弱気が表に出たのだろう。
「わ、わかりました。受けて立ちます」
そんな一瞬の弱気を恥じるかのように気丈に搾り出した言葉もほんの少し震えていた。
グレンはシスティーナが微かな後悔と恐怖を強気の仮面で必死に取り繕い、一生懸命にらみつけてくる様をじっくりと堪能し、突然、腹を抱えて笑い出した。
「だははははッ! 冗談だよ、冗談! そんな今にも泣きそうな顔すんなって!」
「……っ!」
「ガキにゃ興味ねーよ。だから俺の要求は、俺に対する説教禁止、だ。安心したろ?」
その言葉をそばで聞いていたルミアは胸をなで下ろし、ほっと息をついた。
「ば、……馬鹿にして!?」
一方、自分がからかわれていたことを知ったシスティーナは、顔を真っ赤にしてグレンに食ってかかった。
「ほら、さっさと中庭行くぞ?」
それを適当にいなし、グレンは教室を出て行く。
「ま、待ちなさいよッ! もう、貴方だけは絶対に許さないんだから!」
肩を怒らせてシスティーナはグレンの背中を追った。
魔術師の決闘。それは古来より、連綿と続く魔術儀礼の一つである。
魔術師とは世界の法則を極めた強大な力を持つ者達だ。呪文と共に放つ火球は山を吹き飛ばし、落とす稲妻は大地を割る。彼らが野放図に争いあえば国が一つ滅びる。
そんな魔術師達が互いの軋轢を解決するために、争い方に一つの規律を敷いた。それが決闘である。心臓により近い左手は魔術を効率良く行使するのに適した手であり、その左手を覆う手袋を相手に向かって投げつける行為は、魔術による決闘を申し込む意思表示となる。そして、その手袋を相手が拾うことで決闘が成立する。もし、相手が手袋を拾わなければ決闘は成立しない。決闘のルールは決闘の受け手側が優先的に決めることができ、決闘の勝者は自分の要求を相手に一つ通すことができる。
この決闘方式を見ればわかる通り、決闘とは決闘を申し込む側より受ける側に相当の有利がつく。天と地ほどの実力差がない限り、誰もが安易に決闘を仕掛けることをためらう。古来より魔術師達は、こうやって魔術による私闘を極力律してきたのである。
だが、この決闘も帝国が近代国家として法整備を行った現在では形骸化された魔術儀礼に過ぎず、魔術師同士の争いを決闘で解決するなどと言う事態はめったに起こることではない。そんなことをするなら弁護士を雇って法廷で争う方がよほど効率的で拘束力がある。
それでも古き伝統を守る生粋の魔術師達の間では今もなお、決闘は行われ続けている。
例えば――魔術の名門フィーベル家の令嬢、システィーナのように。
等間隔に植えられた針葉樹が囲み、敷き詰められた芝生が広がる学院中庭にて。グレンとシスティーナの二人は互いに十歩ほどの距離を空けて向かい合っていた。
「ねぇ、カッシュ。君はどっちが勝つと思う?」
「心情的にはシスティーナなんだけど……でも、相手はあのアルフォネア教授、イチ押しの奴だからな……うーん……セシルはどう思う?」
クラスの生徒達や、講師と生徒が魔術決闘を行うという噂を聞きつけて集まった野次馬達が二人を遠巻きに取り囲み、そこはさながら即席の闘技場のようだった。
「さて、いつでもいいぜ?」
グレンは指を鳴らしながら余裕の表情でシスティーナを睥睨している。
対するシスティーナはグレンの挙動を注視しながら油断なく身構えている。その額を脂汗が伝い落ちた。
黒魔【ショック・ボルト】は、この魔術学院に入学した生徒が一番初めに手習う初等の汎用魔術だ。微弱な電気の力線を飛ばして相手を撃ち、その相手を電気ショックで麻痺させて行動不能にする、殺傷能力を一切持たない護身用の術である。
呪文を唱えれば、指差した相手を目掛けて指先から真っ直ぐに輝く力線が飛ぶ。なんの奇もてらわないストレートな術なだけに、【ショック・ボルト】の撃ち合いの勝敗は、いかに相手より早く呪文を唱えるかの否かの一点に集約される。
「ほら? どうした? かかってこないのか?」
「……くっ!」
基本的に魔術戦は後の先を取るのが定石とされる。現在の魔術には、あらゆる攻性呪文(アサルト・スペル)に対し無数の対抗呪文(カウンター・スペル)が存在するからだ。
だが、このグレンという男は【ショック・ボルト】の呪文しか使えないこの決闘において、システィーナに先に動くことを促している。呪文を速く唱えることが勝敗を分けるこの決闘で、だ。
考えられることはただ一つ、グレンという男は恐らく、自身の【ショック・ボルト】の詠唱速度に絶対の自信を持っているのだ。システィーナが先に最速で呪文を唱えても、それに競り勝てるくらいに節と句を切り詰めた詠唱呪文を持っているのだ。
察するに、このグレンと言う男は魔術戦に特化した魔術師なのだろう。そう考えれば、どうしてこんなロクでもない男が講師として学院に招かれたのか一応の辻褄は合う。全くなんの見所のない魔術師がこの学院で講師をできるわけがないのだから。
魔術を研究する腕前と魔術を実践する腕前は違う。魔術師としての位階は低くとも、魔術戦においては恐ろしく強かった魔術師は歴史を紐解けばいくらでもいる。
「おいおい、何も取って喰おうってわけじゃねーんだ。胸貸してやっから気楽にかかってきな?」
そう思い至ると、この余裕も歴戦の魔術師然としたものに見えてくる。グレンの言動が許せなかったとは言え、衝動的に決闘を申し込んだことをシスティーナは少し後悔した。
(でも、退けないわ)
システィーナは目前で余裕しゃくしゃくに構えるグレンを鋭くにらみつける。
(私が私である以上、こんな男を野放しにするわけにはいかないわ。例え無様に地を舐めることになっても、私はこいつに否を突きつける。それが私の魔術師としての誇り。……行くわよ!)
覚悟を決め、システィーナはグレンを指差し、呪文を唱えた。
「《雷精の紫電よ》――ッ!」
刹那、システィーナの指先から放たれた輝く力線が真っ直ぐグレンへ飛んでいき――
グレンは得意げな顔でそれを受け――
「ぎゃあああああ――っ!?」
バチンッと電気が弾ける音。
グレンはびくんッと身体を痙攣させ、あっさりと倒れ伏した。
「……あ、あれ?」
システィーナは指を突き出した格好のまま硬直し、脂汗を垂らした。
目の前にはシスティーナの呪文によって無様に地を舐めるグレンの姿がある。
「これって……?」
「あ、ああ……システィーナの勝ち……だよな……?」
決闘を遠巻きに眺めていた者達もこの結末にざわめいている。
まさか、あれほどの大口を叩いて、あれほど大物ぶっておいて、この程度なのか。この男は実戦に特化した魔術師じゃなかったのか。
「わ、私……なんかルール間違えた?」
助けを求めるようにシスティーナはルミアを振り返るが、ルミアは困ったように首を振るだけだ。
「ひ……卑怯な……」
と、その時、ようやく呪文のダメージから回復したグレンがよろよろと起き上がる。
「あ、先生」
「こっちはまだ準備できてないというのに不意討ちで先に仕掛けてくるとは……お前、それでも誇り高き魔術師か!?」
「え? いや、でも、いつでもかかって来ていいって……」
「まぁいい。この決闘は三本勝負だからな。一本くらいくれてやる。いいハンデだろ?」
「は? 三本勝負? そんなルールありましたっけ?」
「さぁ行くぞ! 二本目! いざ尋常に勝負だッ!」
強引に二本目の勝負が始まった。
あっけに取られるシスティーナの前で、今度はグレンが先に動いた。
「《雷精よ・紫電の衝撃以て・撃――」
「《雷精の紫電よ》――ッ!」
グレンの呪文が完成するより早く、システィーナの呪文が完成した。
「うぎょぉおおおおお――ッ!?」
バチバチと派手な音を立てて感電するグレン。再び地面に倒れ、ぴくぴくと身体をけいれんさせている。さっきの光景の焼き直しだった。
「や、やるじゃねーか……」
よろよろとグレンが立ち上がる。膝はがくがくと笑っており、見るからにやせ我慢だ。
「あの……グレン先生?」
「ふっ。いくらこの勝負が五本勝負だからって、ちょっと遊び過ぎたかな。俺、反省」
「さっき、三本勝負だって……」
ジト目でシスティーナがぼやいたその時だ。
「あああああ――ッ!?」
グレンが突然、声を張り上げる。
「嘘だろ!? あんな所に女王陛下がいらっしゃるぞ――ッ!?」
「えっ!?」
グレンが指差したあさっての方向を、システィーナは思わず目で追った。
「ふはは、かかったなアホが! 《雷精よ・紫電の衝撃以て・撃ち倒――」
「《雷精の紫電よ》――ッ!」
グレンの呪文が完成するより早く、やはりシスティーナの呪文が完成した。
「ぴぎゃぁあああああああああ――ッ!?」
ビリビリと感電し、のたうち回るグレン。
システィーナはこめかみを押さえながら言う。
「あの……ひょっとしてグレン先生って……」
「か、構えろ! まだ終ってないぞ!? なにせ七本勝負なんだからなッ!」
「はぁ……」
「《雷精よ・紫電の衝撃以て・撃ち――」
「《雷精の紫電よ》」
「ずぎゃぁああああああああ――ッ!?」
…………。
グレンが呪文を唱える。だが、それよりもいち早くシスティーナが呪文を完成させ、グレンを撃ち倒す。この単純作業が以下、延々と続いた。
と言うのも、グレンが長々とした呪文を詠唱しようとするので、どんな奇策を用いようともシスティーナが唱える短い呪文の方が早く完成するのだ。
そして、グレンが四十七本勝負と言い張った一戦が終った時。
「すみません。無理です。許して下さい。もう立てません。ていうかこれ以上続けるとボク、何かに目覚めちゃいます」
「はぁ……」
システィーナは大の字で痙攣するグレンを見下ろしながら、深いため息をついた。
「いやー、【ショック・ボルト】のみでの勝負なんて俺に超滅茶苦茶不利な不公平ルールだからなーッ! こんなルールじゃなかったら俺が圧倒的に圧勝したんだけどなーッ!」
「先生って本当に口が減りませんね」
もはや、呆れるしかない。
「そもそも、さっきから三節詠唱ばかり……ひょっとしてグレン先生って、【ショック・ボルト】の一節詠唱ができないんですか?」
「ふ、ふはは、な、なんのことだか、わわわ私にはサパーリ!? そもそも呪文を省略する一節詠唱なんて邪道だよね! 先人が練り上げた美しい呪文に対する冒涜だよね! 別にできないからそう言っているわけじゃなくて!」
「できないんだ……」
あまりもの情けなさにシスティーナは泣きたくなってきたが、気を取り直して当初の目的を思い出す。
「と、とにかく決闘は私の勝ちです! だから私の要求通り、先生は明日から――」
「は? なんのことでしたっけ?」
「え?」
予想外の返答にシスティーナは硬直する。
「俺達、なんか約束とかしましたっけ? 覚えてないなぁ~? 誰かさんのせいで、いっぱい電撃に撃たれたしなー?」
そう、目の前のグレンという男はシスティーナの想定を超えて遥かに最低だった。
このグレンの物言いに、システィーナは流石に色めき立った。
「先生……まさか魔術師同士で交わした約束を反故にするって言うんですか!? 貴方、それでも魔術師の端くれですか!?」
「だって、俺、魔術師じゃねーし」
「な……」
ぬけぬけとそんなことを言ってのけるグレンに、システィーナはもう絶句するしかない。
「魔術師じゃねー奴に魔術師同士のルール持ってこられてもなー、ボク、困っちゃう」
「貴方、一体、何を言ってるの……ッ!?」
システィーナにはもうこのグレンという男が全く理解できなかった。まさか、魔術の薫陶を受けた身でありながら、魔術師であることを否定するとは。この男には魔術師であることに対する誇りはないのか。魔術という世界の神秘を紐解く崇高なる智慧に対する敬意は欠片もないと言うのか。
「とにかく今日の所は超ぎりぎり紙一重で引き分けということで勘弁しておいてやる! だが、次はないぞ! さらばだ! ふははははははははははは――ッ! ぐはっ!」
まだ身体にダメージが残っているらしい。グレンは何度も転びながら、それでも高笑いだけは一人前に走り去って行く。
後に残されたのは、しらけきった観客達ばかりだ。
「なんなんだよ、あの馬鹿」
「まさか【ショック・ボルト】みたいな初等呪文すら一節詠唱できないなんてね」
「ふん、見苦しい人ですわね……」
「魔術師同士の決め事を反故にするなんて最低……」
誰も彼もがグレンを酷評する中、ルミアは心配そうにシスティーナの隣に歩み寄る。
「大丈夫? システィ。怪我はない?」
「私は大丈夫……だけど」
システィーナは険しい表情でグレンが走り去った方を見つめていた。
「心底、見損なったわ」
まるで親の敵のようにうめく。
システィーナはこう見えてグレンという男に一応の敬意を払っていた。グレンは先達の魔術師だ。確かに講師としてのやる気はないようだったけど、同じ魔術を志す者として、それでも何か学べるものがあるはずだと思っていたのだ。
だが、もうだめだ。あの男だけは許せなくなった。あの男は魔術を侮辱している。あの男がこの学院にいる限り、自分とあの男は不倶戴天の敵同士だ。
「グレン先生……」
ルミアは激しく憤る親友を前に、途方に暮れるしかなかった。